──中国には「余り男の時代」という言葉があるそうですが、どういう意味ですか?
ミン・ガオ氏(以下、ガオ):「余り男の時代」という言い方は、中国語で「剩男時代」と書きます。中国に推定3000万人から5000万人ほどいると言われる、結婚できない中国人男性たちを指すインターネット用語です。2020年頃からこうした言われ方をするようになりました。
中国には「剩男時代」という曲もあり、Spotifyで検索できます。曲の歌詞が面白く、「残された者は運命を受け入れるしかない」「絶えず後悔しながらため息をつく。これはどんな時代なのか?」といった部分などは印象的です。
中国には「余り男」に対して「余り女」という言い方もあります。中国語では「剩女」と書き、日本語的に言うならば「売れ残り」といった意味になります。もちろん、差別的な意味合いを含んだ言い方です。
中国では「売れ残り男」と「売れ残り女」の間には重要な違いがあります。「売れ残り男」の多くは自ら望んでそうなったのではなく、不本意に結婚から取り残された人たちです。これに対して「売れ残り女」は自ら独身を選んだ人たちを指します。
──結婚しないことを選択する女性が中国で増えているのですか?
ガオ:急増しています。ある意味では、結婚しないことを選択する女性の増加が、昨年の中国の結婚登録率が歴史的に低かったことの大きな理由の一つです。
中国の結婚率は急激に低下しています。2024年の全国の結婚登録数は610万件で、前年の770万件から大きく数を減らしました。これを受けて、中国の国家政治顧問が、法定結婚年齢を22歳から18歳に引き下げることを提案したほどです。
中国の女性たちが結婚しなくなってきた背景には、いくつもの要因がありますが、たとえば、女性の教育レベルの向上や、結婚や家族生活に対する考え方の変化があります。
経済的自立により、現代の中国人女性たちは結婚しないことを選択できるようになってきたのです。若い女性の間では、伝統的な家族の役割よりもキャリアやQOL(生活の質)の向上を優先する傾向が強まっています。
──結婚できない男性が増えているのはなぜですか?
ガオ:1980年代の一人っ子政策と、超音波技術を使った性別判断や中絶があります。
中国に限ったことではありませんが、子どもが生まれる時に、男児の方が女児よりも好まれる傾向があります。韓国にもかつてはそうした風土が強くありましたが、価値観をうまく転換して、そうした文化から脱却できました。
中国ではいまだに男児志向傾向が続いて、妊娠時に女の子だと分かると中絶するケースが見られます。そうしたことが長く続いた結果、男性が偏って多くなってしまった。どうしても男が余る人口構成なのです。
取り残される男性はどのような人たちかというと、一般的には地方出身で、収入や学歴が低い男性たちです。お金、教育、社会資本にあまり恵まれていない男性たちが、パートナーを見つけることに苦労しています。
──一部の中国人男性が海外から花嫁を買っているという報道もあります。
ガオ:中国では、比較的少ない女性をめぐって多くの男性たちが競争している状況で、結婚が圧縮状態にあると言われ、強みのない男性は競争から零れ落ちます。中国にいる私の友人たちにも、必死に妻を探しているけれど相手を見つけられない人が何人もいます。
このような売れ残った男性たちは誰と結婚したらいいのか。実はかなり多くの人たちが、外国人花嫁を「購入」 するのです。買婚です。この需要の高まりが、特に東南アジアの女性を中心とした、違法な結婚や人身売買につながっています。
──花嫁はどのような国から来るのですか?
ガオ:多くはベトナム、ミャンマー、ラオスなどの東南アジア諸国です。中国当局が取り締まりを強化していることもあり、ネットワークは他の国にも拡大しています。最近、注目された事件には、パキスタンやマダガスカル出身の女性などもいました。
引用元: ・中国で急増する「結婚できない男」、ベトナム、ミャンマー、ラオス、遠くはマダガスカルまで嫁探しの旅も苦戦中 [4/5] [昆虫図鑑★]





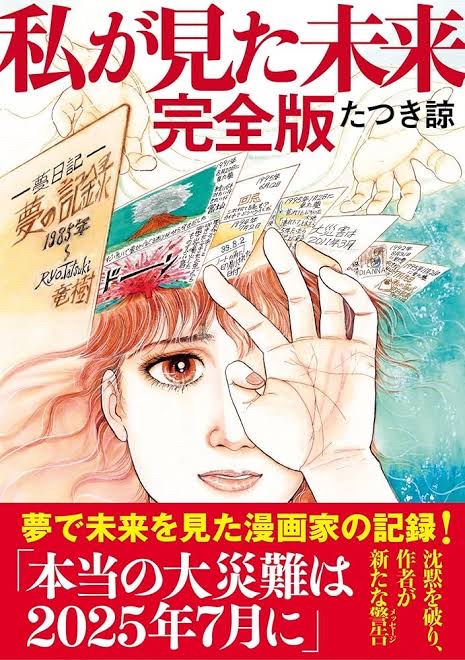
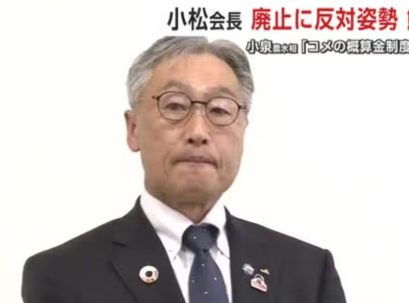







コメント