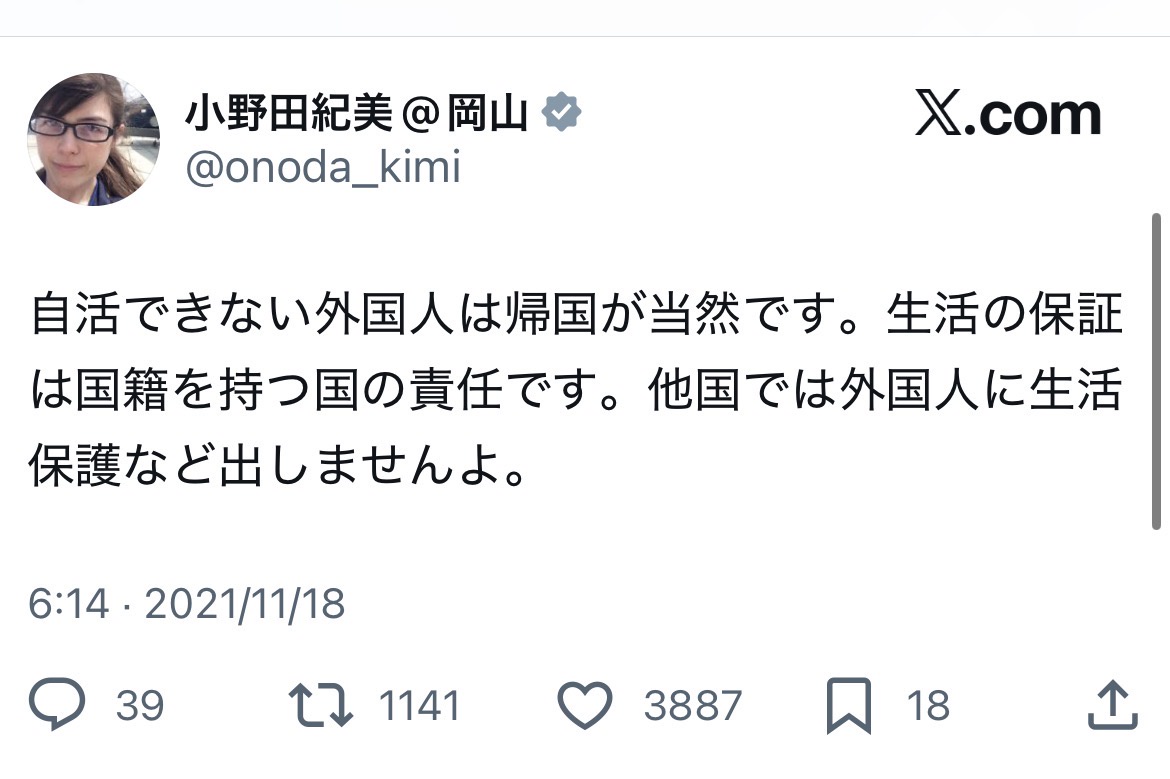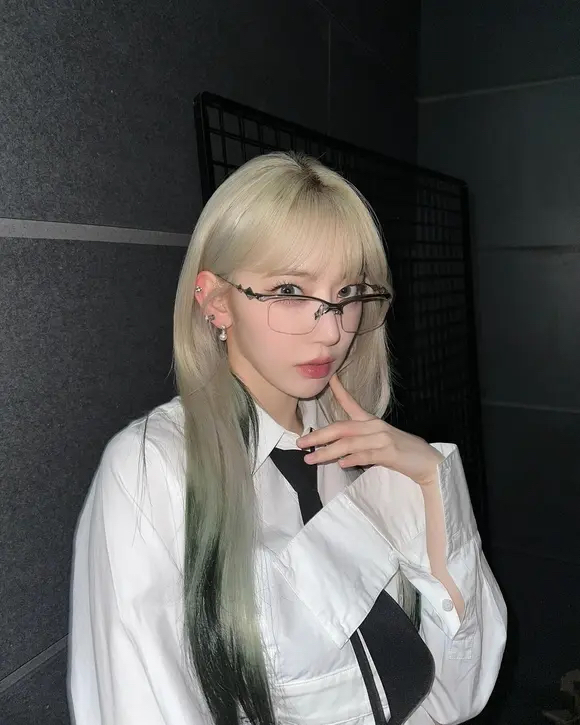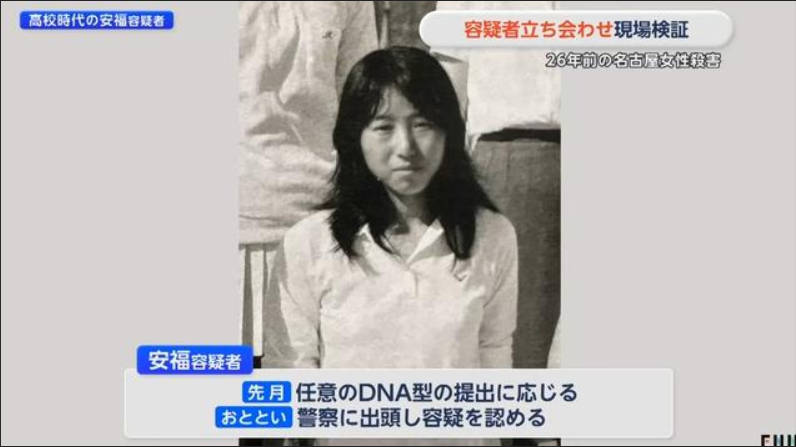西洋思想 日本語訳を採用
日本語が、中国へ流入し始めたのは1900年代初め頃だ。(略)
日本では明治期、西洋思想を翻訳する過程で「哲学」「人権」といった多くの和製漢語が生み出されていた。彼らがそうした言葉を自著を通して中国に広めたのが、日本語が伝わった初めての事例だ。
1920年に中国で出版されたカール・マルクスらの「共産党宣言」も、日本への留学経験を持つ上海・復旦大学の陳望道・元学長が幸徳秋水らの日本語版などを基に完成させた。(略)
72年の日中国交正常化や78年に始まる改革・開放政策を通して日中の経済、文化交流が活発になると、日本の映画やアニメが中国で放映され始め、「寿司」「人脈」といった中国語にはなかった言葉が浸透した。(略)
「萌え」「推し」も
「中国のことばの森の中で」(教養検定会議)の著者、国学院大学の河崎みゆき非常勤講師(日中対照言語学)は「『社畜』などの日本語が受容されるのは、経済発展を遂げた中国で日本と似た社会現象が起きているだけでなく、若者を中心に新しい概念や表現を受け入れる土壌があることを示している」と指摘する。(略)
単語に限らず、「~化」「~性」「~族」といった表現も定着していった。日本人の多くが使う「手帳」は、言葉とともに人々の生活習慣にも取り入れられ、日本同様、年末になると多種多様な手帳が店頭に並ぶ。
現在は、インターネットの普及や訪日中国人の増加に伴い、日本の流行が瞬時に伝わるようになった。若者が「萌(え)」や「推(し)」を使い、「卡拉OK(カラオケ)」のように日本語の音に似た漢字を当てる用法もみられるようになった。(略)
「弁当」「旗艦店」など95語 辞書に収録
(略)日中は、少子高齢化や男女平等の実現など共通する社会課題を抱える。中国の地方政府や医療の関係者は、日本の高齢者施設を視察し、新たな制度や概念を吸収している。北京の書店では、東京大学名誉教授の社会学者、上野千鶴子さんの著作が平積みになっている。日中の政治的対立にもかかわらず、中国語に取り入れられる日本語は今後も増え続けそうだ。(以下有料版で,残り:567文字)
読売新聞 2025/11/08 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/world/20251107-OYT1T50169/
引用元: ・「和製漢語」から「萌え」「推し」、「共産党」も…多くの日本語が中国に輸入 [蚤の市★]
どこの国の新聞の記事なの