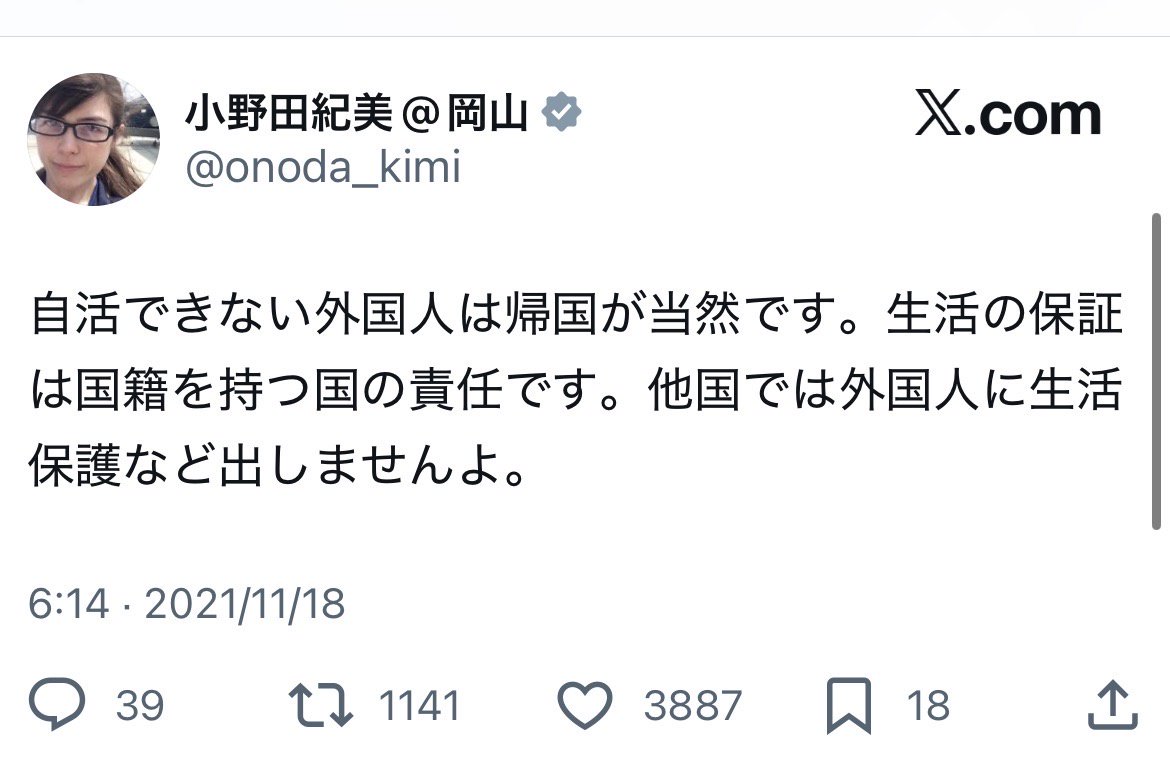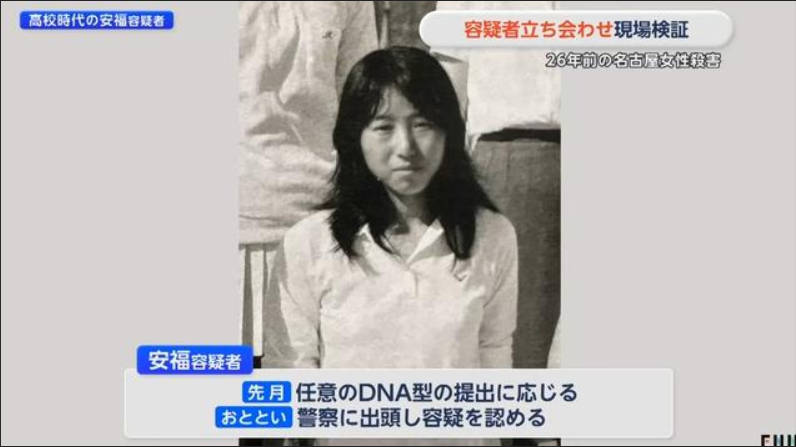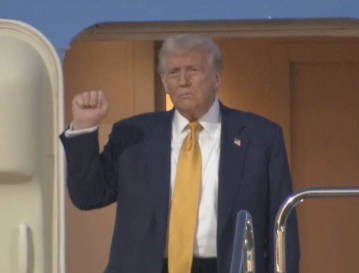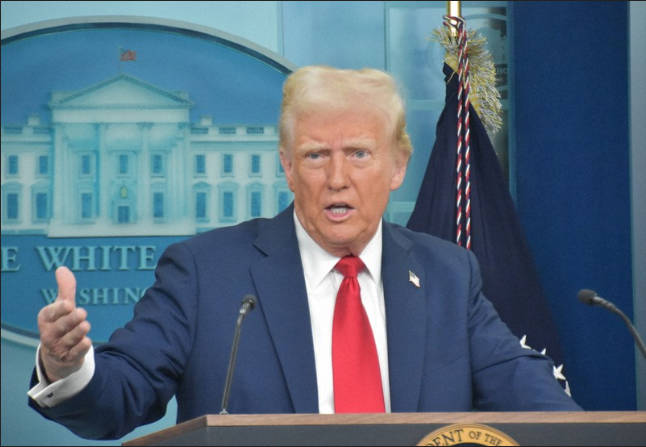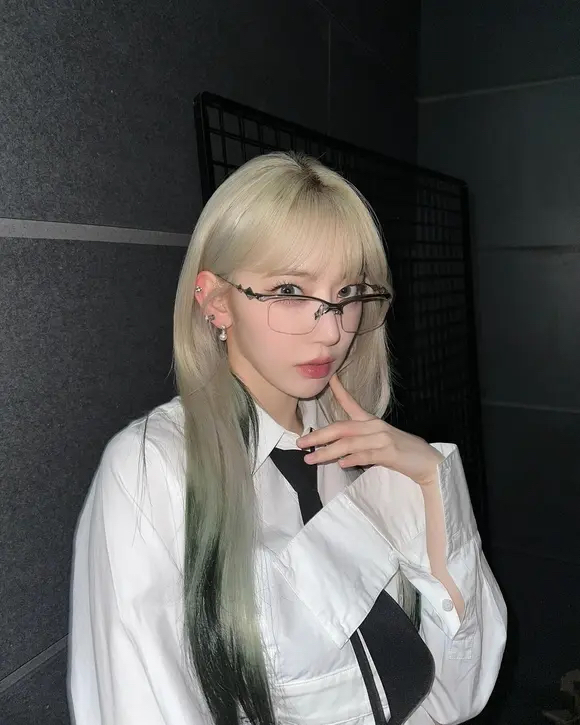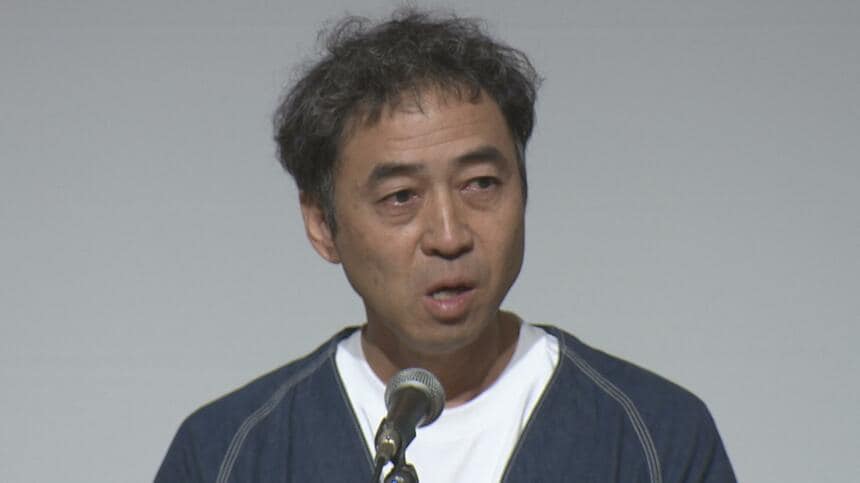https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/df0e6cb6ac94d2a84cabe423cdb5903f843f33f2
高市早苗政権が誕生した。一方でテレビのコメンテーターらかは「保守というより右翼」という批判や「死んでしまえばいい」などと度を越した発言が高市氏に投げかけられた。これは本当に「政治的公平」なのか。
■メディアを神格化する時代は終わった
日本の放送法は、制度上はこのイギリス型に近いが、運用の実態はアメリカ型に寄っている。政治家が放送内容に口を出せば「検閲だ」と批判され、放送局が自主的に判断すれば「偏向だ」と批判される。日本はイギリスとアメリカ、どちらの特徴も中途半端に取り入れた結果、誰も責任を取らない仕組みと化した。
政治的公平は、戦後の放送自由を守るための盾として生まれた。戦前の国家統制への反省から、放送法は「政治から独立し、公正であれ」と定めた。放送人は権力から距離をとり、国民に誠実な情報を届けることを使命とし、政治的公平は国民の信頼を得るための倫理だった。
しかし、放送はかつての公共性を失いつつある。権力と距離を取っていたはずのメディアに多くの利害が入り交じり、SNSの普及によってこうした構造が徐々に可視化され、放送はもはや“聖域”ではなくなった。無論、公共放送であるNHKも例外ではない。政治報道の扱いや受信料制度、番組内容をめぐって定期的に炎上し、スクランブル放送を求める国民は少なくない。
放送法に定められた政治的公平の理念そのものは正しい。しかし、実現困難な理念のもと、テレビのコメンテーターや報道局を一方的に叩き続けるだけでは何も変わらない。政治的公平を守ることが困難である現状を踏まえ、放送に係る制度を大幅に見直すべきではないか。放送がどう作られ、どんな利害が関わっているのか、徹底した情報公開等で、国民が判断できるようにすべきである。ただ上っ面だけの公平を守ろうとするよりも、誠実な説明と情報公開で国民との信頼を築くべきである。メディアを神格化する時代は終わった。国民が考え、選び、監視する社会が、次の公平をつくる。メディアを批判するだけでなく、自らの判断で真実を選び取る社会を築く努力を怠らないことが、私たち国民に課せられた使命である。
引用元: ・日本のテレビの末路…高市下げ発言を繰り返すコメンテーター…「いったい誰のための放送?」 [662593167]