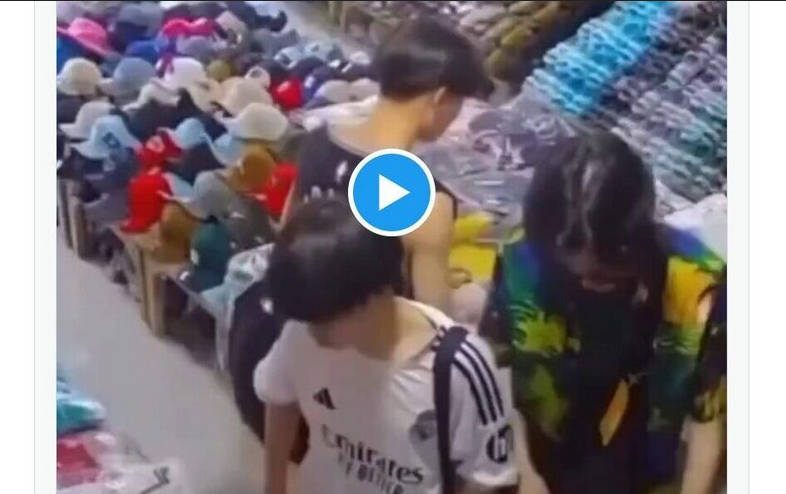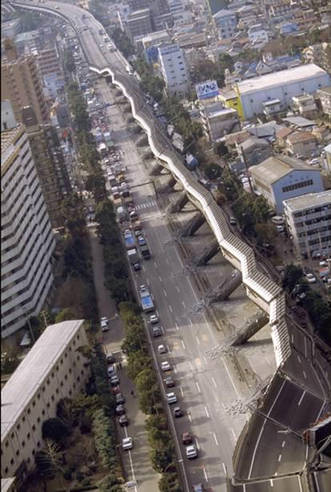日本と朝鮮の古代史に少しでも関心を持ったことがある人なら、「加耶」「任那」と併記された書名を見ただけで感じるものがあるのでは。いずれも3世紀から6世紀にかけて、朝鮮半島南部の洛東江流域に存在した十数カ国の小国群を示す名称。高校日本史の教科書を始め、近年では「加耶」と表記されることが一般的だが、『日本書紀』には「任那」とあるなど、重視する史料によって表記は揺れる。戦後は長らく「任那」が優勢だった。今でも世間的には「任那」の認知度が高いのではないか。
この時代、この地域をテーマとして扱う上で、呼称ひとつとっても論争が起こる。内実に踏み込めばなおのこと、歴史認識が問われる局面は多い。おまけに近年でも、朝鮮半島南部で前方後円墳の発見が相次ぐなど、研究の状況は更新され続けている。
そうした専門家でも手を付けるのが難しい題材に、2021年に同じレーベルから刊行した『藤原仲麻呂』も話題を集めた日本古代史の碩学が、実証主義に基づき挑んだのが本書だ。
歴史好きの読書人は多い。だからこそ生半(なまなか)な内容では響かない。本書はそのハードルを見事に超え、分厚い読者層から熱い支持を受け、着実に部数を伸ばした。
「日韓歴史共同研究がメディアで取り上げられるとき、大体は近現代史についてのやりとりが中心ですよね。でも実は、このテーマでも日韓の研究者は激しく議論を交わしています。歴史好きにとっては比較的メジャーなテーマですが、そうではない人には意外と知られていない。そのギャップを埋めるために、最新の研究成果を盛り込みつつ、入門書として読める本にすることを強く意識しました」(担当編集者の白戸直人さん)
序章に全体の約5分の1、50ページ弱を割いて、丁寧に「加耶/任那」のこれまでの研究史を紐解き、本全体の見通しを立てる。その後の章でも、本文の中でそれまでの内容を適宜まとめ、地名・国名を始めとして大量の固有名詞が飛び交う複雑な内容を追いかけやすく工夫している。
「現状、このテーマで気軽に手に取れる一般書はほぼありません。でも、一度見通しがつくと、日本史の中でもおもしろくて、話題を追いかけやすいテーマなんですよ」(白戸さん)
2024年10月発売。初版1万2000部。現在6刷4万4000部(電子含む)
前田 久/週刊文春 2025年10月30日・11月6日号
https://news.yahoo.co.jp/articles/2399fa6dee657687d31534e48e1aa12cdf08afef
引用元: ・「日韓の研究者は激しく議論を交わしている」近現代史だけじゃない…意外と知られていない“加耶/任那”論争とは [10/30] [昆虫図鑑★]
証拠の問題
韓国「韓国に対する愛情はないのかーっ!」
日本に「資料を見てくれ」
韓国「資料はそうだけれど」 「研究者としての良心はあるのかーっ!」