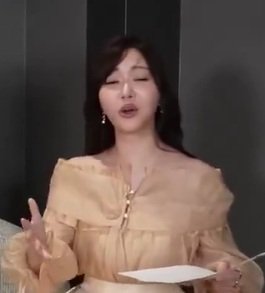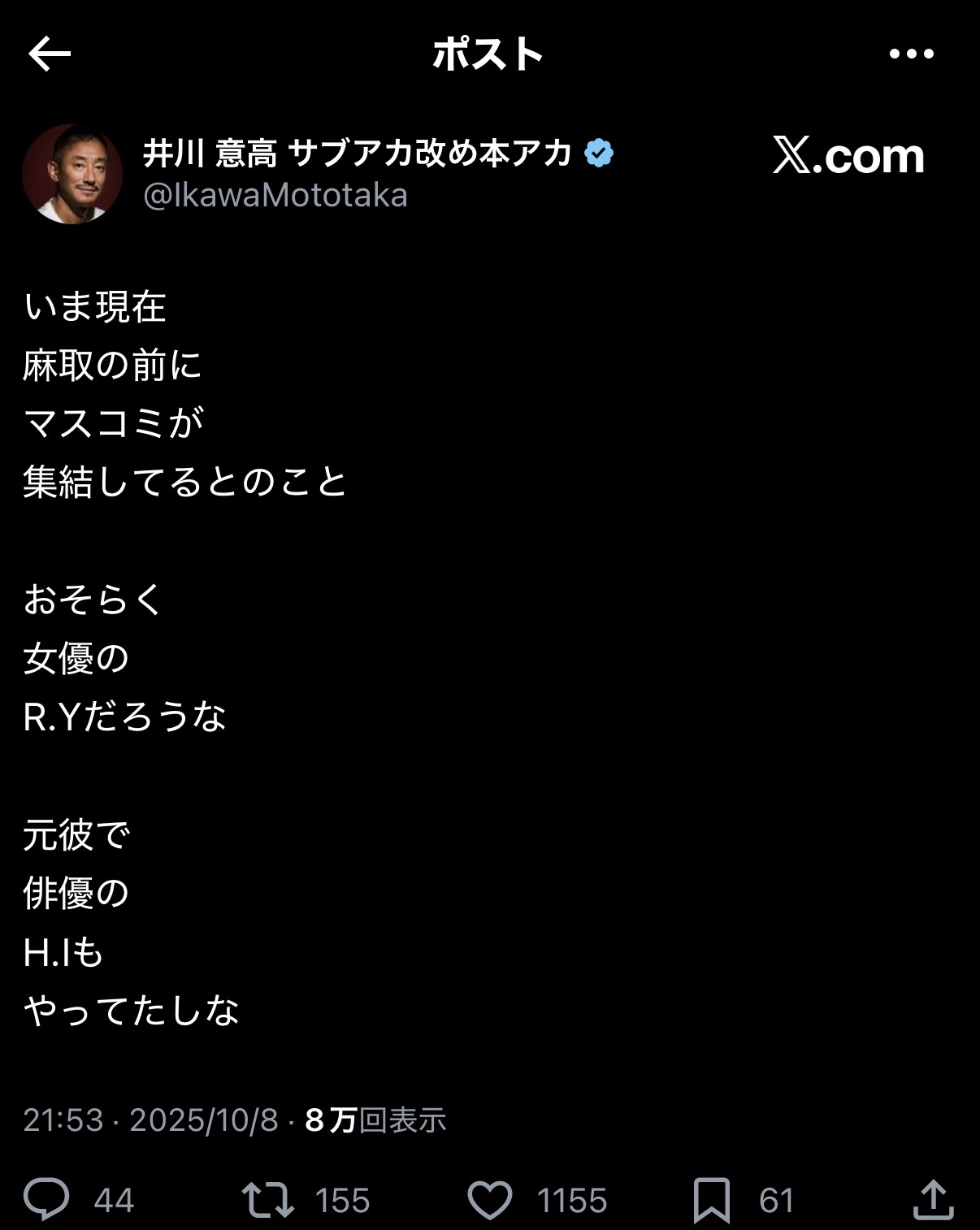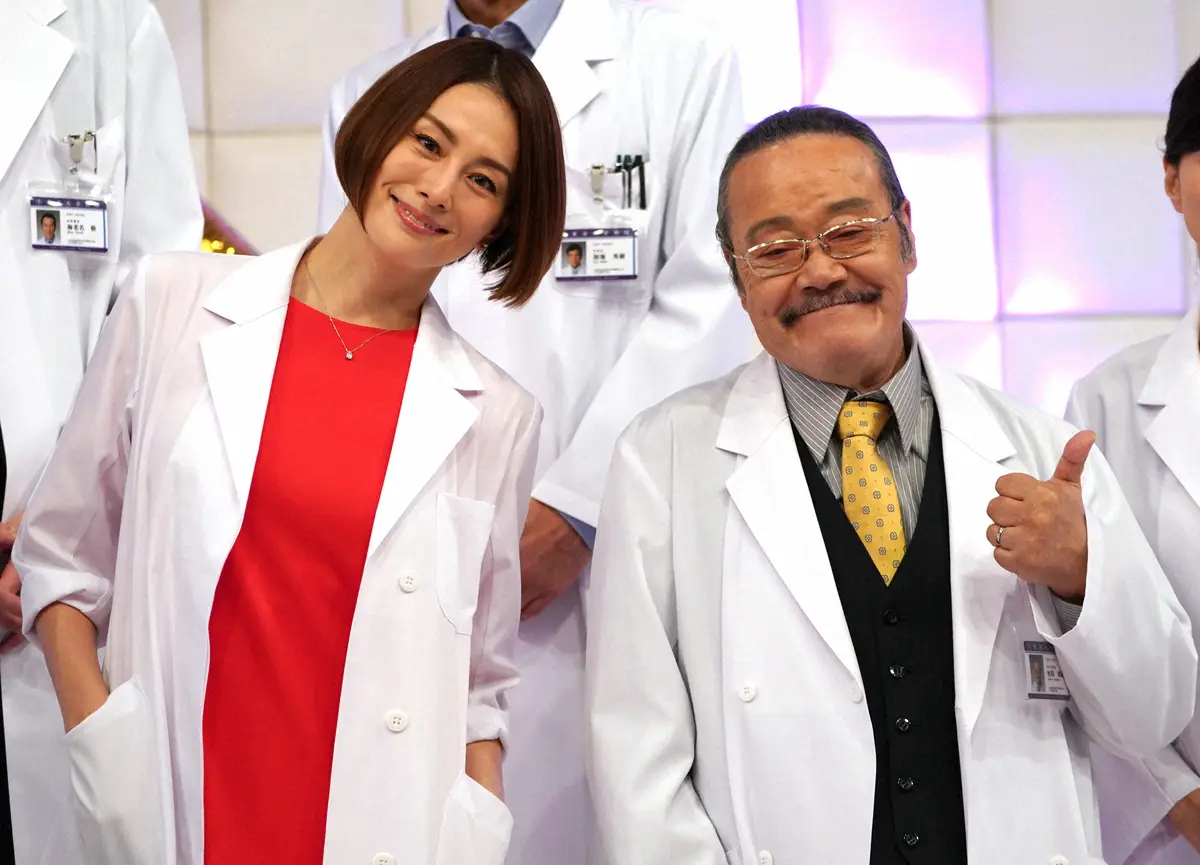マジョリティである日本人には、当事者として差別の問題を考える機会がほとんどなく、そのことが関心の薄さにつながっているのでしょう。でも、多くの弁護士がこの問題に取り組むべきだと思います」
人種差別に基づくヘイトスピーチ裁判を代理人として担当し、原告勝訴を勝ち取り、現在は弁護団の一員としてクルドヘイト訴訟に尽力している神原弁護士は、今、日本社会に広がる外国人差別をどう見ているのだろうか。(取材・文/塚田恭子)
学生時代に少年事件に取り組む弁護士の本を読んで、初めて真剣に考えた職業が弁護士だった。
そんな中、2013年、東京・新大久保でヘイトスピーチデモを目の当たりにした。
「聞くに堪えない言葉を叫ぶ人たちを目の前で見て、弁護士として取り組まなければと思いました」
これを契機に差別問題へ本腰を入れ始めるが、それは「めぐり合わせや流れによるところが大きかった」と振り返る。
「川崎でもヘイトデモが起きた際、2013年に熱心にやっていた弁護士がいたと、被害者側から声がかかって。当事者からの要請に応じる中で、海外の文献を読み込み、現場の課題を学んでいきました」
当時の法曹界は、今以上に「表現の自由はもっとも重要な権利」とする考えが主流だったそうで、ヘイトスピーチ規制を支持する弁護士は少なかったという。
「戦前の日本は治安維持法でおかしな方向に進み、戦争に突き進みました。その反省から、憲法学者の芦部信喜は『表現の自由はもっとも大事な権利』と説いたのです。
それは正しいことですが、憲法学には差別の問題が抜け落ちています。にもかかわらず『表現の自由』を金科玉条にする弁護士や学者が多かったと感じます。
討論すればいいと言いますが、民族名をあげて『殺せ、殺せ』と叫んでいる人たちと、どんな議論が成立するのでしょうか」
ヘイトスピーチの実態が知られることで、少しずつ変わってはきたものの「表現の自由があるのだから、互いによく話し合うべき」という法学者は少なくないという。

引用元: ・【表現の自由を金科玉条にする弁護士や学者が多い】クルドから在日コリアンまで、差別と闘う神原元弁護士の問い 「民族名をあげて『殺せ』と叫ぶ人と議論できますか?」
ああ、例えば「日本人は殺せ」とか言う人ね