【これまでに見えた矛盾】
地震想定を改めなかった理由を石川県の谷本正憲前知事に聞くと、「国の長期評価を待っていた」と国の責任を訴える。県も省庁も同じ「行政」だが、全体では住民の命を守る防災に向かっていない。縦割りのすき間に、責任の空白が生まれていた。(小沢慧一)
◇
◆3つの省庁の「縦割り」が背景に
前回紹介した日本海側の15道府県の調査からは、海底活断層の存在を把握した後も地震想定の見直しに動かなかった3県は、石川県と同様に長期評価が公表されるのを待つという選択を採っていたことがわかった。
選択の背景には、想定に関わる3つの省庁の「縦割り」がある。
まずは文科省について見ていく。国交省は海底の活断層の調査結果を2014年に公表したにも関わらず、文科省の地震本部は、その知見を10年も長期評価に反映させなかった。
なぜ、そんなに時間がかかったのか?
実は文科省は、国交省の調査に相乗りする形で、2013年から海域の活断層などを調査する「日本海地震・津波調査プロジェクト」を開始している。(略)
だが、文科省の地震本部はこの情報を公表することはなかった。長期評価が終わっていなかったからだ。
◆詳細すぎる評価や確率は、本当に防災に役立つのか?
長期評価に着手したのは2017年。南から順に評価し、1番最初に九州・中国地方の海域活断層の評価が公表されたのは2022年。能登半島沖が含まれる近畿・北陸地方の評価は震災後の25年6月となった。北陸以北の評価はさらにこれからだ。(略)
プロジェクトの委託を受け、調査に携わった佐藤比呂志・東大名誉教授は長期評価の議論について「防災に必要な断層の情報を公表する方が先決だ。不要とは言わないが、断層の詳細すぎる評価や確率を出すことに凝り固まり、時間を費やしすぎている」と批判する。
「長期評価に使っている活断層の情報は、日本海地震・津波調査プロジェクトの際にまとめたものとそう変わらない。 石川県が想定を見直すのに必要な断層の位置や形状などの情報は2015年時点で明確になっている」
◆現場が断言「確率は防災に不要」…何のための10年だったのか
(略)地震本部は今回F43断層を未公表にしていたことを受け、検討が終わっていなかった確率は据え置き、前倒しで断層の位置や形状の情報を2024年8月に発表。石川県はそれを基に2025年5月、地震想定を見直した。地震本部は翌月の2025年6月に確率を発表した。石川県は確率の公表までは待たなかった格好だ。
長期評価にこだわった石川県だが、皮肉なことに求めていたものは長期評価のシンボルである確率ではなく、断層情報だった。
なぜ確率を待たなかったのか。その問いに担当課長はこう言い切った。
「確率は想定に不要。その他の防災の施策にも特段使っていない」
◆地震と津波を分けるのはナンセンス 国交省が見落とした地震の危険(略)
(以下ソース及び有料版で)
東京新聞 2025年9月1日 12時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/431109
引用元: ・専門家の議論は「凝り固まり、時間を費やしすぎ」 国も地方も、住民の命を守る「防災」を見ていなかった [蚤の市★]
能登の住民も復興のためにはまず祭りだとか言ってたしずっと祭りだけやってろよ。
脳死してんのかな
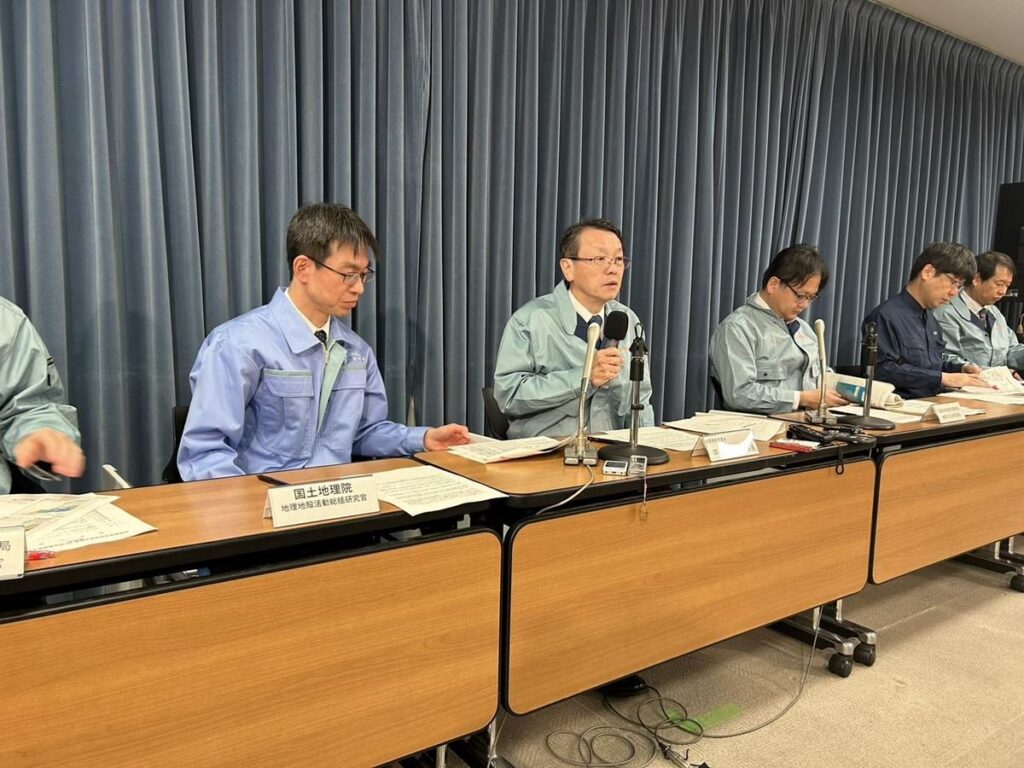











コメント