日本人の銘柄米選好を前提とする限り、コメ問題は、備蓄米の活用では解決できない。生産調整方式の基本を見直さないかぎり、コメ価格の高騰が今後も続くおそれがある。
早場米の販売が始まった。ところが、主な産地のJA(農協)が農家に支払う前払い金(概算金)は、前年よりも5~8割高いと報道されている。
概算金の上昇は、コメの小売価格に直結する。したがって、今後、米の小売価格が上昇する可能性が高い。5キロ5000円で販売する店舗もあるという。
そうなれば、この1年間に起こったことの繰り返しだ。
米価の異常な上昇は、日本のすべての家計にとって無視することができない深刻な問題だ。それにもかかわらず、なぜ2年続いて同じ問題が生じてしまうのか?
政府は、2024年産米の高騰の原因として、外国人旅行客による需要の増加や、日本人の米に対する嗜好の回復などの需要増大要因の過少評価があったことを認めた。
需要の過少見積もりが、生産計画を過少なものとし、その結果として米価が上がったことを認めたわけだ。
そうであれば、今年は、過少な需要見積りは是正され、実情にあった適切な見通しに拡大されたはずだ。その結果として、2025年米の計画生産量も、2024年米に比べて拡大されたはずだ。そして、その結果として米の価格は値下がりし、適正な水準になって然るべきだ。
それにもかかわらず、価格が昨年より8割も高くなってしまうのはなぜだろうか?
新聞報道によれば、それは、酷暑や少雨の影響だと言う。しかし、これは、予想された事態のはずだ。とくに、酷暑は、地球温暖化の結果として不可避の現象なのだから、見通しには当然織り込まれていたはずだ。だから、「異常気候によって生産量が見込みより過少になったから、米価が高騰する」という説明は納得できない。
問題の根幹は、2025年米についても、コメ価格維持のために、生産量を需要に比べて意図的に低く設定していることなのではないか?
つまり、米政策の基本が去年から何も変わっていないために、2024年米について生じた事態とほとんど同じことが、2025年米についても繰り返されようとしているのではないだろうか?
そうだとすれば、24年、25年だけでなく、今後もずっと同じ状況が繰り返されることになる。これは、由々しきことだ。
昨年夏からの米騒動の状況を振り返ってみると、次の通りだ。米が不足し、価格が暴騰した。当初、政府は備蓄米を放出しなかったが、世論に押されて放出に踏み切った。しかし米価格に影響はなかった。
流通の途中で目づまりが生じているためだと説明されたが、そうした事実はなかったと、後で説明が修正された。そして、備蓄米の放出価格の決定方式に問題があるということになり、農林水産相に就任した小泉進次郎氏は、従来の競争入札から随時契約への変更を行った。その結果、備蓄米の放出価格は下がった。
しかし、下がったのは備蓄米の価格であり、銘柄米には影響はほとんど及ばなかった。したがって米の価格が全体として下がることにはならなかった。
この経験で分かったのは、備蓄米の放出を行ない、価格決定方式を変えても、その影響は備蓄米の範囲にとどまり。銘柄米には影響が及ばないということだ。
これは、重要なことである。銘柄米の価格が上がれば、それより多少品質は落ちるといっても、銘柄米の需要の一部が備蓄米に移ってもよいはずなのだが、そのような動きは、ごく限定的にしか起きなかったのである。これは、日本人の銘柄米に対するこだわりが強いためだ。
日本人の銘柄米に対するこだわりの強さは、外国産米との関係においても言える。
カリフォルニア米は、日本の高級銘柄米よりも価格が安定して安価なことが多いため、業務用や加工用(弁当、総菜、外食チェーンなど)では広く使われている。さらに、学校給食などでの使用拡大も考えられる。
しかし、多くの日本人は味に対するこだわりが強く、「主食としての米」に求める要件は非常に高い。とくに家庭用では、国産志向が強固であり、外国産米のシェアは極めて低い。消費者が品質や産地に対して高いブランド選好性を持つ限り、価格差による代替行動は限定的とならざるをえない。
https://gendai.media/articles/-/156616
引用元: ・【一橋大学名誉教授・野口悠紀雄】コメの異常な高騰は今年も止まらない、、その理由を説明しよう
まず石破とか進次郎とか政府が理由を説明するのが筋だろw
銘柄米が少ないから高値って事でしょ
韓国や台湾、スペインより貧しい大多数の下級国民のために関税撤廃して
売れ残りの古古米でもいいから5キロ1500円以下で供給しなければならない




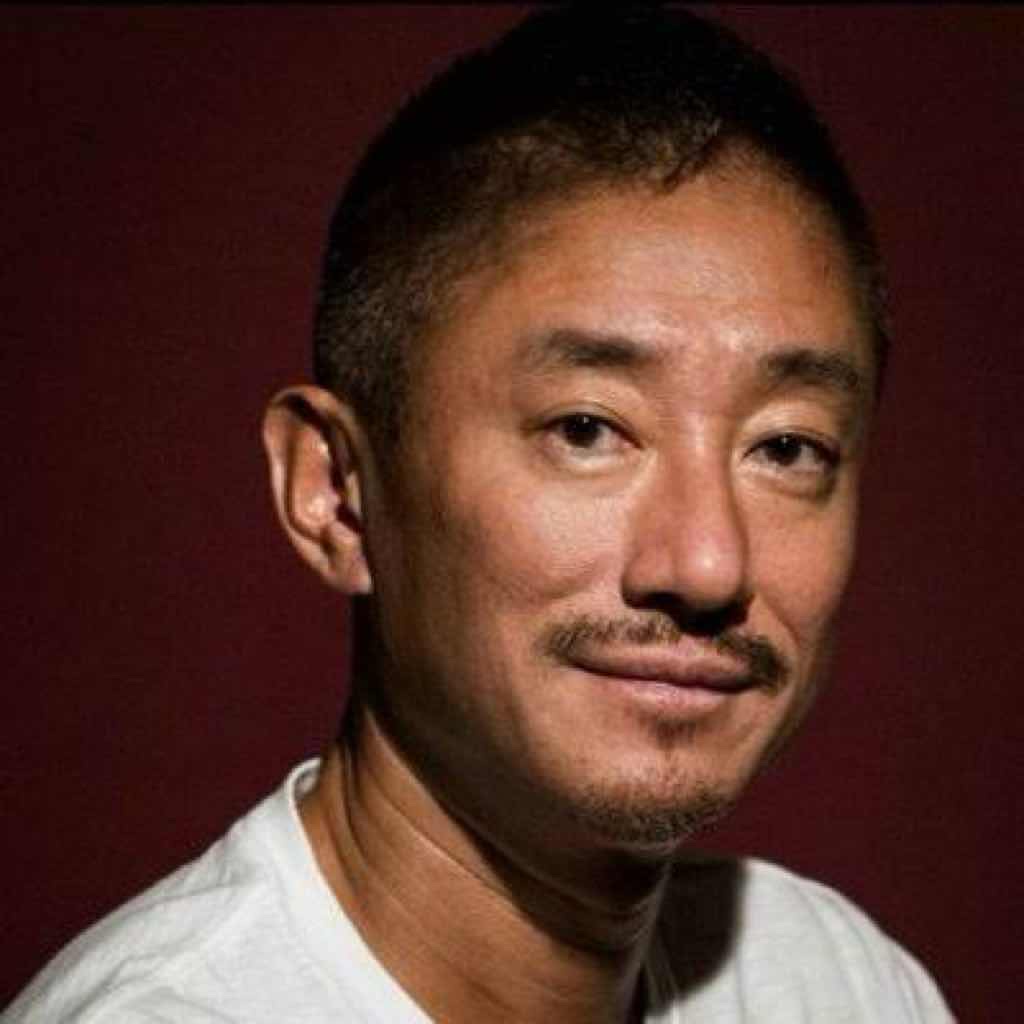





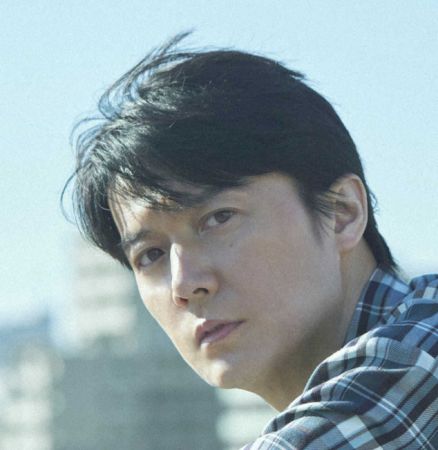

コメント