不動産クラファンとは、運営会社がインターネットを通じて不特定多数の投資家から資金を集めて不動産を購入し、その運用益の一部を投資家に分配。運用期間が終了すると元本を返還する仕組みだが、運用成績によっては元本は保証されない。
運用益を分配する頻度は四半期や半期ごと、運用期間は1年から5年とプロジェクトによって異なる。
国土交通省が発行している「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」によると、不動産クラファンへの新規出資額は2019年度の34億2000万円から、24年度には1763億4000万円に急拡大した。
背景にあるのは、17年に不動産特定共同事業法が改正され、インターネット上での投資勧誘や契約締結行為が認められるようになったことだ。この規制緩和により、不動産クラファンに参入する事業者が相次ぎ、幅広いサービスが提供されるようになった。
不動産クラウドファンディング協会によると、運営会社は24年10月時点で81社に上り、過去5年で5倍に増加した。
不動産は、インフレに強い資産とされ注目が集まる一方、オフィス賃料やマンション価格は上昇しているため、市況の過熱感が懸念されている。
それでも日本の不動産は海外に比べて割安とされており、個人投資家が新たなプレーヤーとして参加すれば、不動産取引がより活発化する可能性がある。
不動産クラファンの需要は世界的に高まっており、調査会社ビジネス・リサーチ・カンパニーによると、世界の市場規模は、持ち分所有への関心の高まりやミレニアル世代の投資熱を背景に、今年約291億6000万ドル(約4兆3000億円)と、前年比で約44%増加すると予想されている。
株式中心の投資戦略を取っていた東京都の会社役員、依田泰典さん(48)は17年ごろから、リスク分散を意識して不動産クラファンへの投資を始めた。1回当たりの投資額は50万-200万円で、累計投資額は数千万円を超えた。
依田さんは「個人投資家が出合うことのない不動産に投資できる。不動産クラファンは、私にとって画期的だった」と振り返る。オフィスビルや商業施設を中心に、これまで投資したプロジェクトの利回りは5%前後で、堅実なリターンを得てきた。償還されなかったプロジェクトはないという。
日本初の不動産クラファン事業が始まったのは14年で、不動産会社ロードスターキャピタルが手がける「オーナーズブック」だ。
金融商品取引法に基づき、不動産を担保にした融資に対して投資家が貸し付ける投資商品が主力で、1口1万円から投資できる気軽さが人気を呼んでいる。
同社の岩野達志社長によると、投資家数は17年から急増して現在は2万8000人を超えた。投資済み案件は8月8日時点で378件、累計投資額は650億円超に上り、主な投資家は、保有金融資産1000万円から2000万円の30代から50代だ。
岩野社長は「機関投資家のみが投資している不動産領域に個人投資家が加わることで、不動産市場の安定化にも貢献する」と意義を強調する。
不動産クラウドファンディング協会の横田大造代表理事は「オンライン取引が株式投資で普及したように、ネット取引を通じた不動産投資も拡大が期待できるため、不動産クラファンには大きな伸びしろがある」と期待を寄せる。
三井住友トラスト基礎研究所私募投資顧問部の米倉勝弘上席主任研究員は、「不動産クラファンによって、不動産投資の裾野が個人投資家まで広がることはウエルカム」と指摘。
市場規模が約40兆円の私募ファンドに比べて、不動産クラファンが不動産市況に与えるインパクトは小さいものの、「不動産の流動性が高まることは歓迎すべきだ」として、小規模物件などの売買活発化に期待を示した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-21/T0GKDKGPFHTT00
誰だこんなアホな法律作った奴
リートも包摂してそうな感じ。
端株みたいなの大量に作ってどうすんねん…






_618650.jpg)

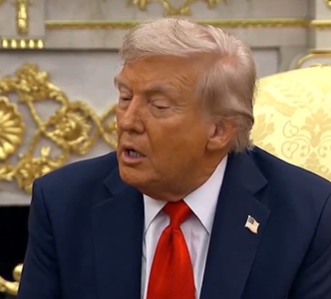

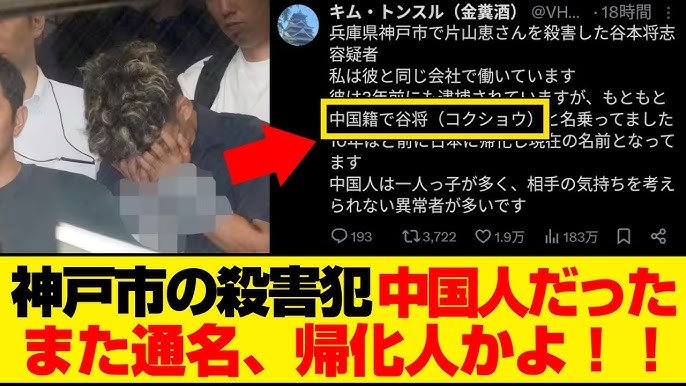
コメント