多くの日本人投資家が米国株式に強い関心を寄せているのは理解できる。2010年から2023年の約13年間、S&P500は年平均約12.8%という驚異的なリターンを記録した。
一方、日経平均株価の同期間の年平均リターンは約8.5%、MSCIエマージング市場指数は約3.5%だった。Appleの株価は同期間で約1800%上昇し、Amazonは約1000%、マイクロソフト社は約900%と目を見張る成長を遂げた。
このような数字を目の当たりにすれば、「米国株だけでいい」と考えたくなる気持ちも自然だ。
しかし、投資においては過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではない。株式市場がプラスの期待リターンを生み出すしくみは米国だけでなく、世界中の資本主義経済で働いている。
ここで考えるべき重要な問いは次のとおりだ。「将来にわたって最も良いリターンを生み出す市場は、必ずしも現在最も強い市場とは限らないのではないか?」
歴史を振り返ると、経済覇権国は常に移り変わってきた。
17世紀にはオランダが世界経済の中心だった。オランダ東インド会社は当時、世界初の株式会社として時価総額が現在の約7.9兆ドル(約1200兆円)相当とも言われ、現代の巨大企業を遥かに上回る規模だった。
18世紀から19世紀にかけてはイギリスが産業革命を牽引し、1900年ごろのロンドン株式市場は世界の時価総額の約25%を占めていた。そして20世紀以降、アメリカが世界経済の主導権を握り、現在に至る。
もし1700年代にオランダの投資家が「オランダ株だけに投資すれば良い」と考えていたら、イギリスの産業革命による成長機会を逃していただろう。同様に、1900年ごろのイギリスの投資家が「イギリス株だけが最良」と信じていたら、20世紀のアメリカの驚異的な成長に乗り遅れていたかもしれない。
この歴史に目を向けると、長期的な投資戦略として、単一国に集中するリスクが見えてくる。
実際、1989年に日本の株式市場は世界の株式時価総額の約45%を占め、「日本株こそ最強」という見方もあった。しかし、その後の30年間で日本の世界シェアは約7%程度に低下した。
米国の地位が近い将来に急激に低下するとは限らないが、世界経済のバランスは徐々に変化している。中国の経済規模はGDPベースで米国の約70%に達し、インドは世界第5位の経済大国へと成長した。
過去10年間でベトナムのGDPは約2.5倍に拡大し、インドネシアも約1.8倍になるなど、アジア諸国の経済成長は目覚ましい。
実際のデータを見ると、全世界株式に分散投資することで、リスク(ボラティリティ)が顕著に低減することがわかった。
過去20年間(2003~2023年)のデータでは、米国株(S&P500)の年間標準偏差は約15.7%だったが、全世界株式(MSCIワールド)では約14.2%だった。これは約10%のリスク低減効果を意味する。
具体的な例として、2008年の金融危機時には、S&P500が約37%下落したのに対し、MSCIワールドは約34%の下落にとどまった。
また、2022年の世界的な株安局面では、米国のテクノロジー株主導のNASDAQが約33%下落した一方、全世界株式は約18%の下落で済んだ。これらの数字は、異なる国や地域の市場間の不完全な相関性がリスク軽減に寄与していることを示している。
米国株1本でいくということは、リスク資産のすべてを米ドルで保有することと同義だ。「え? 円で保有しているのでは?」という反応をされることが時々ある。
たとえ、証券口座の保有資産の金額や損益が円ベースで表示されていたとしても、裏では米国株を保有している金額と全く同じドルを保有しているのだ。当然、米ドルの為替リスクを100%取っていることにもなる。
逆に、全世界株1本でいくということは、リスク資産のすべてを米ドル、ユーロ、円、元、ルピーなどの全世界の通貨に分散して保有しているのと同義だ。為替リスクも複数の通貨に分散されていることになる。
為替レートは2国間の通貨の交換レートに過ぎず、片方が上がればもう片方は下がる。膨大な組み合わせがあり、為替の予測は株価の予測よりも困難と言われている。
リターンの多寡のみで投資対象を選び、投資先の通貨の分散を考えないのはバランスを欠いていると言えよう。
https://president.jp/articles/-/99509
引用元: ・【投資ブロガー・水瀬ケンイチ】「S&P500」より 「オルカン」がおすすめなのは明らか、歴史とデータが指し示す「もっとも賢い投資術」・・・アメリカの名著も「国際分散投資は必須」と推奨している
靴磨きがウンタラカンタラ
大半はアメリカ株式だしな





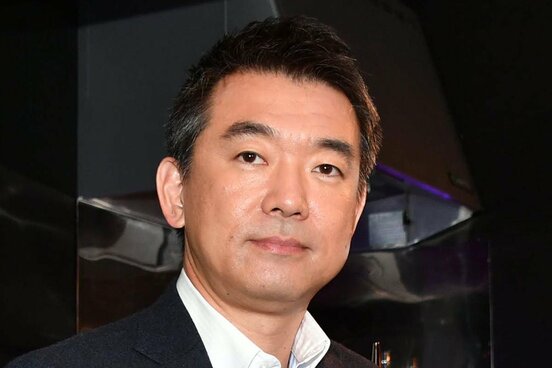










コメント