7/20(日) 11:58 クーリエ・ジャポン
https://news.yahoo.co.jp/articles/e019870ed3e36cda752c52e3139f7e8e2637a04b
Photo: Instagram of Velvet Sundown
https://courrier.jp/media/2025/07/16111933/Screen-Shot-2025-07-15-at-1.03.05-PM-e1752600032501.png.webp
AIが音楽業界に新たな震撼をもたらした。
わずか数週間のうちにSpotifyで100万回以上再生された人気バンドが、実は「完全なAI生成」だったという事実が明らかになり、音楽の創作と消費のありかたに波紋が広がっている。
そのバンドは英国発の「Velvet Sundown(ヴェルヴェット・サンダウン)」という名で、公開されていたプロモーション写真によれば男性4人組だった。
当初は「人間のクリエイティブ・ディレクションによって導かれた合成音楽プロジェクト」と表現されており、AIによる創作であることは否定していた。
6月にカントリーフォーク調のアルバム『Floating On Echoes』と『Dust And Silence』をリリースし、音楽ファンの間で瞬く間に話題となった。
だが、自称「準メンバー」を名乗る人物が、このバンドは楽曲制作に生成AIプラットフォーム「Suno」を使用し、そのプロジェクトは「芸術的な悪戯(art hoax)」だったと米誌「ローリング・ストーン」に語り、物議を醸した。
一方、同バンドはその記事が公開されるやいなや、公式のソーシャルメディアアカウントで「誰かが私たちのアイデンティティを乗っ取ろうとしている」との声明を発表し、ローリング・ストーンが公開した証言を否定。つまり、一度はAI説を否定した。
ところが、最終的には「(私たちは)完全な人間でも、完全な機械でもない」「その中間のどこか」に存在するという声明を出し、楽曲もイメージも、そしてバンドの結成ストーリーも、AIによるものであることを認めた。
この一件を受け、音楽業界からはAI生成音楽に対するラベル表示義務の法整備を求める声が高まっている。
■AI作品には「明確なラベル表示を!」
英作曲家団体「Ivors Academy」のロベルト・ネリCEOは、「人間の創作者を介さずに大規模な聴衆を獲得しているAIバンドは、著作権や透明性、同意の観点で深刻な懸念がある」と、英紙「ガーディアン」に述べている。
BPI(英国レコード産業協会)のソフィー・ジョーンズCSOも、「AIは人間の創造性を補完するものであるべきで、代替してはならないと考えている」と強調し、AI生成音楽には明確なラベル表示の義務や著作権保護を英国政府に求めている。
これまでにも、AIによって生成された音楽は著作権問題を引き起こしてきた。
2023年には、ザ・ウィークエンドやドレイクの声を模したAI音源が、TikTokやSpotifyにアップされ、ユニバーサル・ミュージックが著作権侵害として削除を要請した事例も記憶に新しい。
今回の騒動も、どのアーティストの楽曲を学習素材として用いたのかが不明であり、独立系ミュージシャンへの補償がなされていない可能性が指摘されている。
同紙によれば、ストリーミング大手であるSpotifyは現在、AI生成音楽にラベルを付けておらず、「すべての楽曲はライセンスを持つ第三者によって作成、所有、アップロードされている」と説明するのみだ。
AIによる音楽創作は、新たな芸術の地平を切り拓く可能性を秘めている一方で、既存のアーティストの権利や収益構造といった音楽のエコシステムを根底から揺るがす存在でもある。
前述のネリは同紙にこう述べている。
「AI活用が倫理的におこなわれるためには、創作者への同意と公正な報酬を保証し、聴取者にはその楽曲の出所を明確に伝える仕組みが不可欠だ」
(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)
●The Velvet Sundown – Dust on the Wind (Lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=BzX1YFZW0jc
●Floating on Echoes
https://www.youtube.com/watch?v=WwXI8bXVm9M
引用元: ・【音楽】100万回以上も再生された注目の新星バンド 楽曲もビジュアルも「AIだった」 音楽の未来はどうなる [湛然★]
AIが作ろうと現代人が作ろうと過去の音楽家の作品だろうとどーでもいい。
問題は楽曲のクオリティのみ
でこの2作品はてんで駄作じゃん
凡庸で退屈すぎる
【音楽】「ヒット曲」の概念は時代遅れ? 音楽消費の断片化が影響 [湛然★]






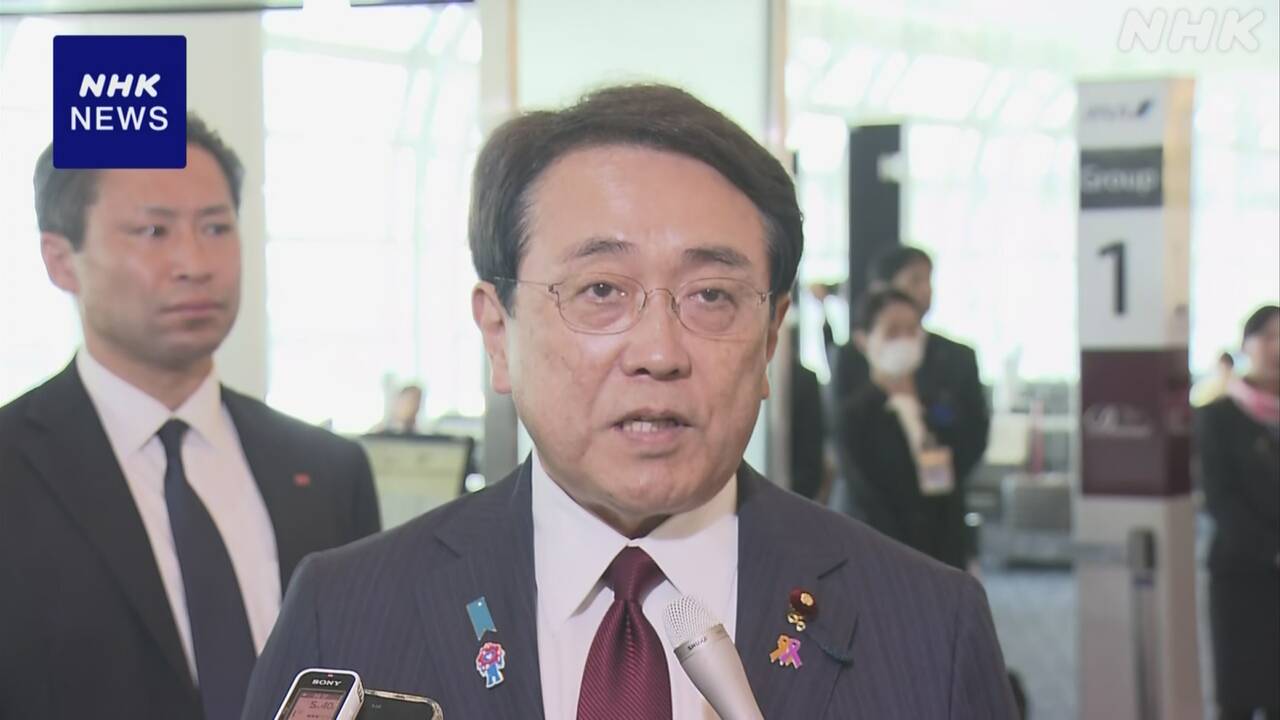



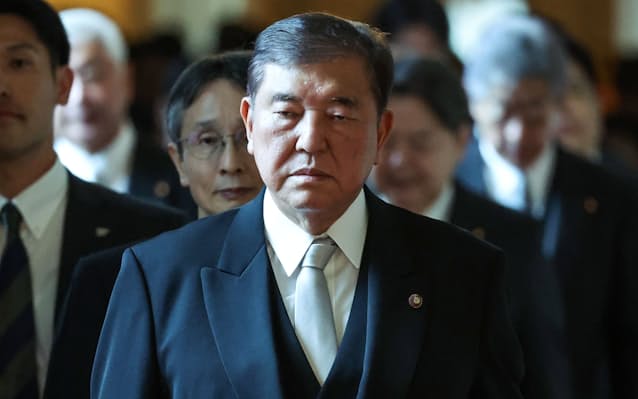
コメント