プレジデントオンライン■いつからおかしな教師が増えたのか
はるか昔、教師は「聖職者」か「労働者」かという熱い論争があった。今なら教師は「性職者」か「労働者」かということになるのかもしれない。
1958年当時、「勤評」という教員の勤務評定、指導力や勤務態度、適性などで先生をランク付けしようという教育行政に反対し、「勤評闘争」という動きが全国へと広がっていった。
だが、世間の目は、「先生は聖職者なのに闘争するなんておかしい」と冷ややかだった。
その当時は「一般の職業と先生は違う大切な仕事だ」という考え方が根底にあったからだろう。
「聖職か労働かの二元論はその後、給特法(71年制定)により、時間外勤務手当の代わりに月給の四%の教職調整額を支給する仕組みを生み出した(今回の法改正で調整額は段階的に10%へ引き上げ)。教師という仕事の『特殊性』を理由にした残業代不支給と裏腹の関係にあるのが、今も昔も変わらない長時間労働だ」(サンデー毎日7月20日号「『サンデー毎日』が見た昭和100年」より)
私が子どもの頃のことだったが、先生たちが赤い鉢巻をして腕を組み、校庭をデモっていた姿は記憶にある。
■わいせつ教師が話題になり始めた時期
私が小学生の頃は、東京の中野でも、まだ戦後の焼け跡があちこちに残り、バラックが立ち並んでいた。
先生たち、中でも女先生は元気で溌溂としていた。男先生は軍隊帰りも多く、肺病を病んで片肺がない先生もいた。
G先生という年輩の先生は、授業の中でよく戦争の悲惨さを語って聞かせてくれた。時には涙ぐみながら……。まだ戦前の名残がそこここにあった時代だった。
続きは↓
教師は「聖職者」から「性職者」になった…名古屋の「わいせつ教員」が給食のスープにしたあまりに卑猥な行為(プレジデントオンライン) – Yahoo!ニュース https://share.google/1Wqm31fpzhsVViu9V
引用元: ・教師は「聖職者」から「性職者」になった…名古屋の「わいせつ教員」が給食のスープにしたあまりに卑猥な行為 [ぐれ★]
お昼時!!

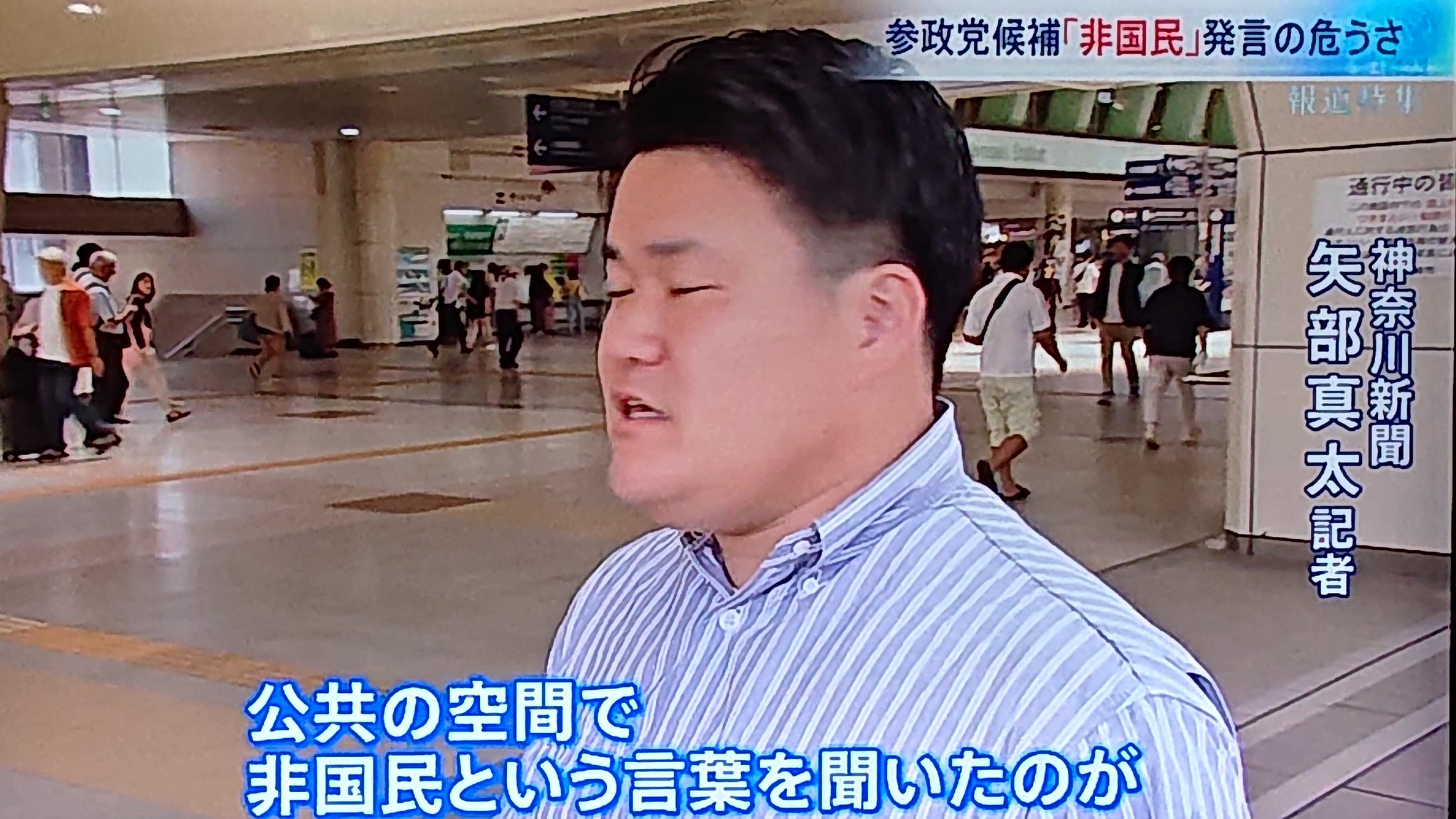














コメント