戦後生まれた中学野球
練習風景
戦前の高等小学校では、軟式球を使った野球大会が新聞社などの主催で行われ、全国大会も行われていた。
それを引き継ぐ形で、新制の中学校では、各学校に軟式野球部ができて、各市町村などの単位で大会も開催された。
高校野球の場合、学校単位の野球部は日本高等学校野球連盟(日本高野連)が統括する各都道府県高校野球連盟に所属している。野球以外の高校の主要競技は全国高等学校体育連盟(高体連)に所属しているが、野球だけは別の組織となっている。野球以外の主要高校スポーツの全国大会は「インターハイ」だが、野球だけは春夏の「甲子園大会」だ。
これに対し中学校の場合、各学校の軟式野球部は、他の競技と同様、日本中学校体育連盟(中体連)に所属している。同時に全日本軟式野球連盟(全軟連)にも所属している。
〜中略〜
選手数が激減する中学軟式野球
従来、最も大きなグループだった中学軟式野球は近年、選手数が激減している。
中体連資料によるここ15年の加盟校数、男子選手数の推移を5年刻みで見ていこう。()は全競技の加盟校、加盟選手に占める比率
2009年 8976校(82.6%)、307,063人(16.7%)
1校平均 34.3人
2014年 8784校(82.8%)、221,150人(12.3%)
1校平均 25.2人
2019年 8318校(80.2%)、164,173人(9.9%)
1校平均 19.7人
2024年 7706校(75.7%)、129,805人(8.0%)
1校平均 16.8人
2009年の調査までは、中学軟式野球部の部員数は増加していたが、2014年には部員数が激減する。3学年合計での選手数は34.3人から25.2人と減少。さらに5年後の2019年には選手数は20人を割り込み、昨年には16.8人まで減っている。
多くの学校では部員が集まらず、野球部そのものが休部、閉鎖に追い込まれている。
24年の学校数は2004年の85.8%、選手数は42.3%にまで減っている。
減少の背景にあるもの
中学軟式野球をめぐる環境は厳しい
確かに少子化は進行しているが、中学野球部の選手数の減少のペースはこれをはるかに上回っている。
選手数減少の原因は多岐にわたっている。
一つは、スポーツの選択肢が増えたこと。従来、野球は一番人気のあるスポーツだったが、Jリーグが創設され、すそ野拡大のために普及活動を全国的に展開したこともあり、サッカー人気が高まった。また水泳や卓球などの人気も高まった。
その一方で、この時期から「野球を知らない子供が増えた」。21世紀に入って巨人戦のナイター中継の視聴率が低迷し、地上波テレビが野球中継から撤退した。これにより地上波の野球放送がほぼ絶滅した。これまでの子供は、帰宅すると父親とともにナイターを見ながら食卓を囲むのが常で、野球のルールは自然に覚えたが、ナイターの視聴習慣がなくなるとともに、野球を知る機会がない子供が増えた。
また、この時期から全国的に「公園でのボール遊びが禁止」になり、「野球遊び」が事実上なくなった。
さらに、スパルタ方式の「野球指導」に反発を覚えて「野球よりもサッカーやその他のスポーツを」という親が多くなった。
※続きは以下ソースをご確認下さい
6/17(火) 12:03
スュニティコラム
https://news.yahoo.co.jp/articles/0eace3fb36eea0501c571f07e21f2ed1309fbfc5?page=2
引用元: ・【野球】複雑な組織、部員減少、曲がり角に立つ「中学野球」 [尺アジ★]
マジ不思議w
リーグ戦にして広く出場機会与えるようにしたらいいのに
昭和全開ワロタ😂😂
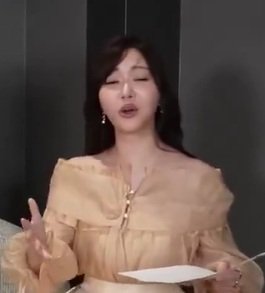








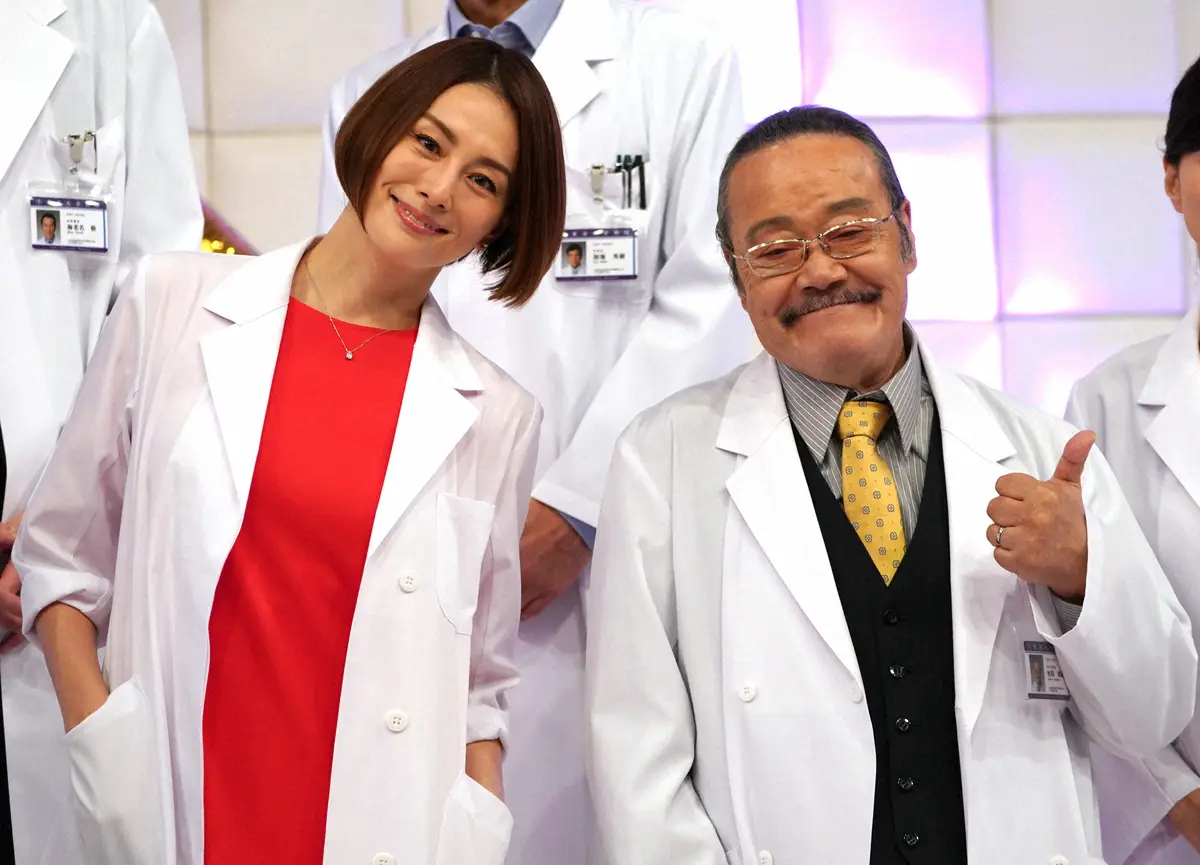


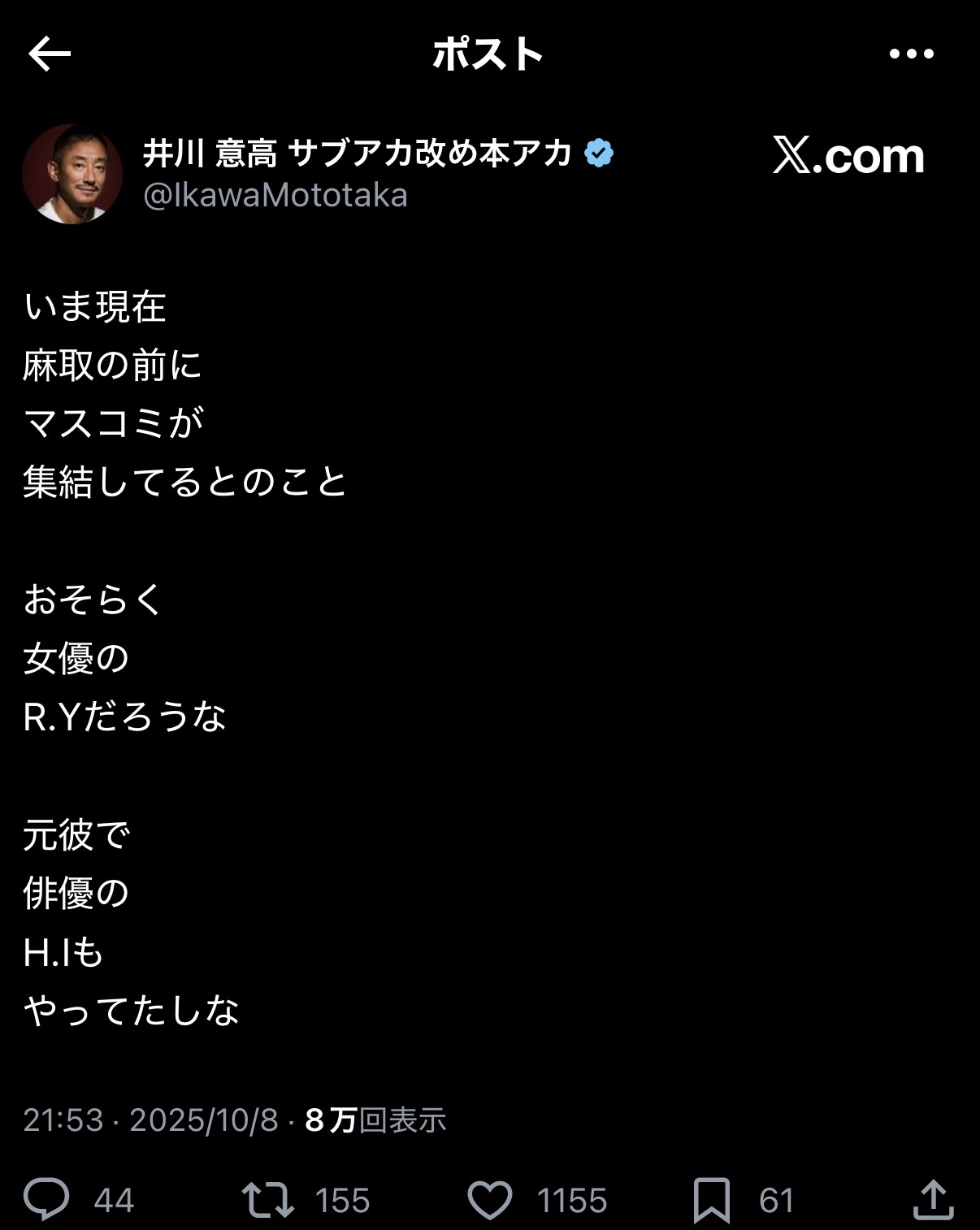

コメント