5/14(水) 6:00 Book Bang
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b7ad1419da72e7afb12b733ec175cb74ef513a3
養老さんはなぜ戦争を積極的に語らなかったのか
4月24日の「ニュースウオッチ9」(NHK)は「戦後80年」をテーマにしたコーナーで、『バカの壁』の著者として知られる解剖学者の養老孟司さんのインタビューを放送した。養老さんは1937年生まれ。子どもながらに戦争を体験したはずだが、あまりそれを積極的に語ってこなかったのはなぜか、とインタビュアーは質問。
その最大の理由として養老さんは、当時は子どもだったこと、直接いろんな被害を受けたわけではないことを挙げている。
そして別の理由として、「体験」を言葉で語ることの難しさを挙げ、次の様に説明した。
――自分は「ことば」をあまり信用していない。実体験のほうが重要だと考えているが、その実体験をことばで伝えることはとても難しい。どうやってもことばでは伝えられないものがある。しかし、聞き手にそういう認識や想像力がないと一生懸命に何かを伝えても違ったふうに伝わったりする、さらにまずいのは「わかったつもり」という状況を生んでしまうことだ――。
この「わかったつもり」に関して、番組内で養老さんは『バカの壁』で取り上げた事例をもとに説明を補い、語っている。460万部以上を売り上げた同書の第1章冒頭で取り上げているのがこの問題なのだ。
放送されたインタビューではかなり短く編集されており、少しわかりづらくなっていたので、ここで該当の部分を引用してみよう(以下、『バカの壁』より)。
***
■話せばわかる」は大嘘
「話してもわからない」ということを大学で痛感した例があります。イギリスのBBC放送が制作した、ある夫婦の妊娠から出産までを詳細に追ったドキュメンタリー番組を、北里大学薬学部の学生に見せた時のことです。
薬学部というのは、女子が6割強と、女子の方が多い。そういう場で、この番組の感想を学生に求めた結果が、非常に面白かった。男子学生と女子学生とで、はっきりと異なる反応が出たのです。
ビデオを見た女子学生のほとんどは「大変勉強になりました。新しい発見が沢山ありました」という感想でした。一方、それに対して、男子学生は皆一様に「こんなことは既に保健の授業で知っているようなことばかりだ」という答え。同じものを見ても正反対といってもよいくらいの違いが出てきたのです。
これは一体どういうことなのでしょうか。同じ大学の同じ学部ですから、少なくとも偏差値的な知的レベルに男女差は無い。だとしたら、どこからこの違いが生じるのか。
その答えは、与えられた情報に対する姿勢の問題だ、ということです。要するに、男というものは、「出産」ということについて実感を持ちたくない。だから同じビデオを見ても、女子のような発見が出来なかった、むしろ積極的に発見をしようとしなかったということです。
つまり、自分が知りたくないことについては自主的に情報を遮断してしまっている。ここに壁が存在しています。これも一種の「バカの壁」です。
このエピソードは物の見事に人間のわがまま勝手さを示しています。同じビデオを一緒に見ても、男子は「全部知っている」と言い、女子はディティールまで見て「新しい発見をした」と言う。明らかに男子は、あえて細部に目をつぶって「そんなの知ってましたよ」と言っているだけなのです。
私たちが日頃、安易に「知っている」ということの実態は、実はそんな程度なのだということです。ビデオを見た際の男女の反応の差というのはかっこうの例でしょう。
■「わかっている」という怖さ
「常識」=「コモンセンス」というのは、「物を知っている」つまり知識がある、ということではなく、「当たり前」のことを指す。ところが、その前提となる常識、当たり前のことについてのスタンスがずれているのに、「自分たちは知っている」と思ってしまうのが、そもそもの間違いなのです。この場合、それが男女の違いに顕著に現れた。
引用元: ・【文芸】「ことばだけで『わかったつもり』になるのは『バカの壁』を作ること」 養老孟司さんが体験の大切さを指摘する [湛然★]
女の子はいずれ自分たちが出産することもあると思っているから、真剣に細部までビデオを見る。自分の身に置き換えてみれば、そこで登場する妊婦の痛みや喜びといった感情も伝わってくるでしょう。従って、様々なディティールにも興味が湧きます。一方で男たちは「そんなの知らんよ」という態度です。彼らにとっては、目の前の映像は、これまでの知識をなぞったものに過ぎない。本当は、色々と知らない場面、情報が詰まっているはずなのに、それを見ずに「わかっている」と言う。
本当は何もわかっていないのに「わかっている」と思い込んで言うあたりが、怖いところです。
■知識と常識は違う
このように安易に「わかっている」と思える学生は、また安易に「先生、説明して下さい」と言いに来ます。しかし、物事は言葉で説明してわかることばかりではない。いつも言っているのですが、教えていて一番困るのが「説明して下さい」と言ってくる学生です。
もちろん、私は言葉による説明、コミュニケーションを否定するわけではない。しかし、それだけでは伝えられないこと、理解されないことがたくさんある、というのがわかっていない。そこがわかっていないから、「聞けばわかる」「話せばわかる」と思っているのです。
そんな学生に対して、私は、「簡単に説明しろって言うけれども、じゃあ、お前、例えば陣痛の痛みを口で説明することが出来るのか」と言ってみたりもします。もちろん、女性ならば陣痛を体感できますが、男性には出来ない。しかし、それでも出産を実際に間近に見れば、その痛みが何となくはわかる。少なくとも医学書だの保健の教科書だのの活字のみでわかったような気になるよりは、何かが伝わってくるはずです。
何でも簡単に「説明」さえすれば全てがわかるように思うのはどこかおかしい、ということがわかっていない。
(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)
リアリティがある訳ない
北朝鮮に行きもせずに北朝鮮を語る人の多いこと多いこと




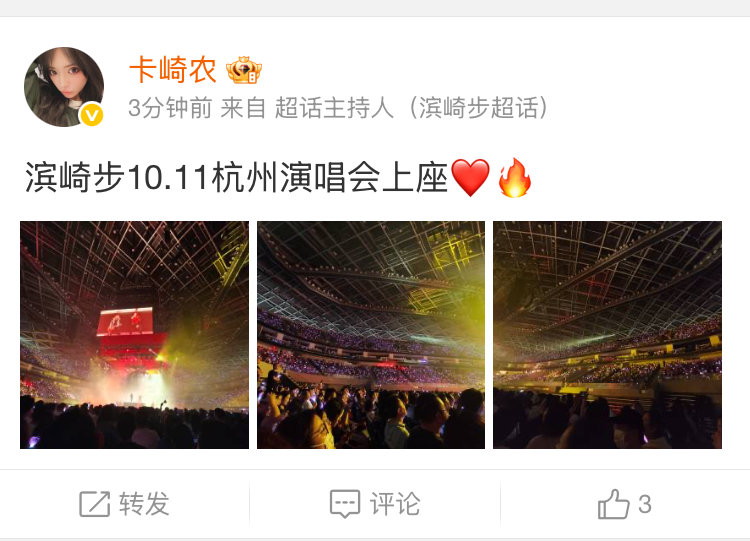




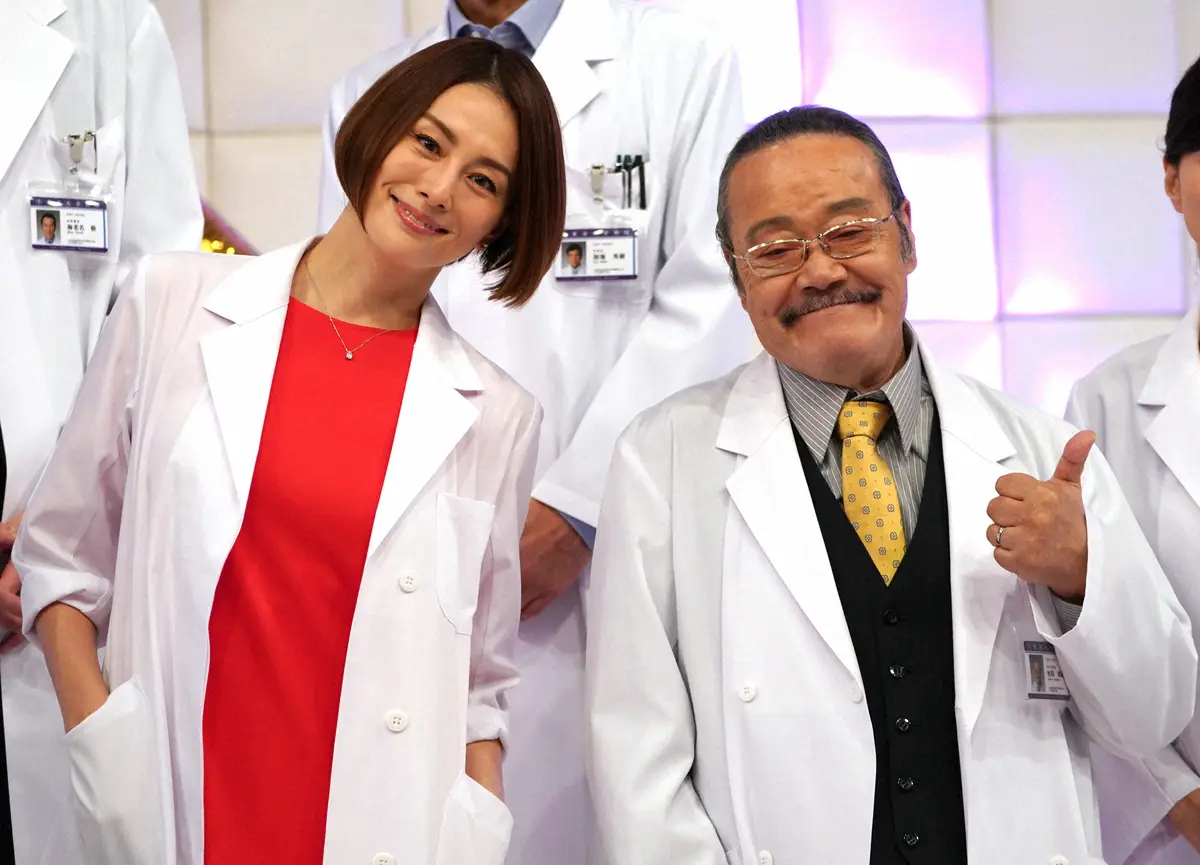



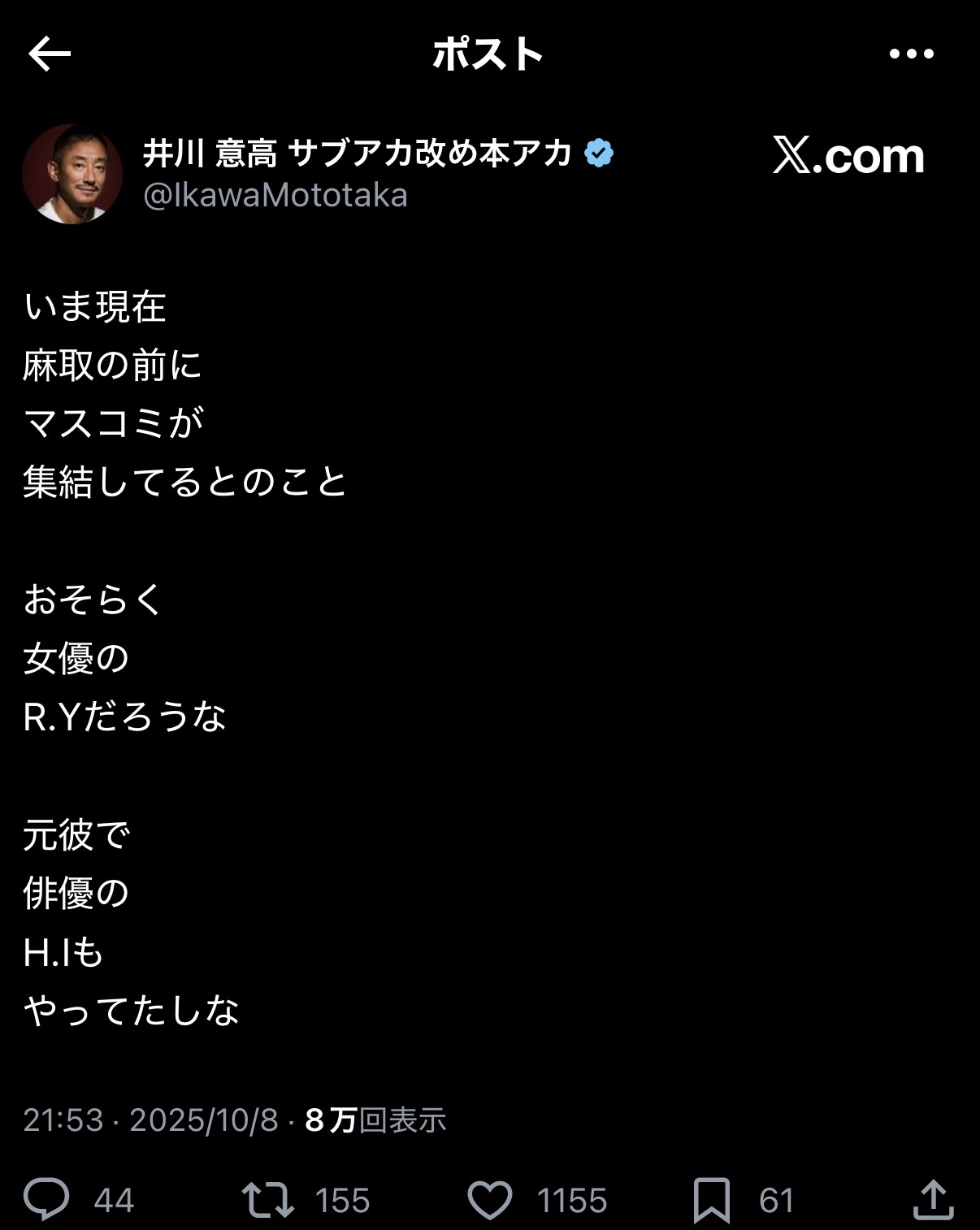
コメント