【滝澤三郎/東洋英和女学院大学名誉教授、元国連難民高等弁務官事務所駐日代表】 番組は、埼玉県川口市に暮らすクルド人への、SNS上での嫌悪・攻撃的発言が2023年以降急増して2500万件に達し、フェイク情報や誤解が世の中に拡散され、社会的緊張が高まっているというイントロで始まった。動画やナレーションをはさみながら、番組の核であるSNS投稿のタイムライン解析がなされた。特に投稿が増えたのは、(1)2023年4月の入管法改正案国会審議の際にクルド人大学生が「(自分がトルコに)強制送還されたら人生がめちゃくちゃになる」と主張したとき、(2)同年7月の川口市立医療センター前でのクルド人の集団騒動が報じられたとき、(3)同年12月に日本クルド文化協会がトルコ政府からテロ組織支援者認定されたとき、(4)2024年2月の反クルド人デモに対して同協会のワッカス事務局長が「日本人」と発言したとSNSで伝えられたとき、(5)クルド人少女が万引きをしたとの動画が投稿されたとき、(6)あるテレビ番組に出演したクルド人が、生活保護を月に34万円受け取っているとの偽情報が拡散したとき、などとしている。
この炎上パターンにつき、メディア研究とジャーナリズム研究の2人の大学教授が、「真偽不明の情報を組み合わせて『物語』が作られ、それが憎悪の連鎖を生む」と解説した。「リアルでないフェイクニュースの拡散がヘイトを助長している」のであり、拡散の背景には普通の日本人の感じるフラストレーションの高まりや「アテンション・エコノミー」というSNS特有の性質がある、というのだ。番組は、「クルド人を巡るSNS投稿は日本社会の痛みと共鳴するように膨れ上がっていった。『信じたいもの』をぶつけ合う、それがいつまで続くのだろうか」との抽象的なナレーションで終わった。
編集上の問題点
編集上の問題点としてまず気づくのは、番組に登場する関係者、つまりクルド人、彼らを支援する団体や個人、クルド人批判をする団体や個人と識者の発言の引用の長さの違いだ。番組を文字起こしして字数を数えると、約7000字の引用のうち、クルド人当事者が約40%、支援者、クルド人批判派、識者がそれぞれ約20%となっている。クルド人当事者と支援者が60%で批判派が20%だ。識者の発言はクルド人に同情的なので、それを加えるとクルド人寄りの話者が80%、批判的な話者は20%となる。意見が分かれるクルド人問題についてこれほどの差を付けるのは不公平としか言いようがなく、番組の狙いが「クルド人の声を大きく伝えること」にあったのではないかと疑わせる。さらに、川口市でのヘイト禁止条例の制定を訴える女性弁護士が2度にわたって登場していることは、番組がヘイト禁止条例の後押しをする政治的意図を持っていたとの推測を呼ぶ。
視聴者の感情を揺さぶる
番組は「被害者(クルド人)」「デマを流す者(SNS投稿者)」「両者の橋渡しをする知識人や支援者」という三層構造を採用していた。これは典型的なドキュメンタリーのナラティブ手法であり、「被害者への共感」→「加害者への批判」→「社会への提言」という流れで視聴者に訴えかける。登場人物の比重配分やナレーションの語調、場面の切り取り方や配置など映像の選び方も工夫されており、泣く子ども、誤認された少女の映像、電話で暴言を寄せる批判者などの様子が視聴者の感情を揺さぶる。この構成により、視聴者は「クルド人は可哀そう」「ヘイトスピーチをする者はひどい」「ヘイトを止めるためには行政や一般市民が何かをしないといけない」という気持ちを持つよう誘導される。クルド人をトルコで迫害され、日本でも差別される「被害者」として描き、日本社会はヘイト行動を許す「加害者」とされ、それを専門家が「権威付け」する――そんな構図が浮かんでくる。
続きはソースで
https://www.dailyshincho.jp/article/2025/04280606/?all=1&page=2
引用元: ・【NHK】引用発言の「8割」をクルド人側論者が占め…NHK「川口クルド人特集」は何が問題だったのか 専門家が感じた“政治的意図” [ネギうどん★]


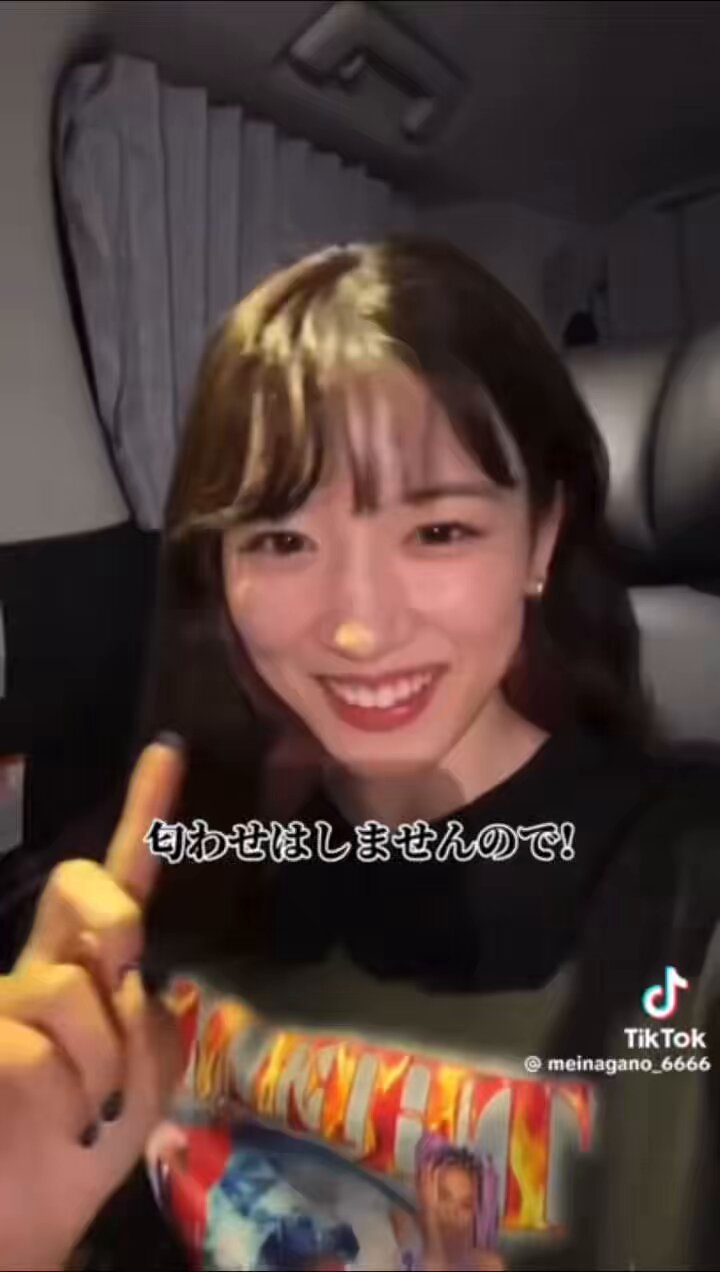

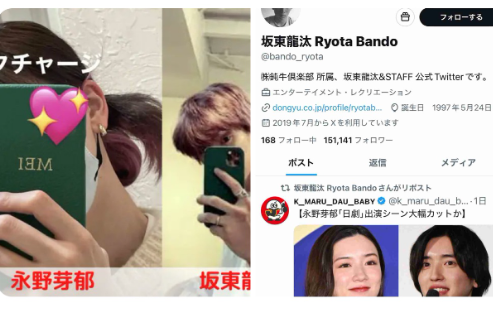
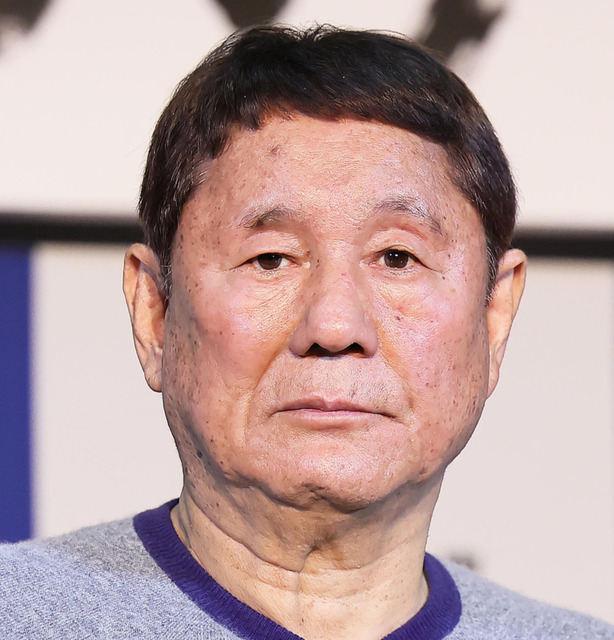
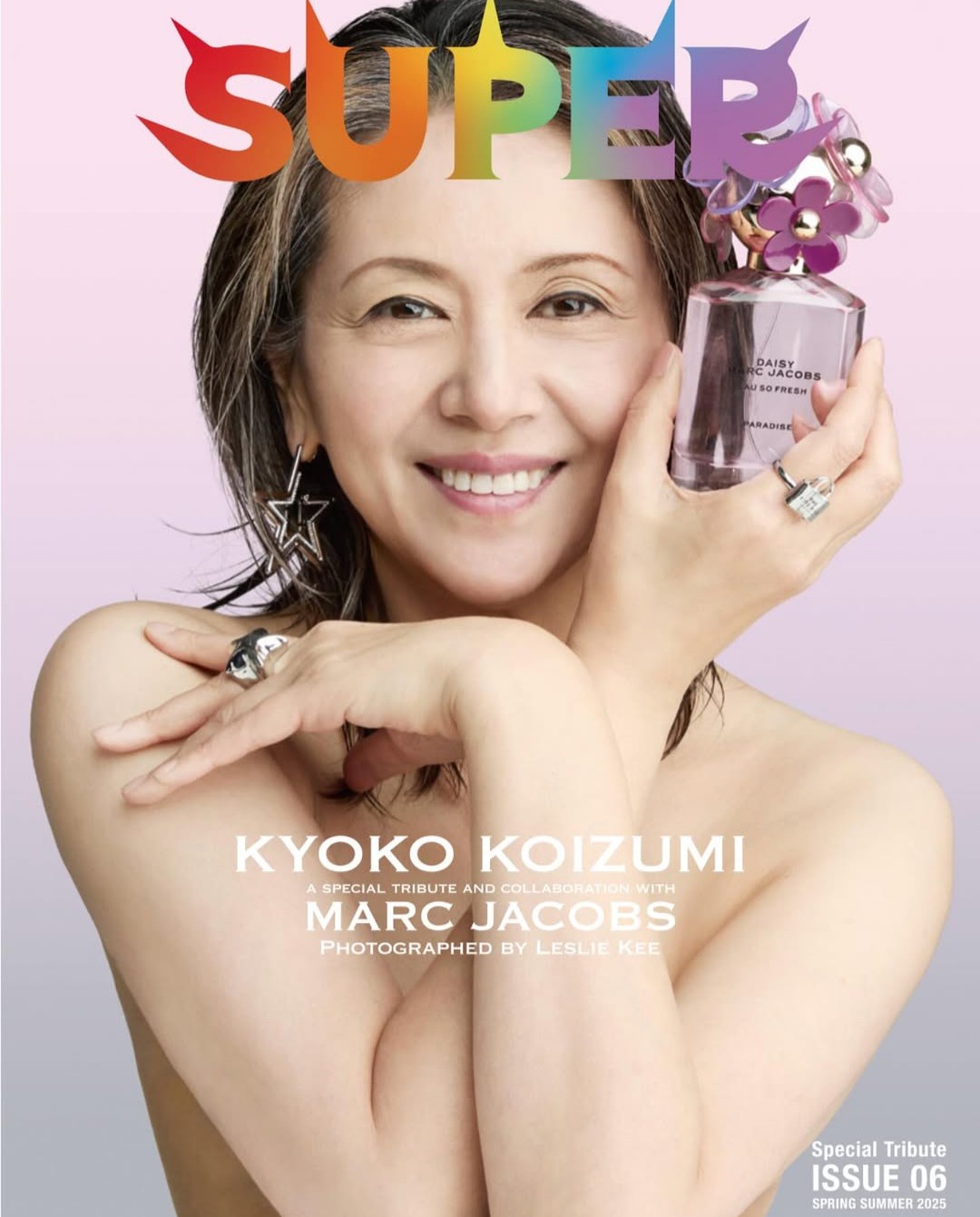




コメント