「親」がダメでも「孫」はOKな理由とは――。
在国会で審議されている下請け法改正案では、発注側のいわゆる「親事業者」と受注側の「下請け事業者」との価格決定の協議を義務化し、発注側による一方的な支払代金の決定を禁止。
材料費や人件費などが高騰する中で、受注側の価格転嫁を推進するのが主な狙いだ。
「下請け」の用語についても「上下関係を感じる」などとネガティブなイメージがあるとして改める。
「下請け事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」にそれぞれ改める。
用語の言い換えを巡っては、2003年の同法改正時も俎上(そじょう)に載った。
当時の国会審議で、参考人として出席した業界団体代表が「『下請け』という言葉は差別用語。改正してほしい」と訴えたが、「関係法令まで変える必要があり、作業が煩雑」といった理由で断念した経緯がある。
その後民間では既に言い換えが進んでおり、「協力会社」や「パートナー企業」といった言葉も一般化している。
今回の法改正でようやく実態に追い付くことになる。
ただ、関係者によると、「下請け」は変更される一方、さらに先の「孫請け」「ひ孫請け」などについては変更しない方針だ。
「下請け」に上下関係のイメージが根強い一方、「孫」にそれほどネガティブなイメージがないことなどが理由という。
つづきはこちら



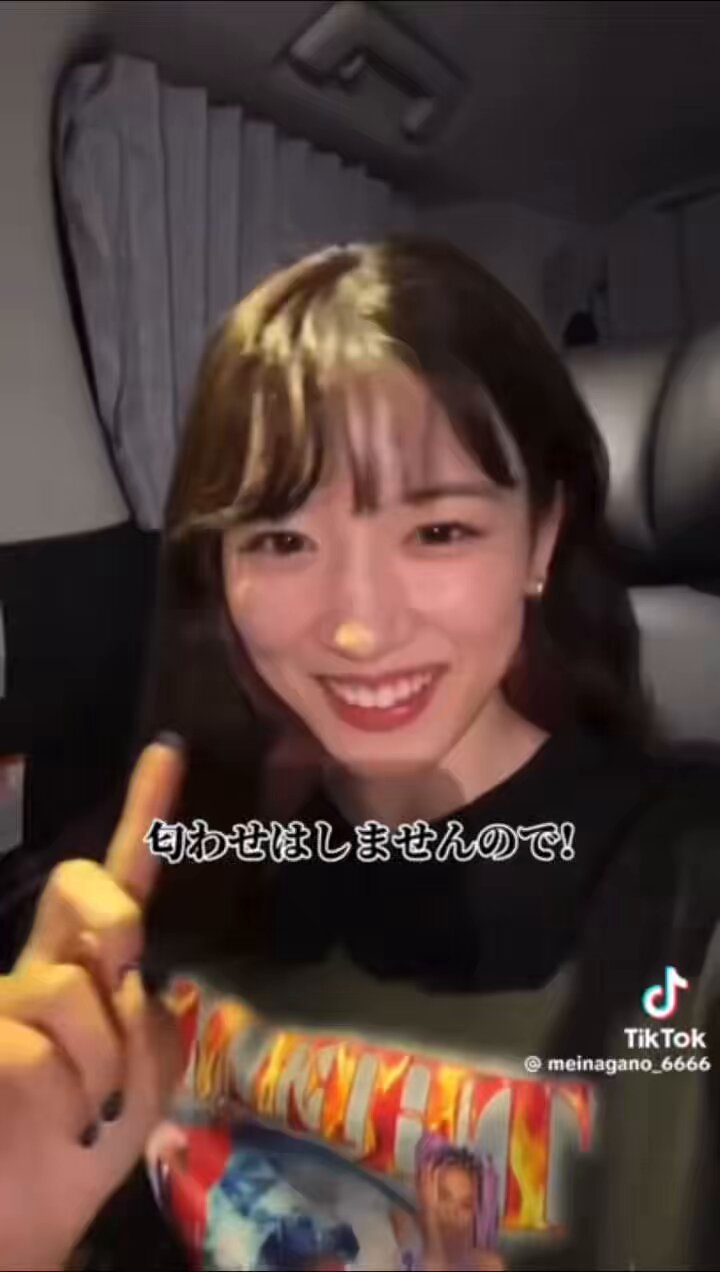
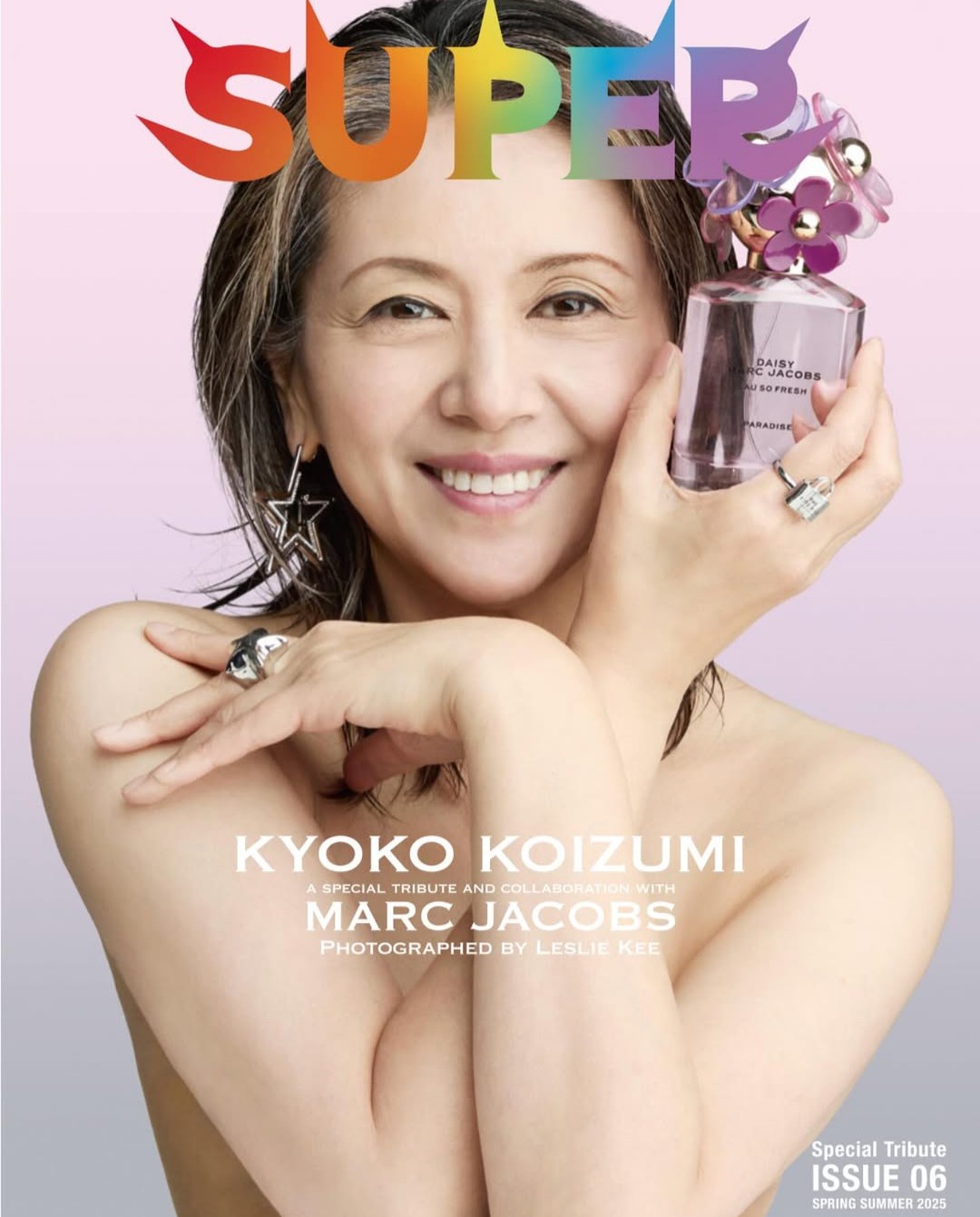

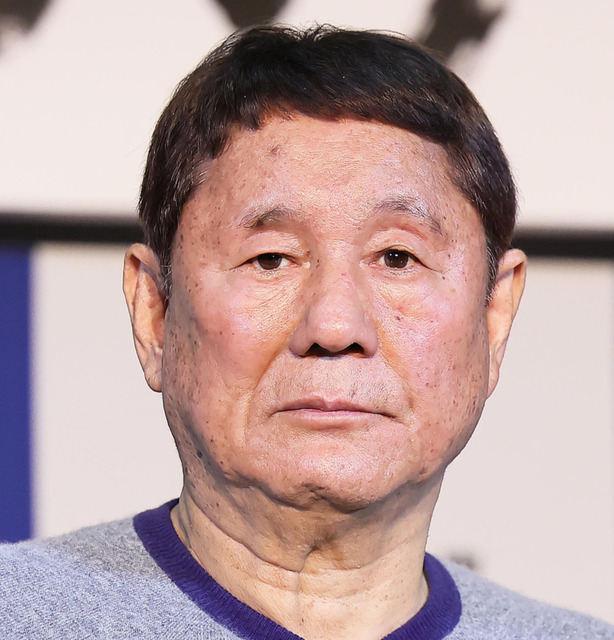




コメント