時代の変化でこの行事の「あり方」も変わってきています。
愛知県愛西市にある「市江小学校」。
寒空のもと、子どもたちが取り組んでいるのは、「持久走」の授業です。
持久走といえば――
「走れる人は走れるけど、(自分は)なかなか走れなかった」(50代)
「楽しい思い出としては残っていない」(50代)
「坂になると脇腹を押さえながら、走る感じで嫌だった」(20代)
親世代からすれば、苦しい思いをして長い距離を走り切る、体育の授業の中でも特に苦手だったという人も多いようですが――
Q.持久走の授業はどう?
「楽しいです。楽しいけどきついです。自分のタイムがものすごく縮まると至高の喜びです」(小学4年生)
そう!今、学校での「持久走」の行事は「楽しさ」を重視する形に変わりつつあるんです。
「楽しさ」を重視する形に変化
今の持久走は「楽しさ」を重視する形に変化
では、どんな変化があったのか?
4年生が走っているところを見せてもらいました。
「競争じゃないからね。自分の目標、自分が一番のライバルです」(指導員 横井達治さん)
4年生はグラウンドを4周、640mを走ります。
走るのが得意な子はぐんぐん距離を伸ばしていきますが、中には歩いている子もいます。
指導員は――
「歩いてもいいけど、ちょっと走ろうね」(横井さん)
厳しい指導はせず、歩くことを肯定し、やさしい言葉をかけます。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/9bb2f5afd2a7fcac7dd880ffdb7463317f226a2e
引用元: ・【持久走】「歩いても大丈夫」 時代の変化に伴い「楽しさ」重視へ










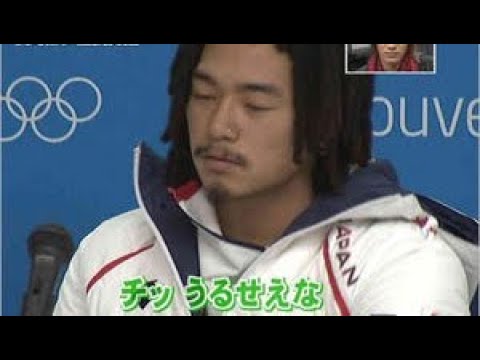


コメント