北陸新幹線敦賀以西の「小浜ルート」について馳知事はルート選定に向け具体的な議論が重要だとの考えを示しました。
北陸新幹線の「小浜ルート」については京都府などが工期の長期化などを理由に慎重な立場を表明しています。
25日の県政報告会で馳知事は延伸については京都を含めた沿線自治体を納得させるべきだと指摘し、改めてルート選定に向けた説明や議論の場が必要だと語りました。
馳知事:
「説明がないのに小浜で納得しろとは残念ながらできない」
「沿線の自治体が合意ができないに京都府の皆さんが合意できない状況があるならば打開するような議論を進めていくことをお願いしたい」
着工に向けては費用対効果などデータを用いた具体的な議論が必要だと強調しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/db0851d8d7170e711dbabba8d319a79752e7c75a
引用元: ・北陸新幹線 馳知事「ルート選定には具体的議論が必要」「説明なしに”小浜”は…」 [178716317]
北陸新幹線「小浜ルート」に京都の懸念は山積み 財源や地下水、残土…負担に見合う恩恵はあるのか 京都新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/cce1931afaa004fecb481560496d7a9aa94b1b42
北陸新幹線の敦賀(福井県)―新大阪間延伸計画で、与党整備委員会が目指していた2025年度中の着工を断念した。
京都府や京都市がヒアリングで訴えた懸念への回答は示されないままだが、与党整備委は今後、市民も含め理解を得るため説明していくという。
懸念を取り除くには、財源では整備委幹部が主張する「全額国負担」が実現する制度的な裏付けなどの説明が不可欠だ。
地下水への影響や建設残土の処分を巡っては、「問題ない」と判断できるだけの科学的な知見や対策案を示すことが求められる。積み上がる「懸念」をまとめた。
■「全額国費負担」主張も…
最大5兆3千億円とされる巨額の事業費に伴う地方の財政負担は、財政が厳しい府と京都市にとって大きな懸念材料になっている。
与党整備委員長の西田昌司参院議員(京都選挙区)は「全額国費負担」を主張するが、中野洋昌国土交通相は17日の会見で「現時点で(負担の在り方を)見直すことは予定していない」と否定。
松井孝治市長も「国交省以外の省庁から得ている情報では、市の負担がないなんてことはない」と懐疑的な見方を示す。
事業費のうちJR西日本が支払う「貸付料」を除いた残りを国が3分の2、自治体が3分の1の割合で負担する現行の仕組みは、延伸地域に利益があることを前提に1997年につくられた。
一方、敦賀―新大阪間で府内に設けられる駅は京都駅周辺と松井山手の2駅で、どれだけ恩恵があるか見通せない。
府市は積極的に延伸を誘致しておらず、西脇隆俊知事も「受益に応じた負担」を繰り返し主張してきた。
着工条件の一つで、見込み利益を事業費で割った「費用対効果」を国などが示していない点も自治体側の不信の一因だ。
2016年の小浜ルート決定時の試算では「1・1」と、投資に見合うとされる「1」を辛うじて上回ったが、今年8月に詳細ルート3案が示された際は新たな数値は出ず、
詳細ルートが確定してから算定するとした。
西田委員長は「1より低かったらやらないというルールではない」と訴えるが、理解が広がっているとは言えないのが現状だ。
■「豆腐にストロー通すようなもの」
整備による影響で最も懸念の声が噴出したのが地下水だ。穴を掘りながらトンネルを造るシールドトンネル工事は「豆腐にストローを通すようなもの」(国交省幹部)とされ、
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行ったシミュレーションでも地下水への影響はなかったという。
ただ、シミュレーション結果は公開されておらず、京都市の松井孝治市長は「影響があるのかないのか、現時点では確信を持てない」と疑問視する。
駅舎は「東西案」「南北案」「桂川案」のいずれの場合でも土留めで地下水をせき止めた上で、地上から穴を掘って建設される。
だが、開削はかつて市営地下鉄工事で井戸枯れが相次いだ工法で、国交省幹線鉄道課も取材に、周辺で水枯れが「全く発生しないわけではない」と影響を認める。
具体的な影響の範囲や補償方法は未提示のままだ。
地下水は酒造や茶道、豆腐作り、銭湯など幅広い業種に関わり、懸念の声は以前から出ていた。
府酒造組合連合会と伏見酒造組合が今月2日、府と市に地下水への配慮を求める要望書を提出したが、内容は2017年とほぼ同じ。
7年たっても解消されない不安に、関係者のいら立ちは募る。
京都の地質や地層に詳しい京都大の尾池和夫名誉教授は
「地下水はすべてつながっており、掘った場所と離れたところで影響が出る可能性もある。地下水の流れを変えるということは広い範囲で水質や水量を変えるということだ」と警鐘を鳴らす。
■残土は東京ドーム16杯分
国交省によると、「東西案」「南北案」「桂川案」のいずれになった場合でも、
山岳トンネルの掘削や大深度地下工事で約2千万立方メートル(東京ドーム16杯分)の残土の発生が見込まれるというが、具体的な受け入れ候補地は提示されていない。
関係者によると、京都市は2021年ごろ整備委幹部の要請を受け、市内で複数の候補地を探し、水面下で提示した。
しかし、盛り土の崩落を防ぐ大規模工事が必要だったり、市内からのアクセスが難しかったりして、正式な候補地として俎上(そじょう)に載ることはなかった。
具体的な受け入れの動きは、今月4日の整備委で福井県が敦賀港で約40万立方メートルの受け入れが可能と示したのにとどまる。
そもそも「2千万立方メートル」は日本維新の会の国会議員が国交省から11月下旬に聞き取った数字で、公式な資料に記載はない。
量について、同省幹線鉄道課の担当者は「走る距離が長ければ土の量も多くなる」と淡々と語るが、かつて一部で報じられた
「880万立方メートル」との推計を大幅に上回る量に住民らから驚きの声が聞かれる。
また府中北部の土壌は自然由来のヒ素の濃度が高く、山岳トンネル区間で出る残土の約30%は遮水シートによる封じ込めや中間処理が必要な「対策土」となる見通しだが、
対策にどのぐらいの費用がかかるのかは示されていない。残土を運搬する車両による交通渋滞への懸念も強まっている。





_618650.jpg)

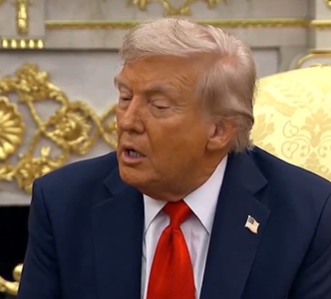
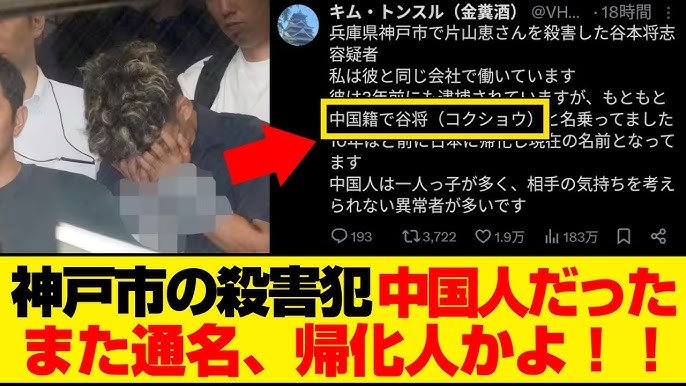

コメント