
このウキクサが12月になっても 大繁殖しているという。
「岩瀬ダム」は小林市を流れる岩瀬川と大淀川の合流点付近に位置する宮崎県営のダム。
2024年8月、上空から岩瀬ダムを見ると鮮やかな黄緑色が際立って見えていた。
ウキクサのそのほとんどは、ウオーターレタスと呼ばれる「ボタンウキクサ」だ。
(垣内記者)
「根の長さ80センチぐらいあるんじゃないでしょうか?横幅も30センチぐらいはありそうです。葉っぱは結構丈夫で、周りに小さな毛が生えているので、ふわふわしていてすごい触り心地はいいです」
もともと「ボタンウキクサ」は、観賞用として輸入された熱帯原産のサトイモ科の植物で「特定外来生物」に指定されている。
岩瀬ダムでは2023年10月にウキクサが確認され、11月には約11ヘクタールに繁殖。
宮崎県では、2024年2月から4月にかけて除去作業を行い1ヘクタールまで減らした。
その直後の写真がこれだ。
■2キロ以上 東京ドーム9個分にあたる面積に
しかし・・・
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「5月の連休明け以降に、爆発的に増殖して現在に至っているところです」
およそ1か月後、ウキクサは再び大繁殖してしまった。
8月、小林市の上空から岩瀬ダムを見てみると・・・
水面を覆いつくすウキクサは、2キロ以上にわたって続いているのが確認できた。
その広さは40ヘクタール、東京ドーム9個分にあたる面積だ。
ここ数か月でその生息域が40倍に拡大したことになる。
県によると、岩瀬ダムでは2010年以降、数回、ウキクサの発生が確認されているそうだが、ここまで繁殖するのは初めてだという。
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「このように爆発的に増えたのは今回が初めてというような経験になってます。声にならないというかびっくりするの一言ですね」
引用元: ・ダムの水面を覆いつくすウオーターレタス「ウキクサ」が80ヘクタールに大繁殖 除去費用2億円超 [582792952]
■クローンとして繁殖 なぜ、ボタンウキクサが爆発的に増えてしまったのか。
南九州大学環境園芸学部の山口健一教授に8月に現場を見てもらうと・・・
(南九州大学環境園芸学部・山口健一教授)
「ここの特徴というのは一つ一つの個体がかなり大きいので、もしかしたら窒素とか、リン、この雑草が増える栄養素というのがいっぱいあるのかもしれないですね」
ボタンウキクサの最大の特徴はその繁殖力の強さ。
花を咲かせて種をつけるため、風や水、動物、人間などによって拡散されるほか、
水の中で横に茎を伸ばし、その先に新たな株をつけて増殖するという。
(南九州大学環境園芸学部・山口健一教授)
「水平方向にね、次々クローンとして繁殖をします。ですから、あっという間にこのように水面全体がボタンウキクサによって覆われてしまいます」
そして大繁殖の要因のひとつとして、水の温度も関係しているという。
(南九州大学環境園芸学部・山口健一教授)
「基本的には、ボタンウキクサの場合は10℃を超えるとストロン(水平方向の茎)を形成して増殖をするということなんですけども10℃を下回ればいいかというと必ずしもそうではなくて10℃を下回ったとしても、どこかで数株は冬越しをしてしまう個体が出てしまいます。そうすると、彼らの生き残り戦略で次の年はこのような状況になってしまいます」
さらに、ボタンウキクサの間から縦に伸び、紫色の花を咲かせているホテイアオイも同様に繁殖力が強い植物だ。
■大繁殖したウキクサは現在どうなっているのか
2024年12月、調査班は 再び岩瀬ダムの上空に向かった。
(垣内記者)
「小林市の岩瀬ダム上空に到着しました。夏に確認したときは、青々とした緑色だったウキクサですが、現在は、茶色く変化しています。そして、その繁殖の範囲ですが、上流側にかなり広がっているように見えます」
さらに・・・
(垣内記者)
「支流にも広範囲にウキクサが広がっています。こちらは、青々とした緑が健在です」
焼き肉くるむと最高
■80ヘクタールにまで拡大県によると、7月に、40ヘクタールだったウキクサの繁殖範囲は、現在、その2倍となるおよそ80ヘクタールにまで拡大しているという。
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「外来種の繁殖力の強さにびっくりしているところ。今年の夏が非常に暑かったということ、それと岩瀬ダムの貯水池の位置、周辺の環境が水質に与える影響などが相まって(繁殖した)」
岩瀬ダムの周辺では、現在、重機を使った作業が行われている。
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「(ウキクサを)陸揚げをするための事前の準備として現地にヤード(広場)の確保をしているところ」
県では、1月から、専用の船を使ってウキクサの除去を始めることにしている。
その費用として2億1600万円の補正予算が組まれたが…
(都城土木事務所・鏡園義幸課長)
「私達も想定する以上に繁殖力が強くて広がってしまったということで予算が足りないのではないかっていうところも懸念されるところですけれども、まずはコスト削減ということも考えていて、ウキクサを一時仮置きする場所を近くに確保するということを考えていて、最終的に搬出するのは後ほど検討していく」
県ではウキクサの繁殖が再び始まる4月から5月までには、作業を完了させたいとしている。
ただ、他県の例を踏まえると、根絶は難しいのが現状で、専門家は、こうした植物は根絶させるのではなく、人や野生生物、産業に影響を及ぼさない程度に、低い密度でコントロールすることが重要だとしている。
県では、ウキクサ撤去完了後の対策として、
(1)早期に発見し、早期に回収するため、特に夏場は巡視頻度を増やすほか、漁協などにも協力してもらう。
(2)ダム周辺に看板を設置し、外来種のウキクサを持ち帰ったり捨てたりしないよう
呼びかけている。
また、ボタンウキクサを持ち帰ったり、育てたり販売することは法律で禁止されている。
>>2024年8月公開の 増殖しすぎてドローンで全体を映せない 数ヶ月でダムの水面を覆いつくした緑の正体は「特定外来生物」に追加取材したものを加えて再構成しました。





_618650.jpg)

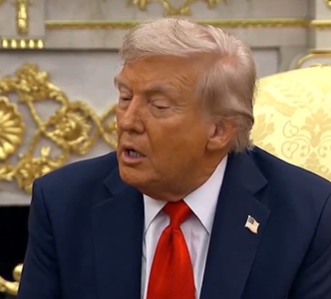
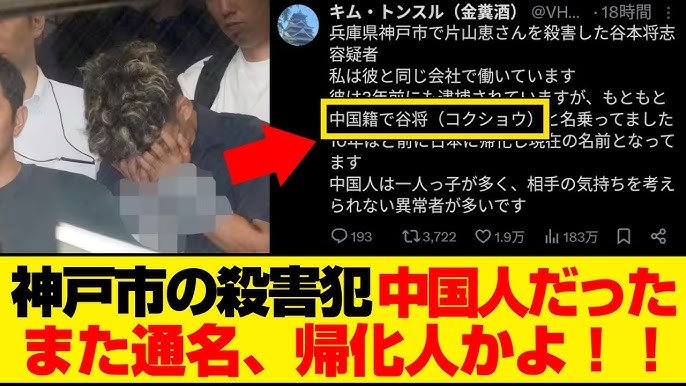

コメント