日本列島は昨年も多くの災害に見舞われた。学生時代から災害ボランティアに従事し、その後、研究者としても中山間地域の被災地の復興過程に関わってきた大阪大学准教授の宮本匠氏はその過程で、被災地の復興には「空気」が決定的に重要な意味を持つことに気づいたという。
2004年に発生した新潟県中越地震の際、大学生だった宮本氏は、復興ボランティアとして新潟県を訪れて以来、20年近くにわたり中越地域に関わってきた。長岡市の木沢集落で出会った住民たちにまた会いたいと思い、年の半分以上を木沢で過ごすようになったという。
親しくなった木沢集落の人々は、山や畑では誇らしげに自分たちの村の話をしてくれるのに、復興について話し合う会合になると途端に「水がない」、「子どもがいない」と、将来に対する諦めや足りない物を求める発言が相次いだという。しかし、宮本氏が住民たちの話をひたすら聞くことに徹するようにすると、住民たちの語りは次第に「ここにはサワガニがいる」、「ウラシマソウがある」といった前向きなものに変わっていったという。
引用元: ・【空気】日本人が流されがちだと言われる「空気」こそが「失われた30年」から脱することができない

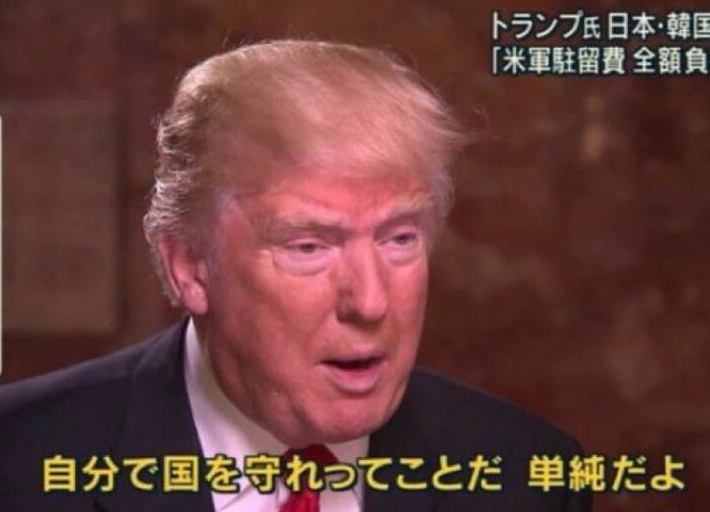
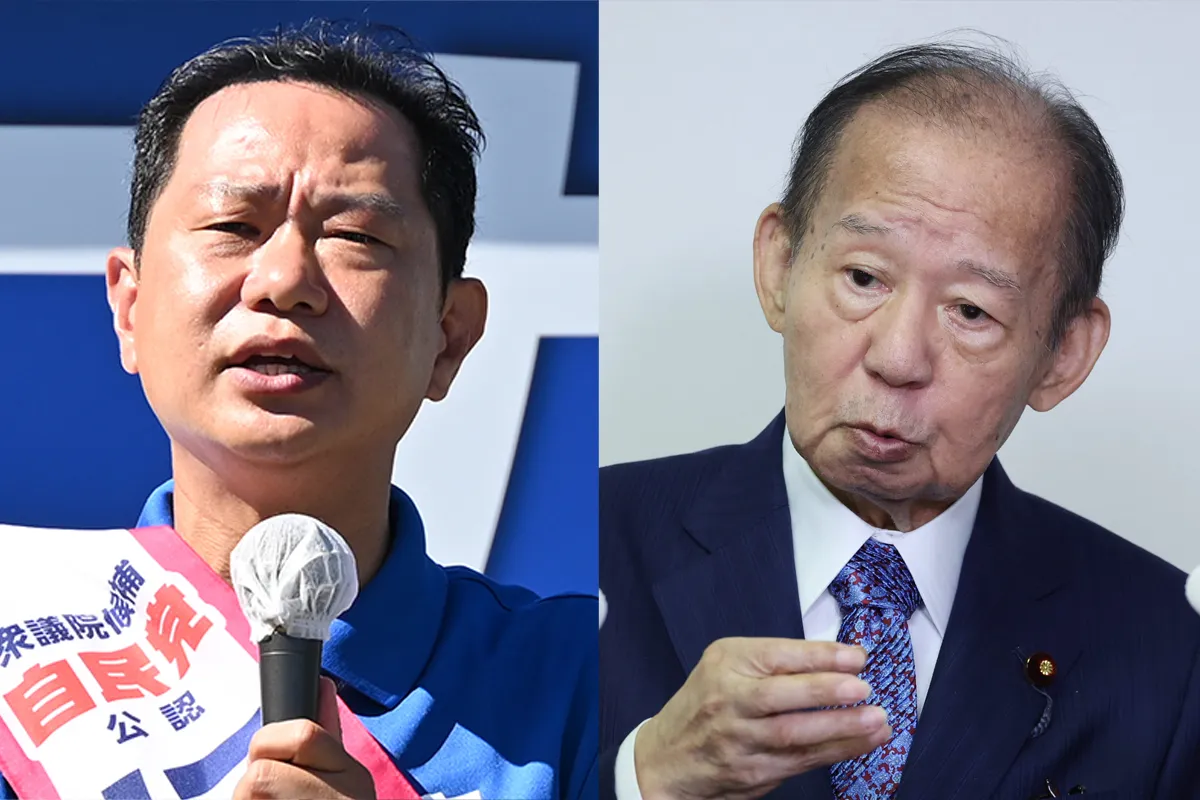










コメント