今年もビッグニュースの連続だった。やれドイツが、そしてインドが日本をGDPで抜いていく──とか。しかしいま点検してみると、
トランプ再選を除けば、「それほど大したことではなかった」ものがほとんどだ。
問題は、メディアがその点検をせずにおくものだから、われわれの頭には最初の大げさな見出しが実際に起きたこととして頭に
刷り込まれてしまうことだ。例えば、「ドイツが日本をGDPで抜いた」「インドが2025年、日本をGDPで抜く」という先走った報道が、
「日本は沈む一方」という日本人のマゾ的な諦めをますます強固なものにしてしまう。
IMFは23年10月の世界経済見通しで、「23年はドイツのGDPが日本を抜いて世界3位になるだろう」と予測した。
これは、ドイツより日本で騒がれた。ドイツ人にしてみれば、ドイツが低成長とインフレに苦しんでいるときにIMFは何を言う、
という気持ちだっただろう。
ドイツ経済は、05年までの社会民主党シュレーダー政権の時代に労働者の権利を制限することで賃金の上昇を抑え、
さらに10年代後半のユーロ安に乗って輸出を急増させた。メルケル前政権はこの好況の上にあぐらをかいていたのだが、賃金の上昇、
そして原発撤廃やロシアからの天然ガス輸入の一時的停止による電力価格の上昇、さらにユーロ高のトリプルパンチで競争力を失った。
今年の成長率は0.01%と予想されている。
円はこの1年ほど、「円キャリートレード」(低金利の円を借りて高金利のドルなどを仕入れ、これで高利を得て儲けるやり方)で、
過度な円安を仕掛けられた。これからドル、ユーロ双方に対して円が値上がりすれば、ドル換算のGDPで日本はドイツを再び抜くだろう。
■インドへの海外投資は急落傾向
だからといって、昨今の西欧メディアのように、ドイツ経済を古い製造業立国モデルにしがみつき、ITやAI化に立ち遅れた「欧州の病人」
と揶揄するのは行きすぎだ。実態はそれほど悪くない。世界でトップシェアの製品を作る中小企業の数は世界最多。
IT部門ではシーメンス、SAP、ボッシュ、半導体でもパワー半導体で世界首位のインフィニオンを擁しているし、
台湾のTSMCはドイツに生産拠点を建設している。
もう1つ。「3年内には日本やドイツを抜いて世界3位」になるといわれたインド経済も、21年以降は成長率を落としている。
インドがその歴史の中で積み重ねてきた、癒着・腐敗した利権構造や中国以上の所得格差、クモの巣のような規制などを改めることが
できていないからだ。
<日本は言われているほど駄目じゃない>
既得権構造を破ることのできるのは巨大な外国資本で、1990年代後半からの中国は外資に優遇措置を与えることでこれを実現したのだが、
インドでは政治にそれだけの力がない。だから、「中国に代わる輸出産業立地先」と言われながら、外国企業による直接投資は20年を
ピークに急落傾向にある。われわれが「インド経済は希望の星」という言葉に裏切られるのは、最近20年間でももう3回目だ。
日本は逆で、「駄目と言われていたが、案外すごい」の口。人口が減るからもう駄目だと自ら思い込んでいるが、人口が減れば
通勤も楽になるし、これまでより優れた利益率の高いものを売っていけば、GDPも落ちない。それに、これまで蓄積した富は利子を生む。
それも合わせて日本経済はそれなりの成長を続けていけるのだ。来年に向けての一番の薬は、マゾ的思考をやめることだろう。
河東哲夫(外交アナリスト)
12/14(土) 17:50配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/0edeb7c61ab7534cb15f05a577a7fe71f213ee13
引用元: ・【Newsweek】 来年に向けて日本人の一番の薬は「マゾ的思考」をやめること [12/16] [仮面ウニダー★]









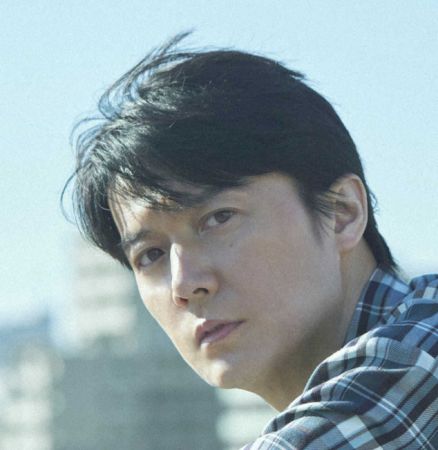


コメント