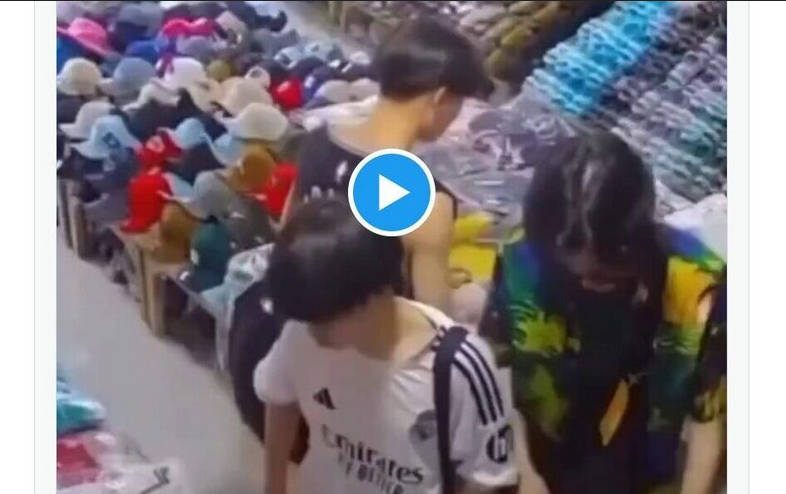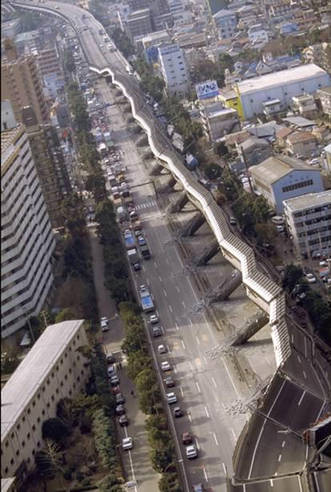この国会中継を見ていて、中国ウォッチャーの私は「もう一つの危機事態」が気になりだした。それは中国の「過敏な反応」である。
(略)
外交部の報道官が、これだけ長々と日本政府を批判するのは、久方ぶりのことだ。日本の政権が、中国に比較的融和的だった石破茂内閣から、強硬な高市早苗内閣に変わったため、一発威嚇しておこうという意図もあったろう。
だがそれと同時に、「中国自身の変化」も感じたのだ。その背景にあるのは、先月20日から23日まで開かれた中国共産党の年に一度の重要会議「4中全会」(中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議)である。
習近平主席の外交スタンスが変化
中国政治というのは基本的に、「緊」(ジン)と「松」(ソン)という逆方向に向くベクトルの引っ張り合いで成り立っている。前者は、社会を引き締めて安全な社会主義体制を構築すること。後者は、社会を緩めて市場経済による発展を促していくことである。
習近平総書記は、基本的に「緊」の側に立つリーダーである。実際、13年前に共産党トップに就いて以来、そうした路線を貫いてきた。
ところが中国経済の失速が、いかんともしがたいところまで来た。それで私が見るに、昨年3月の全国人民代表大会(国会)を契機として、「松」に方向転換を図った。
今年1月に太平洋の向こう側でドナルド・トランプ大統領が就任し、関税を振りかざすようになると、その対策のため、4月8日と9日に「中央周辺工作会議」を開いた。それまでの「戦狼(せんろう)外交」(狼のように戦う外交)を捨てて、「周辺諸国との友好を図れ!」と、習近平主席が号令をかけたのだ。その影響で、対日外交も「松」に転じた。
ところが、先月の「4中全会」で見られたのは、元の習近平政治である「緊」に回帰していく流れだった。再び潮目が変わったのである。
例えば、今月5日から10日まで、上海で8回目の「進博会」(ジンボーフイ=中国国際輸入博覧会)が開かれた。これは、「中国は輸出ばかりしている」という海外の非難をかわすため、習近平主席の肝煎りで、2018年に始めた毎年11月に行う国家級のイベントだ。
1回目と2回目は習主席が上海に赴き、「中国は輸入大国を目指す」という基調演説をぶった。以後はコロナ禍に入ったため、オンラインでスピーチした。
しかしながら、昨年の第7回から、ナンバー2の李強首相に任せて参加しなくなった。今年は完全無視だった。その間、海南島の軍事基地で3隻目となる空母「福建」に乗り込んだり、広州で国威発揚のための「国体」(中華人民共和国第15回運動会)に出席したりしているのだ。
細る中国とのパイプ
こうした流れを見ると、単に高市首相の「存立危機事態」発言を巡るやりとりというより、もっと深いところで日中関係の悪化が懸念されるのである。
折しも同盟国のアメリカは、10月30日の米中首脳会談後に、「台湾の話はしていない」などと嘯(うそぶ)く無責任極まりない大統領が統治している。
高市政権には、これまで中国とのパイプ役だった森山裕幹事長も、公明党もいない。中国問題がアキレス腱とならぬよう要警戒である。
全文はソースで
引用元: ・高市首相の「存立危機事態」発言に過敏反応する中国、背景にあるのは習近平主席の「外交スタンスの転換」[11/12] [昆虫図鑑★]
まぁ、海洋進出しないと、国内はヤバいらしいから