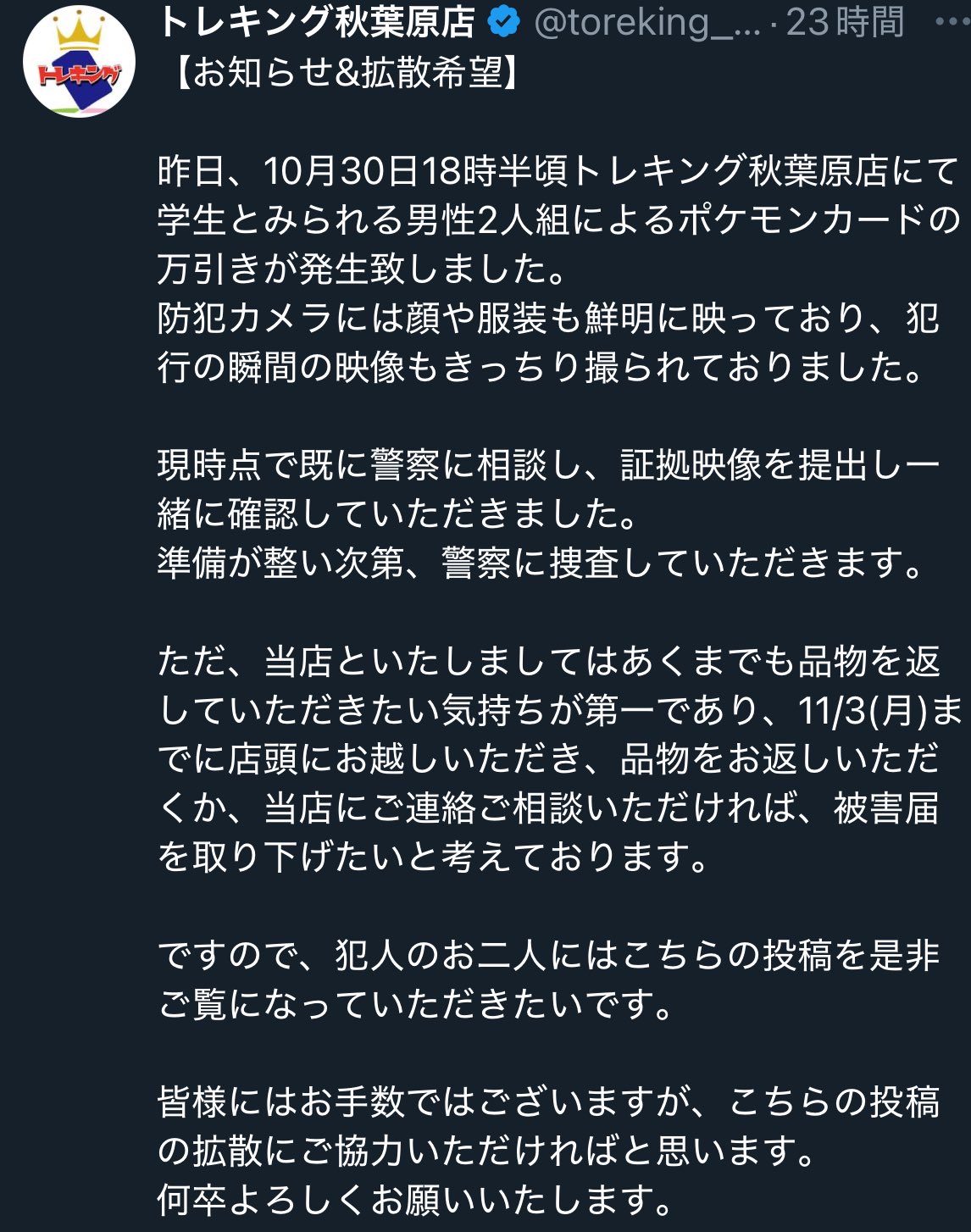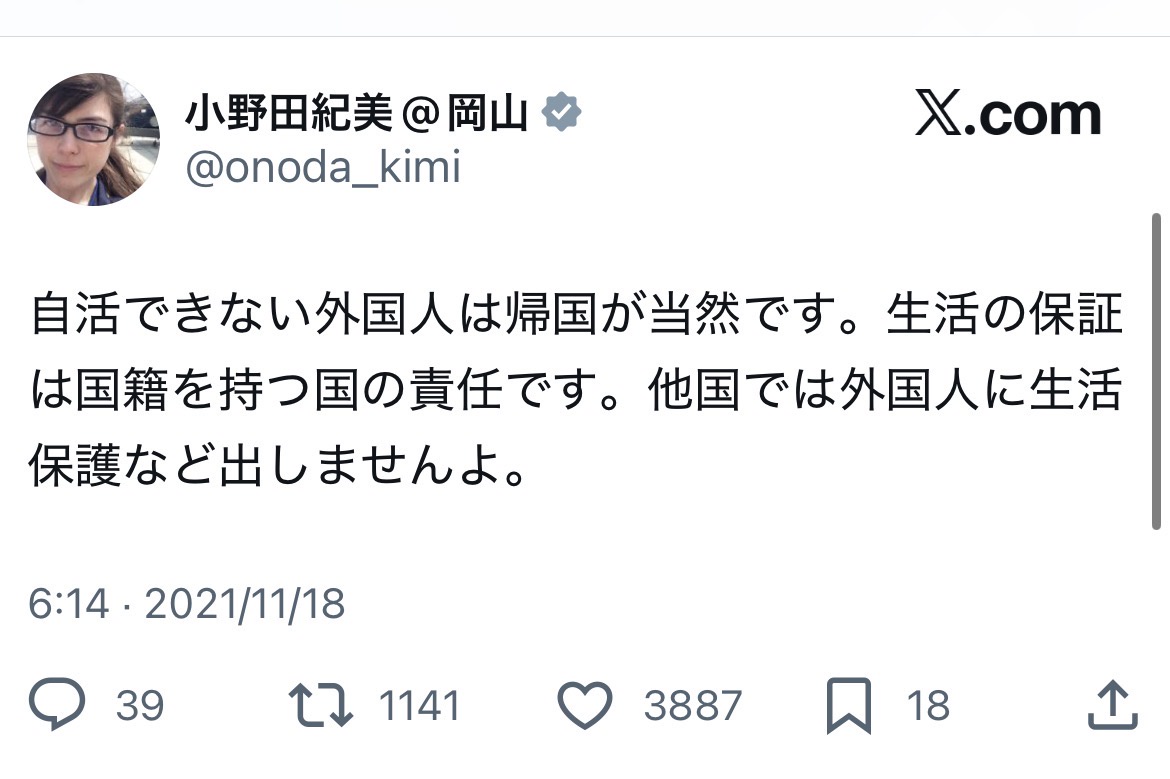https://merkmal-biz.jp/post/103380
都市部で1664万人が利用するタクシー配車アプリ。しかし地方では高齢化と車両不足が障壁となり、利便性格差が顕在化。技術革新と制度整備で格差解消の可能性を探る。
都市部では、スマートフォンでボタンを押すだけでタクシーを呼べる配車アプリが日常風景になっている。通勤や買い物、深夜の帰宅など、さまざまな場面で活用されており、時間の節約や安心感といった生活の利便性に直結している。到着時間や料金が事前にわかることから、移動にともなう心理的負担も軽減され、特に仕事帰りや急ぎの移動において大きな安心感をもたらしている。
しかし、この利便性が地方まで均等に浸透しているわけではない。地方では、スマートフォンの普及率が都市部より低く、高齢者の比率が高いため、アプリ操作自体が心理的な障壁になりやすい。また、タクシー自体の配置密度が低く、必要なときにすぐ利用できない地域も少なくない。利用者にとって、呼んでも到着まで時間がかかる、あるいは利用方法がわかりにくいといった不便感が日常的に存在する。
こうした環境下では、住民が移動手段として車やバスに頼らざるを得ず、自由に選べる移動の幅が制限されてしまう。都市と地方の間には、単に技術の差だけでなく、生活習慣や地域の交通文化の違いも含めた「移動の格差」が生まれている。便利さの裏側に潜むこうした課題を踏まえ、現状とリスク、そして可能性を明らかにする必要がある。
ICT総研の調査によると、2024年末時点でタクシー配車アプリの利用者数は約1664万人に達している。都市部では通勤や買い物、外出先での移動など、日常生活のさまざまな場面でアプリが使われており、時間の節約や心理的な安心感に直結している。到着時間や料金が事前に明示されることは、利用者が移動の計画を立てやすくするだけでなく、初めて訪れる土地でも安心してタクシーを選べる環境を作っている。
タクシーの車両数は、業界構造の変遷を映す指標でもある。法人車両は20万3,943台、個人タクシーは3万9304台を含めた総車両数は24万3247台(国土交通省・2013年3月末現在)である。コロナ禍以降は多少回復しているが、2007年度のピーク時(26.7万台)から15年間で約10%減少している。こうした市場縮小のなかで、配車アプリは都市部のタクシー利用を活性化する刺激剤として機能している。
利用者層を見ると、アプリを「利用したことがある」と回答した人は東京都で16.2%と最も高く、京都府13.9%、大阪府12.6%と続く。年齢層は20~40代に偏っており、若年層は利便性やキャッシュレス決済への適応力、中年層は時間効率の高さを評価して利用する傾向がある。都市部のタクシー会社にとって、アプリ経由の予約増は空車巡回の無駄を減らし、運行効率やドライバーの負担軽減にもつながっている。
技術面では、
・GPS追跡
・到着時間表示
・キャッシュレス決済
・事前運賃
が標準化しつつある。加えて、AIやビッグデータを活用した需給予測や最適配車の導入も進み、運行効率や利用者満足度の向上に一定の成果を上げている。しかし、この刺激だけでタクシー市場全体の健全化や地方部の課題解決までを担うことは難しく、構造的課題は依然として残る。
■地方タクシーに立ちはだかる壁
タクシー配車アプリを「利用したことがある」と回答した人にどのアプリを利用したかを聞くと、トップ5の都府県すべてで「GO」が首位となった。東京都と愛知県では、2位との差がそれぞれ30ポイント以上あり、都市部での利用集中がうかがえる。しかし、地方ではアプリの利用が日常生活に浸透しているとはいいがたい。
地方では、デジタルインフラと高齢化という「二重の壁」が存在する。スマートフォンやインターネットに慣れていない高齢者が多く、アプリ操作自体が心理的な障壁となる。また、アプリ対応タクシーの配置密度が低く、呼んでも到着まで時間がかかる場合があるため、利用をあきらめる住民も少なくない。地域住民にとって、タクシーは特別な場合にしか使わない移動手段であり、日常的な利用習慣が形成されにくい。
タクシー会社にとっても、アプリ導入や運用コスト、手数料負担は大きく、特に地方の小規模事業者にとってハードルは高い。導入しても、地域の利用者が少なければ十分な収益につながらず、事業者は投資のリスクを懸念する。また、配車アプリに依存しすぎると、自社の集客力や価格交渉力が制限され、地域交通の自律性が損なわれる可能性もある。
さらに、地方では
・ドライバー不足
・燃料高騰
・保険料上昇
などの外部圧力も重なる。
※以下出典先で
引用元: ・タクシー配車アプリが「地方」を見捨てる? アプリ依存で高齢者&地域交通が取り残される辛らつ現実 [七波羅探題★]