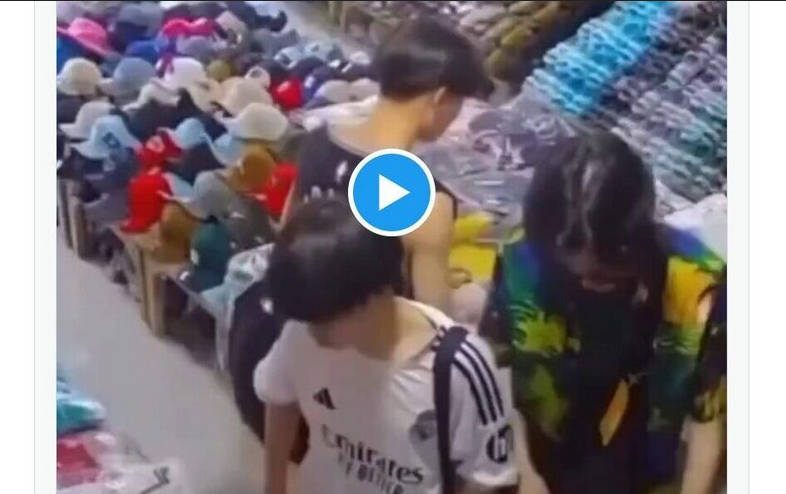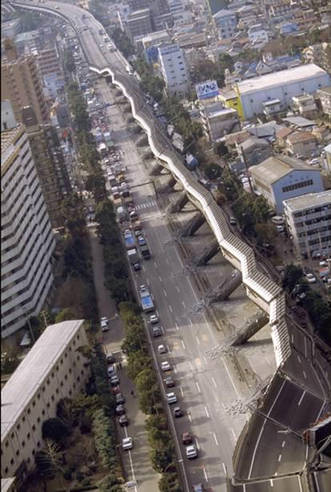火蓋を切ったのは米テスラのEVだが、現在は中国最大手BYDが「ガソリン車より安い」PHV(プラグインハイブリッド車)を投入し、市場は赤字消耗戦の様相を呈している。
この中国市場の価格破壊を主導し、日系メーカーを苦しめる「激安PHV」が、2026年にも日本市場へ投入される予定だ。
本稿では、湯進氏の著書『2040 中国自動車が世界を席巻する日』(日本経済新聞出版)より、価格競争の背後にある市場構造の変化と、EV・PHVの可能性をみていく。
新車需要低迷の巻き返しを図るべく、中国で激化する「価格競争」
中国政府が自動車消費の喚起やNEV市場の育成を図るために実施したNEV購入補助金制度の優遇期限は、2022年末までであった。
2023年に入っても新車需要の低迷は続いており、新車市場で「巻」と呼ばれる過熱した価格競争が起こっている。
価格競争のはじまりは「テスラ」から
値下げ競争は、テスラが2023年1月に発表した価格改定に端を発する。
テスラ上海工場の年産能力は約100万台、自動車部品の国産化率も95%に達した。
生産規模の拡大によるスケールメリットによって、他社よりも高い利益率を維持するテスラには、車両価格をさらに下げる余地が残っている。
生産の規模が小さいメーカーにとっては大きな脅威となる。
これを機にBYDは「油電同価(ガソリン車と電動車が同じ価格)」というキャッチコピーを掲げ、2023年2月に発売したPHV「秦PLUSDM-i」の低グレード車を10万元以下の価格で販売している。
またNIOなど新興勢をはじめ、トヨタやVWなど大手の中国合弁も相次いで価格を引き下げ、中国EV市場に価格競争の波が押し寄せた。
電動車で起きた価格競争がガソリン車にも飛び火した格好だ。
東風汽車や第一汽車など大手自動車グループも追随し、地方政府と一体となって補助金の支給など大規模な消費促進の措置を相次いで打ち出した。
こうした価格競争は新車市場の低迷に加え、電池材料価格の下落や排ガス規制の新基準の実施、メーカー各社が余剰在庫の削減を急ごうとしたことにより生じた。
なかでも車載電池の主要部材である炭酸リチウムの価格は、2020年から高騰が続いていた。
安定的な価格で電池を調達するため、完成車メーカーはサプライチェーンの上流へ勢力圏を広げるべく動いてきた。
これによって電池原材料の需給が緩み、2022年末には炭酸リチウム価格が下落に転じた。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/858a601513dcd67900fa98bac824f46e7201e6d8
引用元: ・【中国】〈カローラより約100万円安い〉衝撃価格。中国自動車市場を価格破壊した“激安PHV”が2026年日本上陸…「もう競争力を維持できない」日系メーカーの悲鳴
家電みたくどんどん浸食可能な業界でもあんな
電気は無理よ。
壊れやすすぎる