
【超朗報!】自民爆勝【高市早苗・自民単独300議席】
1: リトナビル(東京都) [US] 2026/02/05(木) 12:04:08.85 ID:ZHPQJNHI0 BE:718678614-2BP(1500) sssp://img.5ch.net/ico/anime_ […]
2026-2-5
2025-10-23


1: リトナビル(東京都) [US] 2026/02/05(木) 12:04:08.85 ID:ZHPQJNHI0 BE:718678614-2BP(1500) sssp://img.5ch.net/ico/anime_ […]
2026-2-5

1: どどん ★ 2026/02/04(水) 19:02:35.37 ID:HnK8wxBW9 東北放送 4日午後0時頃、仙台市太白区の八木山橋の下で、警察が女性の遺体を発見しました。 遺体は、2日から行方不明になってい […]
2026-2-4

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 09:58:06.61 ID:QxCz1uBp0 日米欧、レアアース安定供給へ「貿易圏」 最低価格制で中国製を排除 ワシントン=八十島綾平】トランプ米政権は4日、日本 […]
2026-2-5

1: ばーど ★ 2026/02/05(木) 12:09:06.77 ID:mbdyeC7M 日本が南鳥島沖の海底からレアアースを含む泥の採取に成功したことに対する中国外交部のコメントが、中国で話題になっている。 3日の […]
2026-2-5

1: メシル酸ネルフィナビル(みかか) [US] 2026/02/05(木) 16:43:45.52 ID:dCzhnOxC0● BE:565421181-PLT(13000) sssp://img.5ch.net/ic […]
2026-2-5
記事は、国際協力機構(JICA)が進めていたアフリカ諸国との交流を深める「ホームタウン」事業について、SNSで「移民を大量に受け入れる」などの誤情報が拡散し、撤回に追い込まれたことを紹介。「この出来事は、近年日本で高まりを見せる排外的な世論の一端を示している」と論じ、政界においても「日本人ファースト」を掲げる参政党が存在感を高め、自民党総裁の高市早苗氏が外国人問題に言及していることを伝えた。
その上で、「日本国内で排外的な感情が強まっていることは、さまざまな側面で顕著に見られる」とし、日本のマスコミの報道について「外国人が関わる犯罪や交通事故などのニュースを過度に取り上げ、誇張する傾向がある。それによって一般市民の間で外国人への不信感が高まっている」と苦言を呈した。
また、「こうした排外感情は現在の経済状況や生活への不満と結び付けられ、多くの国民は『物価の高騰は外国人によって引き起こされている』と考えるようになっている」「SNS上では、『日本政府が外国人に対して奨学金や社会保障の面で優遇措置を与えている』といった根拠のない情報が拡散し、国民の不満を一層あおっている」とも言及。「世論の高まりを受け、日本政府も在日外国人の上限について議論を開始し、不動産取引や経営・管理ビザに関して制限をかける案を打ち出している」と伝えた。
一方で、記事は「日本が直面している最も切実な矛盾は、経済と社会の運営が高度に外国人に依存しているという点にある」と指摘。少子高齢化による労働力不足が年々深刻化し、20~30代を中心とした外国人労働者は230万人を超え、2008年比で4.7倍に急増したことに触れた上で、「日本の経済学者の間では、外国人労働者の受け入れは日本国内の経済・社会構造上の問題を緩和する有効な手段であるとの見方が一般的だ。若い外国人労働力は人手不足を補うだけでなく、税金や社会保険料を相当額納めることで日本経済を下支えしているのである」と論じた。
そして、「建設、介護、農業など労働力不足が顕著な分野で重要な役割を果たす彼らがいなければ、日本の多くの基幹産業は立ち行かなくなり、国民の日常生活にも支障をきたす。たとえば農業では、農家の高齢化が進む中、若い技能実習生など外国人労働者が現場作業を支える主力となっている。家屋の解体作業なども、ほとんど外国人労働者が担っている」などと伝えた。
記事は、外国人を標的にした根拠のない誤情報が出回り、日本政府もそうした「外国人優遇論」の打ち消しに積極的に取り組んでいると説明。「厚生労働省によると、生活保護を受給している約164万世帯のうち、外国人が世帯主である割合は約2.9%。これは日本の総人口に占める外国人の割合とほぼ同水準である」としたほか、「外国人が日本人の賃金を押し下げている」という見方についても、「日本で働く外国人の平均月収は約24万円で、日本人の平均月収(33万円)を大きく下回っている。
(略)
さらに、外国人犯罪についても「国立社会保障・人口問題研究所のデータによると、過去30年間で在日外国人の総数は130万人から370万人以上に急増したが、刑法犯として検挙された外国人数はむしろ減少傾向にある」とし、日本の市民らの声として「外国人は私たち日本人がやりたがらない多くの仕事を担ってくれている。彼らは私たちの生活に欠かせない存在で、排斥するなんて許せない」「社会のあらゆる問題を『外国人のせい』にしているだけ」などを紹介した。
そして、「経済的には外国人労働力に依存しているにもかかわらず、外国人への受容度は経済的必要性に見合う水準には達していない。このギャップは、『日本人ファースト』という意識と現実との間で揺れ動く日本の葛藤を如実に示している」と指摘。日本経済新聞社とテレビ東京が実施した世論調査で、「外国人の受け入れを拡大すべき」と答えた人が45%、「拡大すべきでない」と答えた人が46%で賛否が拮抗したことを挙げ、「日本社会がこの問題をめぐって深く分断されていることを示す結果となった」と論じた。
記事は、「経済的には外国人を受け入れつつ、文化的には多様性を尊重する包容的社会を築けるかどうかが日本の課題。もしこの両立に失敗すれば、『人口減少』と『排外主義』という負のスパイラルに日本はさらに深く沈み込むことになるだろう」とし、「外国人が来ると面倒が増えるからと拒むなら、日本は確実に衰退の道をたどる」と主張した。(翻訳・編集/北田)
引用元: ・日本で突然、排外感情が高まったのはなぜか―中国メディア [10/23] [昆虫図鑑★]
むしろ、マスゴミが伏せてた節があるが?

1: プロストラチン(大阪府) [EC] 2026/02/05(木) 21:42:09.67 ID:N1k5Y79B0 BE:595582602-2BP(5555) sssp://img.5ch.net/ico/anim […]
2026-2-5

1: プロストラチン(みょ) [US] 2026/02/05(木) 21:52:46.95 ID:wJRxhtkB0 BE:595582602-2BP(5555) sssp://img.5ch.net/ico/anime […]
2026-2-5

1: ファムシクロビル(やわらか銀行) [US] 2026/02/05(木) 22:03:15.77 ID:hGVbl5zn0 BE:478973293-2BP(2001) sssp://img.5ch.net/ico/ […]
2026-2-5

1: テノホビル(東京都) [CN] 2026/02/05(木) 22:52:33.55 ID:ba9IpZmz0● BE:237216734-2BP(3000) sssp://img.5ch.net/ico/tona1 […]
2026-2-5

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 23:03:46.07 ID:xLCS7BNe0 ソースはニンダイ まさかの全12タイトル収録wwwwwwwwwww https://news.denfaminico […]
2026-2-5

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 22:24:24.95 ID:3ccajb1W0 参政党の神谷宗幣代表がSNSでの発信が広がらないことに違和感を訴えているそうです。 そこで、2025年の参議院選挙の […]
2026-2-5
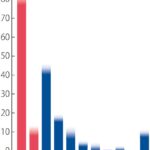
1: 影のたけし軍団 ★ 2026/02/05(木) 22:23:56.85 ID:??? TID:gundan 読売新聞社が3~5日に実施した衆院選の終盤情勢調査では、比例選(定数176)でも自民党が勢いを増しており、 […]
2026-2-5

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 21:24:29.04 ID:PCq86WWg0 https://socialcounts.org/youtube-video-live-view-count/yLx […]
2026-2-5

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 21:47:51.67 ID:lPq6mYHm0 やったぜ 引用元: ・【画像】国産レアアース、ガチで確保wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww […]
2026-2-5

1: それでも動く名無し 2026/02/05(木) 22:46:56.32 ID:7s3Lo4/H0 ヤバ😭 引用元: ・【画像】高市早苗のパンフ、怖すぎるWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
2026-2-5
PAGE TOP