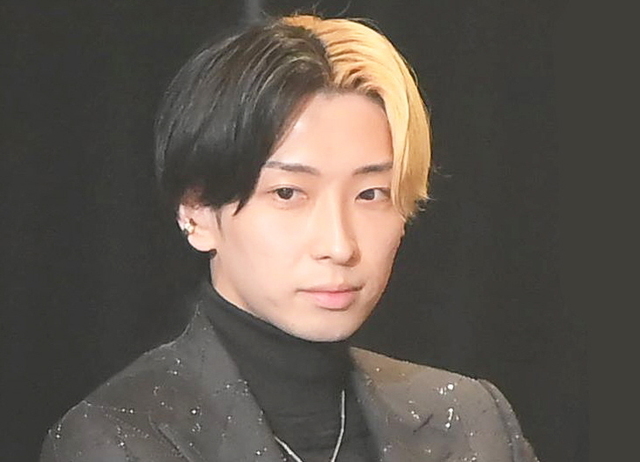フォロワー約180万人を持つ微博アカウント「風雲学会陳経」氏は18日、日本のレアアース戦略の動向について紹介する書き込みを行った。
同氏はまず、日本が2010年の尖閣諸島沖衝突事件で中国がレアアースの対日輸出を一時停止したことに強い危機感を覚え、中国へのレアアース依存脱却を国家戦略に位置づけて以来官民一体で供給網の多様化や代替技術の確立を進めてきたと紹介した。
その上で、15年に及ぶ取り組みの成果として、レアアース使用量を減らすための技術の普及を挙げ、家電向け磁石ではジスプロシウムの使用量が10年比で7割減り、トヨタやホンダはモーターに粒界拡散技術を導入してネオジム使用量を3~5割削減したと紹介。完全な「脱レアアース」ではないものの、必要量を大幅に減らした点は実用的成果と言えると評した。
また、日本はレアアースのリサイクルにも力を入れ、ホンダが廃棄ニッケル水素電池から約8割のレアアースを再利用することに成功し、三菱マテリアルも高純度回収で「戦略的保険」を確保していると指摘。リサイクルによるレアアース調達のコストは輸入品の数倍に上るものの、供給途絶時の備えとして一定の意味を持つとした。さらに、国家備蓄も拡充し、60日分だった戦略在庫を180日分超に引き上げ、23年以降はジスプロシウムやテルビウムなど重希土類の追加備蓄を進めていると伝えた。
さらに、輸入構成も変化しており、豪州ライナス社からの軽希土類調達が奏功して09年に93%を占めた対中依存度は24年に58%まで低下したと紹介。一方で重希土類の供給は依然として中国が握り根本的な脱依存には至っていないとし、日本国内でも南鳥島沖の海底泥試掘など新資源開発が試みられているものの、実用化は30年以降とみられると説明した。
同氏は、重希土類の採掘・精製には高度なノウハウと長年の積層技術が必要で、西側諸国が短期で中国依存を断つのは容易でないと指摘。日本の取り組みは「全面脱中国」ではなく、「リスク分散」としての自立化でバランスを取る段階にあると言えると評した。(編集・翻訳/川尻)
引用元: ・日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている?―中国ネット [662593167]
おとなしく中国へ依存するアル😠
いやー輸出してくれないから依存しようがないんだよなぁー
よって頓挫