
東急自動車学校(多摩市)の四輪教習コースで開催
競技車両は、常時3輪以上が接地して静止時に自立する構造で、走行時に車体が傾斜する構造の場合は最大傾斜の状態でも自立が保たれること
実行委員会が用意する市販バッテリ2個(12V/3Ah以下)を使用する
車両に搭載できるバッテリは1個のみ
モーターに制限はない
市販車両を無改造で利用することは認めない
車両の意匠も評価対象
安全規定あり
引用元: ・日産エコワン 生産技術が参戦するも今時「抵抗制御」で中高生に大敗 内外装の高級感で差別化を図る [618719777]
以下、記事を抜粋
2025年大会には高等専門学校からの参加はなく、18校が参加。
毎年ボランティアとして大会運営に参加している日産のスタッフもチームを結成。
車両生産技術開発本部の若手社員が中心となり、1年をかけて手作りBEVマシン「R36 GTR」を製作。
表彰対象外の参考出走という扱いながら「チーム日産・生産技術開発」としてエントリーし、計19チームがコース走行を行なった。https://asset.watch.impress.co.jp/img/car/docs/2041/330/001_l.jpg
初参戦した「チーム日産・生産技術開発」の手作りBEVマシン「R36 GTR」
R36 GTRの外装は素材にプラ段(プラスチックダンボール)を使いフィルムコートを貼り付けて高級感を演出。
フロントノーズに3Dプリンターで製作した日産エンブレムを装着。
車体のフレームはアルミ構造材を使用。パイプ同士を組み合わせる段階で使用したジョイントが鋳鉄製で重量増の要因になってしまい、次回は溶接構造にしたいと意気込みが語られた。
車内で乗員が足を置くフロアパネルにはCFRP(炭素繊維強化プラスチック)が使われている。 「R36 GTR」は最高速60km/hを想定。バッテリ2個を直列にした24Vをスーパーキャパシタで48Vまで昇圧、電動車いす向けのモーターなどを生産しているコアレスモーターに生産を委託したインホイールモーターに送って強力な加速力を生み出し、制動時には回生発電を行なって高効率化を図ろうと計画していた。
しかし、実際に設計を進めるとユニットが大きく重量増の要因になり、回生発電で想定していたパーツの入手が間に合わず、モーターを抵抗で制御するシンプルな設計に変更して本番に臨んでいる。
(引用者が高校生の時には、サイリスタでDCをチョッパ制御、転流させて回生ブレーキも実装させました。三十年ほど前の話。エコラン出場経験あり)
また、初参戦となる今回はなによりも10周完走を目標として設定し、平均タイム2分45秒で完走を実現。バッテリ残量にはまだ数周できそうな余裕が残っていたが、一方で学生たちのチームでは、トップクラスになるとラップタイムが自分たちの半分以下というスピードを見せながらしっかりと完走しており、非常に高度なマシン作りをしていることに驚かされたという。https://asset.watch.impress.co.jp/img/car/docs/2041/330/065_l.jpg
1位の金賞に輝いた「長野県松本工業高等学校 松本工業高校 原動機部」
表彰された中高生
https://i.imgur.com/awBEzRx.jpeg
https://i.imgur.com/mIdOVX4.jpeg
っていってもその時代には既にFETによる電圧制御も出ていたな






_618650.jpg)

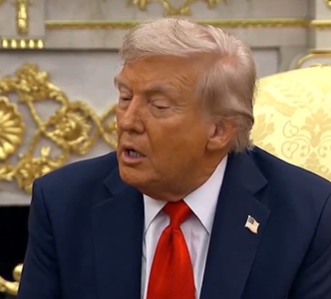

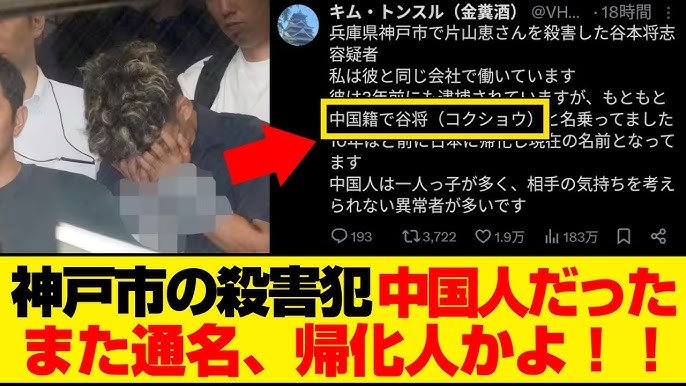
コメント