最大の障壁は為替だ。車両価格に直接影響するため、消費者の購買意欲に直結する。現在(2025年7月)の為替レートは「1ドル = 147円前後」で推移しており、円安が続いている。米国から車両を輸入・販売する場合、この為替水準では価格競争力が著しく劣る。
・輸送費
・型式認証
などの付帯コストを加味すると、米国内で3万ドルの車両は日本では530万円程度になる。これは同セグメントの国産車と比較して割高だ。仮に120円まで円高が進めば、同じ車両は100万円近く価格を抑えられ、販売現場での選択肢として現実味を帯びる。
一方で、米国内の製造原価は上昇傾向が続いている。労務費や原材料コストの上昇が背景にある。輸入される米国製トヨタ車の価格が、国内市場でのトヨタ既存モデルと正面から競合できる水準に達するかは不透明であり、ここが事業成立の可否を左右する分水嶺となる。
仕様や法規対応も大きな障壁となっている。米国車は左ハンドル仕様が基本であり、日本市場に対応させるには右ハンドルへの変更が求められる。これはステアリングやミラー位置の調整だけでなく、車体設計の根本的な変更とそれにともなう生産設備の改修を必要とする。コストは決して小さくない。左ハンドルのまま導入することも不可能ではないが、国内ユーザーの一定層にとっては受け入れが難しい。
加えて、日本の独自保安基準への適合も必須だ。
・ウィンカーの色
・灯火類の光度
・排ガスや騒音の制限
などに対応するには、設計変更や各種試験の実施が不可欠であり、その費用は軽視できない。販売台数が限られるうちは、こうしたコストは単価を押し上げ、採算性を圧迫する。政府が検討する安全基準の簡素化によって、どこまで要件が緩和されるかが、今後の焦点となる。
さらに、アフターサービス体制の未整備も深刻な課題だ。部品の安定供給体制を構築するためには、パーツやアクセサリーの物流網を再構築し、在庫管理も含めた仕組みを整える必要がある。また、全国の販売店で対応できる整備士を育成しなければならない。米国車は国産車とは構造や仕様が異なるため、教育・訓練の水準も高く求められる。こうしたサービス体制が不十分なまま販売を拡大すれば、顧客満足度は著しく低下し、ブランドイメージを損なう恐れがある。
輸入販売の実現には、為替の安定・製造コストの抑制、設計と規制対応、そしてアフター体制の整備という複合的な条件がそろわなければならない。各課題への対応を一つずつ着実に進めなければ、市場への浸透は難しい。
価格面の障壁を乗り越えるには、為替要因に加え、輸送費や保険料、車両登録といった諸費用の見直しが不可欠だ。こうした輸入関連コストの圧縮が、今後の焦点となる。
政府による政策支援が導入されれば、採算改善の突破口となる可能性がある。低炭素車や輸入車に限定した購入補助金の導入に加え、重量税や取得税への特例措置が講じられれば、米国車の価格競争力は大きく向上する。
これらの支援策は、トヨタ単体の利益追求にとどまらない。消費者の選択肢を拡大し、国内市場の競争を活性化させる公益性がある。さらに、米政権に対して約束した市場開放の実効性を示す政策としても評価されるだろう。
詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/889d04dc87ad876e4854e8707af5616ed67c24b8
引用元: ・【自動車】トヨタ豊田会長が挑む「米国生産車の輸入」どうなる?──制度・経済・技術の壁と突破シナリオを考える
どうすんのこれ


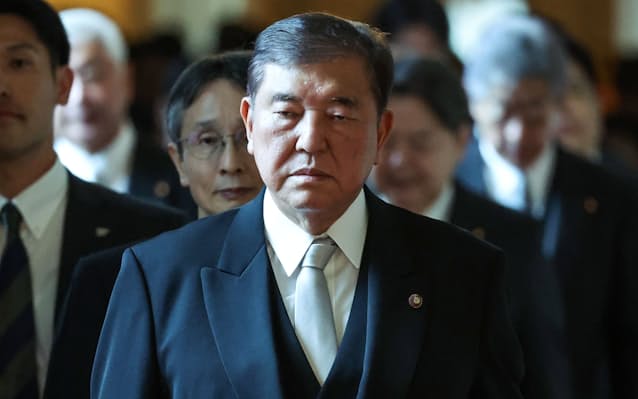

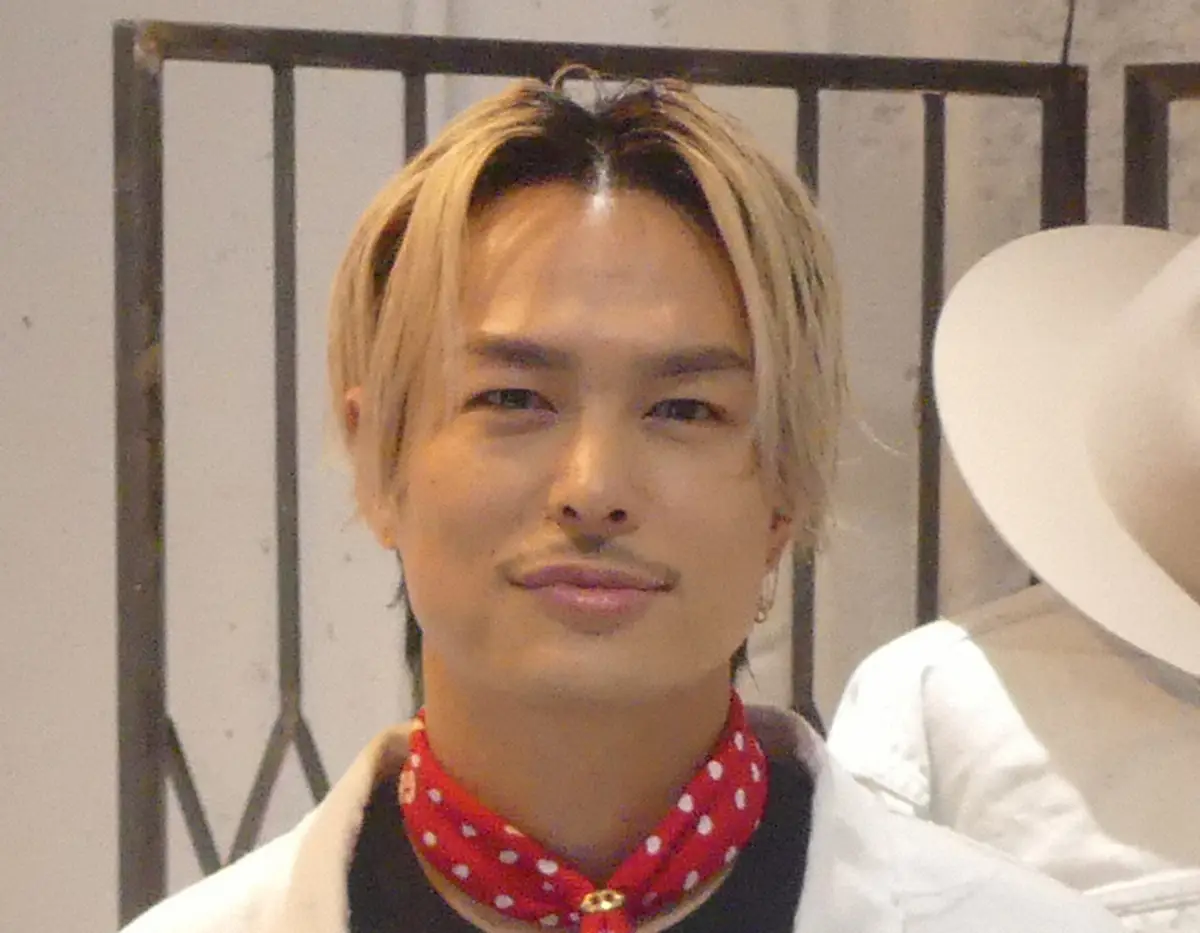

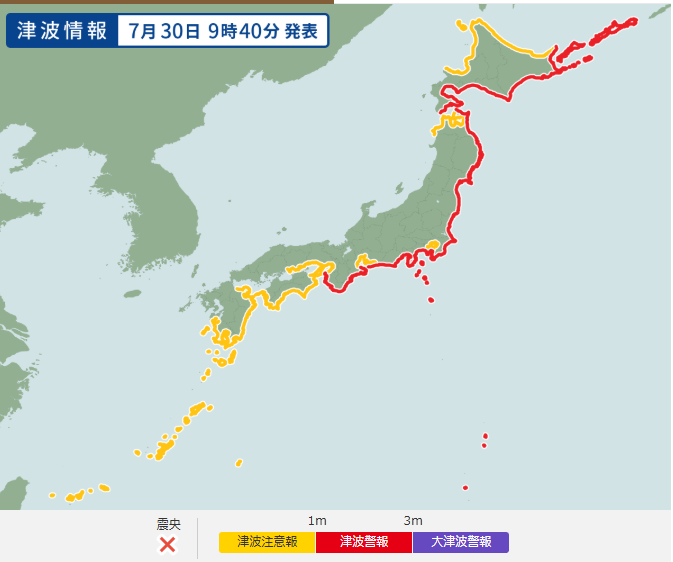





コメント