これまでも中国発のニュースやSNSでは、無人配送車の動向や、「これだけ走っている」という情報がたびたび報じられてきた。車両の発表やサービスがスタートするときこそ華々しく紹介されるが、いざ運用が始まると、道路工事中大きな穴に落ちたり、スピードバンプに引っかかって動けなくなtたり、車に衝突してそのまま走り去ったり、倒れた二輪車を認識せず引きずって走行したり、二台の無人配送車が道を譲り合って動かず道を塞ぐといった、面白ニュースばかりが出回るようになった。こうした事件はホテル内の荷物配送ロボットなどにも通じるものがある。
とはいえ、無人配送車を実際見たことがある人がどれだけいるかを考えると、運用されている都市や地域は限定されていて、「普及している」とはとても言い難い状況だった。なぜ普及していないかというと、車両の値段が高いのと、各地方政府の道路走行許可がそれほどされなかったからだ。逆に現在普及が進みそうというのは、この双方の問題が解決しつつある。
中国における無人配送車の主要企業としては、新石器(Neolix)、九識智能(ZELOS)、白犀牛(WHITE RHINO)という3社に加え、大企業ではアリババの物流企業の菜鳥(CAINIAO)も加わっている。
5月には九識智能は製品価格が2万元(約40万円)を切る、積載量500kgの初の戦略モデルE6を発売し、続いて新石器が積載容積6立方メートル、積載量1000kg、航続距離200kmのモデルXを頭金888元(約1万8000円)で購入可能だと発表。
6月18日に菜鳥は2万1800元(約44万円)の新型自動運転車「Cainiao GT-Lite」を発売し、さらに期間限定で5000元(約10万円)割引きの1万6800元(約34万円)での販売を開始した。1台40万円を切る激安価格で無人配送車が買えるようになったのだ。
(略)
無人配送車の普及を後押ししているのが、中国政府の政策だ。2024年11月には、2027年までに社会全体の物流コストの対GDP比を約13.5%まで削減することを目標とする、「社会全体の物流コストを効果的に削減するための行動計画」を発表している。その施策の一環として、ドローンや、ロボットが稼働する無人倉庫に加えて、無人配送車の活用が推奨されている。具体的には、宅配会社の都市内拠点からマンション団地内の配送ステーションまでの数キロの区間を無人配送車で結ぶことで人材不足の解決を目指している。
以下全文はソース先で
36Kr Japan 2025年7月28日
https://36kr.jp/357050/

引用元: ・中国の無人配送車、1台40万円弱の衝撃 政策・低価格で2027年に大衆化へ [7/28] [ばーど★]
中国は人間だけが多いのが取り柄なのに無職を増やしまくるだけだろ

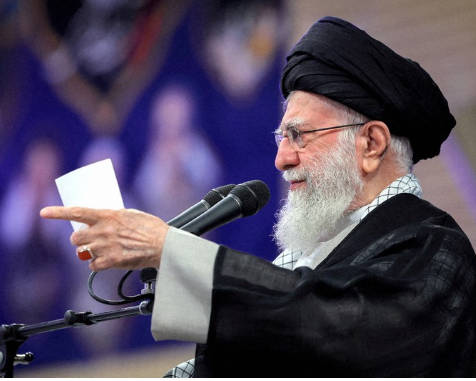



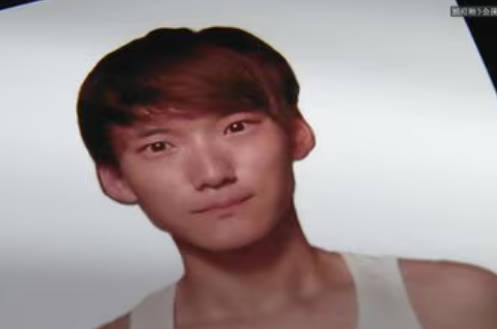







コメント