この不思議な呼び名は、もともとロシア発祥の概念ですが、中国では短編動画やSNSを通じて急速に浸透し、今では「仏系」「寝そべり族(寝そべり)」に続く新たな“ネガティブ文化”の象徴として注目を集めています。
「ラット・ピープル」とは、昼夜逆転の生活を送り、外の世界との関わりを最小限に抑え、自室にこもって日々を過ごす若者たちのことです。
深夜2時に眠り、朝10時に目覚めた後はベッドで延々とスマホをいじり、デリバリーの食事を取ってまた昼寝をします。
目が覚めれば、ゲームやSNSに再び没頭し、夜更かしを繰り返します。1日のほとんどをベッドの上で過ごし、部屋を出るのはゴミ出しや宅配の受け取りくらいです。
現実の人間関係はほぼ途絶え、生活の中心はデジタル空間へと完全に移っています。
こうした生活は、学生だけに限らず、卒業間近の大学生や社会人の間にも広がっています。たとえば、武漢に暮らす28歳の女性・趙雨晴さん(仮名)は、「どうせ外に出たって変わりません。人生に期待なんて持ってない。無理に動くより家で静かにしていた方が気楽です」と語ります。
外出の基準は、部屋にゴミが溜まったかどうかです。何もなければ、一日中カーテンも開けずに部屋にこもるのが日常だといいます。
安徽省の大学に通う20歳の尹浩さんも、1年以上にわたって「ラット・ピープル」のような生活を続けてきました。
入学当初は、授業にも積極的に参加し、図書館にこもって、熱心に勉強していました。しかし、就職を意識し始めた頃から、「家庭も地元も、自分の未来を支えてはくれない」と痛感しました。
地方出身であること、実家に経済的な余裕がないことが、「努力しても報われない」という無力感を生み出し、気がつけば夜更かしとゲーム中心の生活にのめり込んでいました。「もう戻れない」とつぶやきます。
中国のSNSでは、「#低エネルギーのラット・ピープル(老鼠人)」といったハッシュタグが数十億回閲覧され、若者たちは「朝11時半起床→デリバリーで昼食→昼寝→ミルクティー→ペットと遊ぶ→またベッドへ戻る」といった日課を淡々と投稿しています。
「こんなに怠けていていいのか」と自嘲しつつ、どこか安心感を求めているようにも見えます。
この現象の背景には、中国の深刻な経済状況があります。2025年、中国では大学卒業生が過去最多の1220万人に達しました。一方で、16~24歳の若年層の失業率は15%以上という高水準が続いており、就職は熾烈な競争となりました。
「頑張っても報われないなら、最初から頑張らない方が楽」と感じる若者も少なくありません。
重慶市の心理カウンセラー・譚剛強氏は、「寝そべり族」は疲れや収入への不満から一時的に立ち止まる姿勢だが、「ラット・ピープル」は社会との接点自体を断ち切り、より深い孤立にあると指摘します。
「真面目に生きても変わらない」と感じた若者たちが、静かに、そして確実に、自室へと退いていくのです。
しかし、「ラット・ピープル」は単なる怠惰や逃避ではなく、むしろ今の社会構造そのものへの静かな抵抗とも言えるかもしれません。
学歴インフレ、雇用不安、長時間労働文化(いわゆる「996」)といった過酷な現実が、心の奥底で反発を生んでいるのです。
SNS上では、自らを「鼠族」と名乗りながら、「自分を変えたい」と揺れ動く感情や小さな希望を共有する姿も見られます。
ある専門家は、「これは単なる社会的撤退ではなく、自分にとって本当の幸せとは何かを見つめ直す過程」だと話します。実際、経済的にある程度の余裕を持つ30代の社会人が、自発的に競争から離脱して「ラット・ピープル的」生活を選ぶケースも増えており、それは一時的な心の休憩とも言えるでしょう。
とはいえ、長期間このような生活が続けば、心身への悪影響も無視できません。孤独感や自己否定感、昼夜逆転による生活リズムの乱れは、さらに深い負のループを引き起こす可能性があります。
もし「このままではいけない」と思えたなら、まずはスマホから1時間だけ離れてみる、小さな目標を立ててみる、軽く散歩に出るといった、些細な一歩から始めてみるのがいいかもしれません。
https://www.visiontimesjp.com/?p=49823
https://www.youtube.com/watch?v=s7lCdK8s1Mc
引用元: ・【寝そべり族より絶望的?】中国で広がるラット・ピープル(老鼠人) 昼夜逆転の生活を送り、外の世界との関わりを最小限に抑え、自室にこもって日々を過ごす若者たち
それにしてもデリバリー頼む金は親の脛齧りか?
-昼夜逆転の生活を送り、外の世界との関わりを最小限に抑え、自室にこもって日々を過ごす若者たち_585430.jpeg)



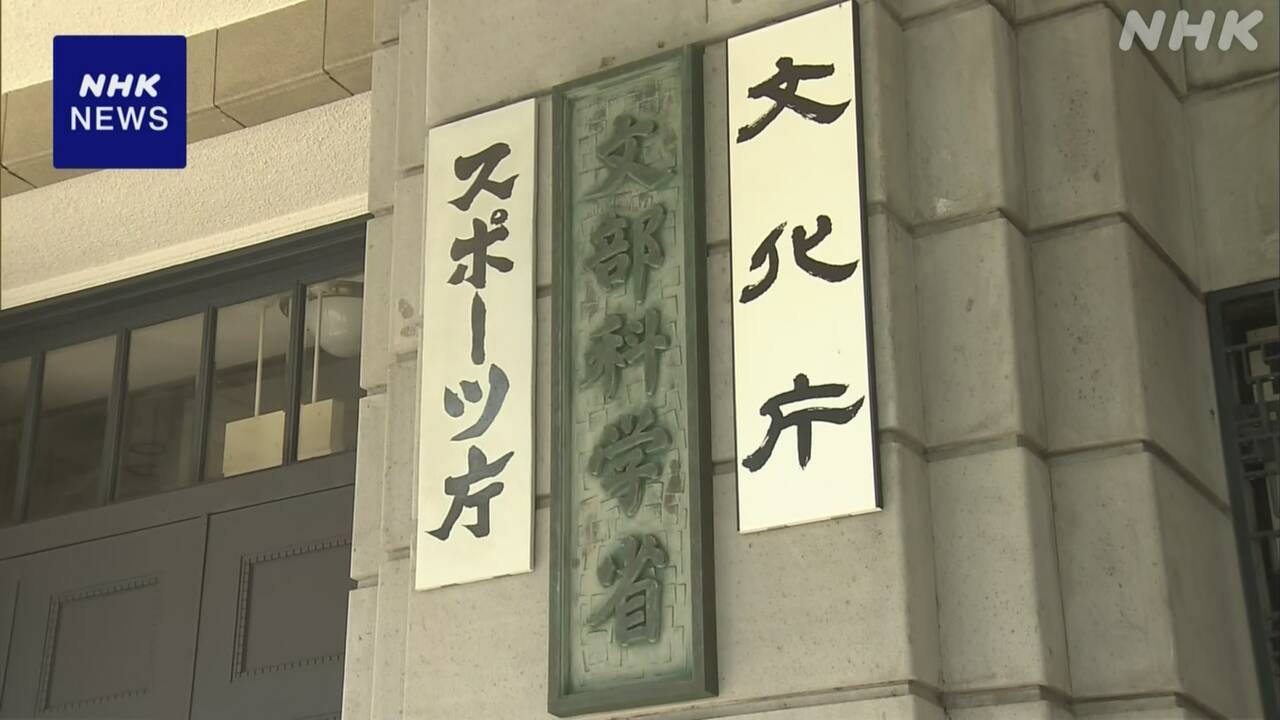





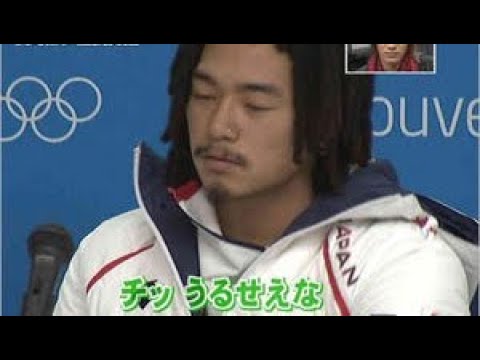

コメント