7/12(土) 12:12 文春オンライン(※抜粋)

翌2024年10月には、327カットのリテイクと再ダビングが施された『真生版』が公開され、累計興行収入30億円、累計観客動員数208万人を突破するロングラン・ヒットとなった。
時は昭和31年。帝国血液銀行に勤める水木は、日本の政財界を牛耳っている龍賀一族が支配する哭倉村へ向かう。彼はそこで、行方不明の妻を捜す謎の男・ゲゲ郎と遭遇。村に渦巻く恐ろしい因習とおぞましい妖怪が跋扈するなか、2人はそれぞれの目的のため協力することになる。
「妖怪 vs. 人間」という従来のバトルものとは一線を画し、かつてないほど不穏なムードに包まれた『ゲ謎』。なぜこれほどのブームを巻き起こしたのか、本稿ではその理由を考察していこう。
■“大人向け”に原点回帰して大ヒット
Filmarks For Marketingのデータによると、観客の男女比はほぼ半々で、20代から40代を中心に幅広い世代から支持されている(>>1)。これは非常に興味深い事実だ。
なぜなら、TVアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』第6期シリーズ(2018?2020年)は、日曜朝9時?9時30分放送という、明らかなファミリー向けコンテンツだったからだ(このシリーズが、社会的テーマを含んだ、大人の鑑賞にも耐えうる内容だったことは事実だが)。
通常であれば劇場版もファミリー層をターゲットにするはずだが、『ゲ謎』は大胆にもPG12指定(『真生版』はR15+)に振り切っている。TVシリーズのファンに媚びることなく、大人向けのミステリーホラーとして徹底的に作り込んだことが、新たなファン層の獲得に繋がった。
思えば、貸本時代の妖怪漫画『墓場鬼太郎』は、人間の業や社会の暗部を深く描いた大人向けの怪奇譚だった。そう考えると、『ゲ謎』は水木しげるのオリジナルのスピリットに回帰した作品ともいえる。
それは、モンキー・パンチの『ルパン三世』が、テレビアニメ第2シリーズで子供向けの痛快娯楽路線に舵を切り、近年再び大人向けのハードボイルド路線へと回帰した流れとも似ている。
本作は、国民的IPをリブランディング/原点回帰することで、新しい可能性を押し広げたのだ。
■『ゲゲゲの謎』と『犬神家の一族』の共通点
『ゲ謎』のストーリーの大枠は、横溝正史の『犬神家の一族』と同じ。名探偵・金田一耕助が活躍するこの作品は、監督・市川崑、主演・石坂浩二による1976年公開の映画を筆頭に、古谷一行バージョン、片岡鶴太郎バージョン、稲垣吾郎バージョン、池松壮亮バージョンが作られるほど、映画・テレビで繰り返しリメイクされてきた。
信州財界の巨人・犬神佐兵衛翁が莫大な遺産を残して死去。その遺言を巡って、凄惨な連続殺人が発生する。金田一耕助は、複雑に絡み合う血縁、因習、そして愛憎が渦巻く旧家の闇へと分け入り、おぞましい真実に迫っていく。ある種のパロディと言って差し支えないほど、基本構造が酷似しているのだ。
具体的に例を挙げるなら、(1)閉鎖的な共同体での連続殺人事件、(2)醜い遺産争い、(3)血の因習、(4)異形なるもの(『犬神家の一族』であれば湖に逆さまに突き刺さった足や、ゴムマスクを被った佐清)、(5)招かれざる探偵、などなど。どちらも、「閉鎖的な空間に外部からやってきた人物が、事件の謎を追うなかで、一族の秘密や闇に触れていく」という構図だ。
もはやこれは、ミステリーホラーの鉄板テンプレートともいえる。『犬神家の一族』の因子は、『金田一少年の事件簿』、『TRICK』、『零』シリーズ、『ひぐらしのなく頃に』といった漫画・アニメ・ドラマ・ゲームに受け継がれ、我々もその世界観を(『犬神家』を観ている・観ていないに関わらず)知らず知らずのうちにプリセットしている。
『ゲゲゲの鬼太郎』には関心がなくても、『犬神家』の匂いに惹かれて劇場に足を運んだ観客も多かったはずだ。
(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)
引用元: ・【映画】「おぞましくて陰鬱」なのに女性ファンが劇場に殺到…『鬼太郎の誕生 ゲゲゲの謎』がかつてないブームを巻き起こした理由 – 文春 [湛然★]
オマージュと言うやつなんだろうが
犬神家のパクりなんだが良くできてる漫画の一作目に上手くつながる最後











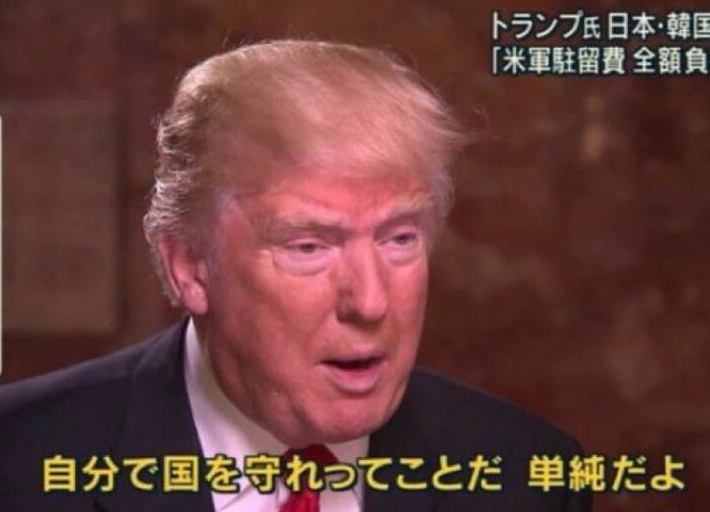


コメント