7/6(日) 11:46 ふたまん+(徳江風波)
https://news.yahoo.co.jp/articles/e78a9f068d7ce120949608fcaee6c6fd4a19e2a2?page=1
■大前提!リセットに込められた意味とは?
まず前提として、ファミコンは非常にデリケートなものだった。母親の掃除機がコツンと本体に当たったり、猫の足がコードに軽く触れたりするだけでもすぐにストップしてしまう。カセットに搭載されているセーブ機能は、導入された当時は非常に繊細であり、それだけですぐにデータが消えてしまうようなもろさだった。
そもそもファミコン当初にはバッテリーバックアップは想定されておらず、セーブ機能は、当時のソフト開発者たちが苦労して取り入れたもの。そのため、まだまだ不完全な部分があり、電源を切るタイミングや状態によって、最悪の場合セーブデータが消えてしまうこともあった。
そんなデリケートな仕組みとはどういったものだったのか?
当時の技術ではゲームデータをカセットに記録する際、少しでもデータにエラーがあれば、安全のためにセーブデータを消してしまう仕様だったのだという。
そのエラーは、ゲームが動作しているときに電源を切ってしまうと起こりやすい。ゲームが動いているということは、カセットのメモリとファミコン本体との電気信号が激しく行き来している状態だといえば分かりやすいかもしれない。
そんな状態の途中で電源を切ると誤動作を起こしやすく、データの書き込みや読み込み時にエラーが生じやすいということなのだ。
そのため、リセットボタンを押すことでゲームとファミコンの動作をストップさせ、そこから電源を切ることで安全にゲームを終えることができるのである。
だが、当時の子どもたちにそんな詳しい説明をしても理解できない(筆者もコンピュータのシステムに詳しくないので今でもよく理解できない)ため、『ドラクエ3』では「りせっとをおさずにでんげんをきるとぼうけんのしょがきえてしまうばあいがあります」とメッセージで注意喚起した。冒険の書が消えた際には呪われた音楽を流すという演出まで盛り込み、わかりやすくプレイヤーに恐怖心を植え付けつつ、リセットボタンを押して電源を切る流れを学ぶように仕向けたのだろう。
だが、当時はそれこそセーブ機能が不完全な時代であり、前述したようにカセットにちょっとショックを与えただけでセーブデータが消えることはよくあった。それこそ赤子をあやすかのごとくカセットを扱っていた人も多い。
注意したにもかかわらずデータが消えてしまい、「なんやねん、もう!」と怒り、嘆いたプレイヤーは星の数ほどいるのではないか。
プレイヤーたちは、祈りを込めて儀式のようにリセットボタンを押すようになったわけだ。
■逆に「リセットしながら電源を切ってはいけない」というソフトも存在した
ところが、すべてのファミコンソフトにこのリセットの儀式が有効だったわけではない。むしろ、一部のソフトでは「リセットボタンを押したまま電源を切ってはいけない」という、真逆の注意が必要なタイトルも存在していたのだ。
たとえば『ドラクエ3』と同じ年に発売された『三国志 中原の覇者』(1988年、ナムコ)は、ソフトの説明書に赤文字で「リセットボタンを押しながら電源を切らないでください」と、はっきり書かれているのである。
(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)
引用元: ・【芸能】ファミコン時代の神聖な儀式「リセットボタンを押しながら電源を切る」はなぜ必要だったのか [湛然★]
ゆっくり抜いてフーフーだろ
せめて電源OFFにしてからカセット抜けよ…
貝獣物語何回もデータとんだわ
というタイトルもあるよね










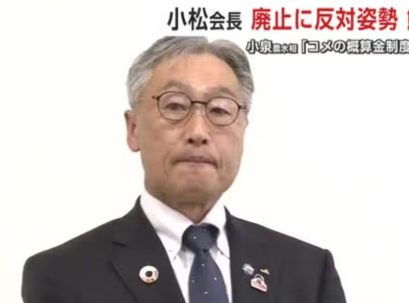

コメント