この条例では、カスタマーハラスメントに該当する行為や「就業者」の定義が示されているが、ガイドラインをよく読むと、一見「就業者」とは思えない立場の人々も対象に含まれている。
いったい、こうした人々はどのような被害を想定して記載されたのか。
担当部署を訪ねて話を聞くと、そこには予想外の回答があった。
東京都のカスハラ防止条例で保護の対象となる意外な「就業者」
社員や店員だけじゃない! PTA、自治会役員、議員もカスハラ対象に
今年4月から東京都・北海道・群馬県・三重県桑名市など、全国複数の自治体で施行開始された「カスハラ防止条例」。
制定がもっとも早かったのは東京都で、昨年10月4日に条例を制定し、12月25日には『カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)』も公開。
このガイドラインでは、カスハラに該当する行為の例や、顧客・就業者の定義などが紹介されている。
なかでも注目すべきは、保護の対象となる「就業者」の範囲だ。
定義によると、「就業者」とは〈労働者だけでなく、有償・無償を問わず業務を行うすべての者〉を指すという。
具体例として、企業の従業員や公的機関の職員のほか、PTA役員や自治会役員、議員、家族従事者などが挙げられている。
カスハラといえば、従業員と客とのトラブルというイメージが一般的だ。
しかし、こうした多様な「就業者」が保護対象に含まれることからも、条例が想定する範囲の広さがうかがえる。
なかでも自治会やPTAといった組織は、「客」に相当する存在や、カスハラに該当する行為がイメージしづらいと感じる人も多いのではないだろうか。
そこで、「カスハラ防止条例」の担当部署である東京都産業労働局・雇用就業部労働環境課に、直接話を聞くことにした。
まず話を聞いたのは、自治会役員に関するケースである。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/15d7480175c1104239e60b6d1e7f99f266d01b60
引用元: ・【カスハラ防止条例】「夏祭りがうるさい」で認定対象に!? ユーチューバーによる“警察官の職務質問撮影”は?…東京都の担当者に聞いた認定の範囲
地域の要注意人物を特定します
ジャンル別に把握しておきます
昼間ならセーフってこともないだろ
うるさいものはうるさいこれ当たり前
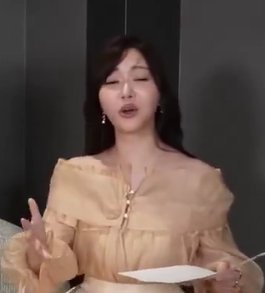








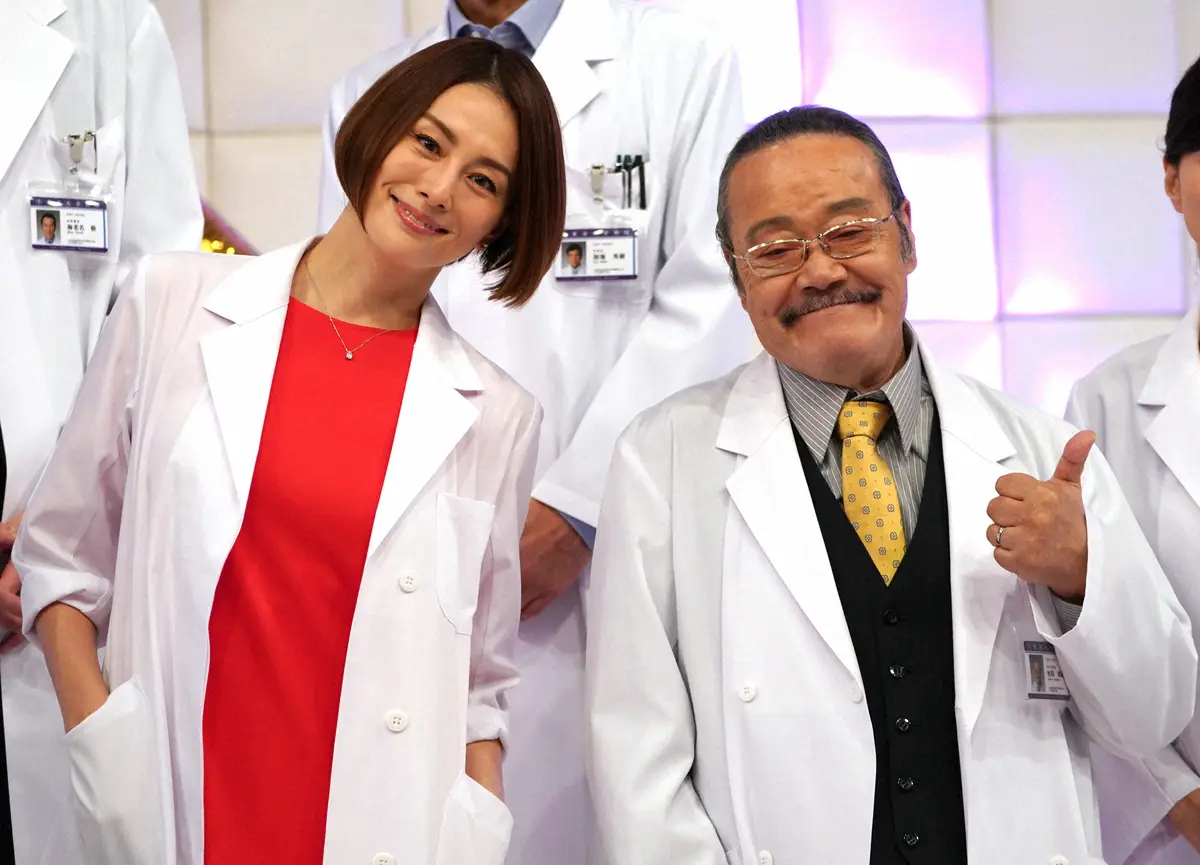


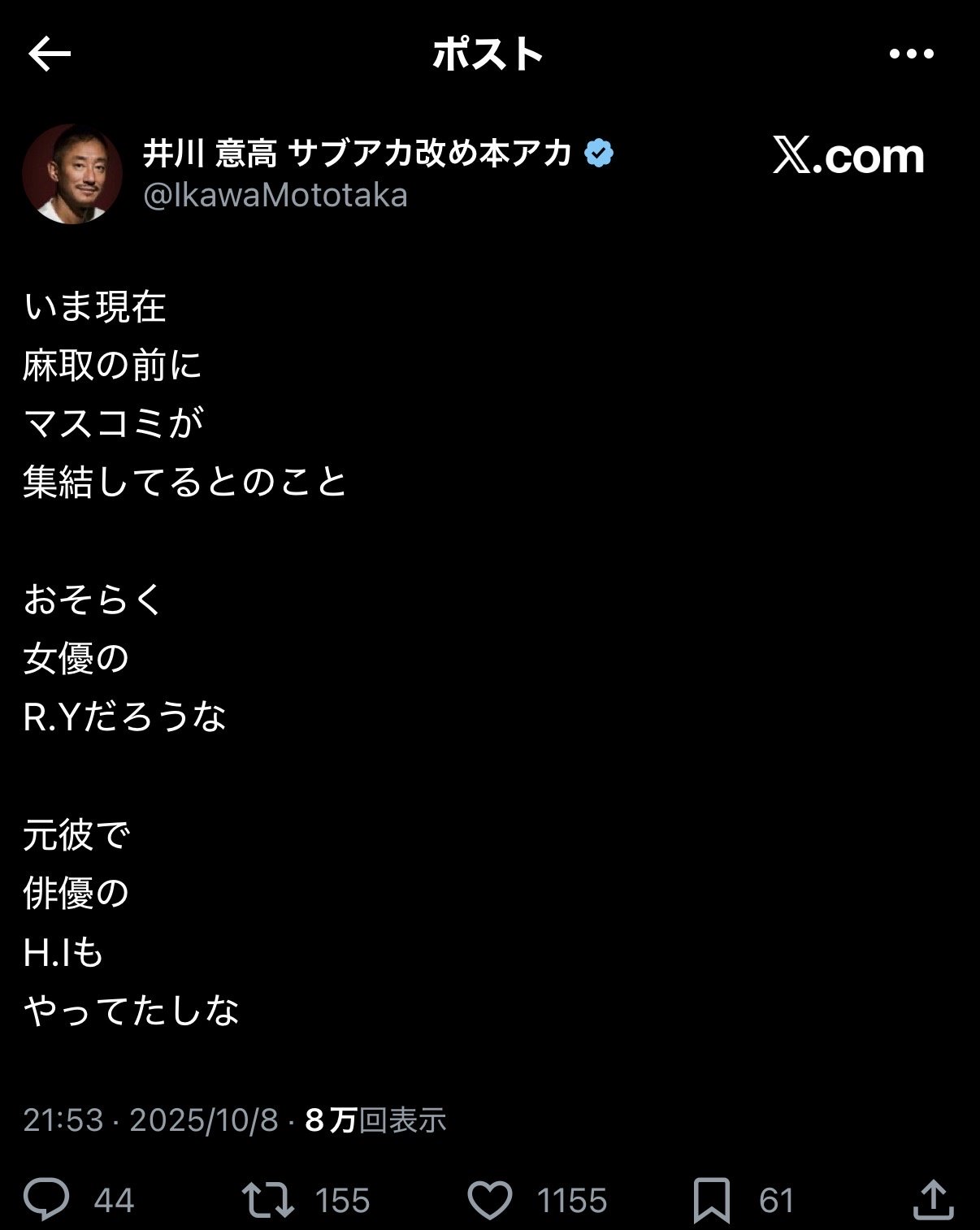

コメント