いわゆる『就職氷河期世代』の支援をめぐる議論が、与野党で活発化しています。就職氷河期世代の中には、「違う時期に生まれたかった」と悔やむ人もいます。
就職氷河期世代とは、バブル崩壊後の1993年から2004年の雇用環境が厳しい時期に就職活動をした世代です。4月時点で、
●大卒であれば、大体43歳~54歳、
●高卒であれば、大体39歳~50歳の方々が該当します。
就職氷河期世代の中には、厳しい就職活動などによる影響で、今なお不安定な仕事や長い失業状態にあり、支援が必要な人が約80万人いるとみられています。
不遇だとされる就職氷河期世代ですが、どのような厳しい状況にあってきたのでしょうか。
【10代】
1980年代後半から90年代前半ですが、就職氷河期世代は、団塊ジュニア世代と重なっていて、人数が多いです。結果、受験の競争率が高くなりました。
【20代】
1990年代、バブルが崩壊し、就職率が低くなり、非正規労働者が増えました。
【30代】
2000年代の不景気とデフレで、給料と株価は上がらず、その影響もあって、未婚率が高くなりました。
【40代】
2010年代です。管理職になる世代ですが、就職氷河期世代の一つ上の世代はバブル世代で、会社の中でも人数が多く、社内の多くのポストを占めてしまいます。
結果、就職氷河期世代がつけるポストは、少なくなりました。
【50代以降】
両親の介護に携わる人も増えますが、少子高齢化の影響で、介護費が増えます。1974年生まれ、2025年に51歳になる人は、全体の4割が年金が月10万円未満になるという試算です。
就職氷河期世代の50代、現在求職中の方です。「(新卒の時の)就活では、履歴書を300社以上に送った。ようやく内定をもらえた会社は、高校生に高額な教材を売りつける悪徳業者。パワハラも横行し、半月でやめた」
「非正規で働いていた期間が長く、彼女もいたが、経済面が心配で結婚に踏み切れず。現在は実家暮らしで求職中だが、病歴(がん)があり、苦戦している」
「違う時期に生まれたかった。成功している人もいるので、なんとも言えないが、格差があまりに激しいので残念には思う」
就職氷河期世代の貯蓄です。世帯主の年代別にみた1世帯あたりの貯蓄額のグラフですが、青が2018年、赤が2023年です。20代、30代、40代、60代では、この5年で増えていますが、50代のみ貯蓄額が減少しています。
年代別の賃金の伸び率です。コロナ前の2019年と2024年を比較すると、20代から50代に向って伸び率は低くなり、50歳~54歳で最も伸び率が低くなっています。
第一生命経済研究所主席エコノミストの永濱利廣さんによると、「就職氷河期世代の賃金は、入社するときも、中高年になってからも、低く抑えられている状況。雇用形態が不安定かつ、収入が低い結果、資産形成で割を食っている」ということです。
就職氷河期世代への支援を、各党がアピールしています。人口ピラミッドを見ると、就職氷河期世代は約1700万人いて、これが7月参院選の大票田となっています。
第一生命経済研究所主席エコノミストの永濱さんによると、「就職氷河期世代が、将来の社会保障財政のカギも握っている」ということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5daedbecd0202673e74a14bfb695004c9406e93c
引用元: ・【1974年生まれ、全体の4割が年金月10万円未満に】就職氷河期世代 「違う時期に生まれたかった、格差があまりに激しい」 厳しすぎる現実







、共演男性の『膝の上に座る』のが得意技だった_501002.jpg)



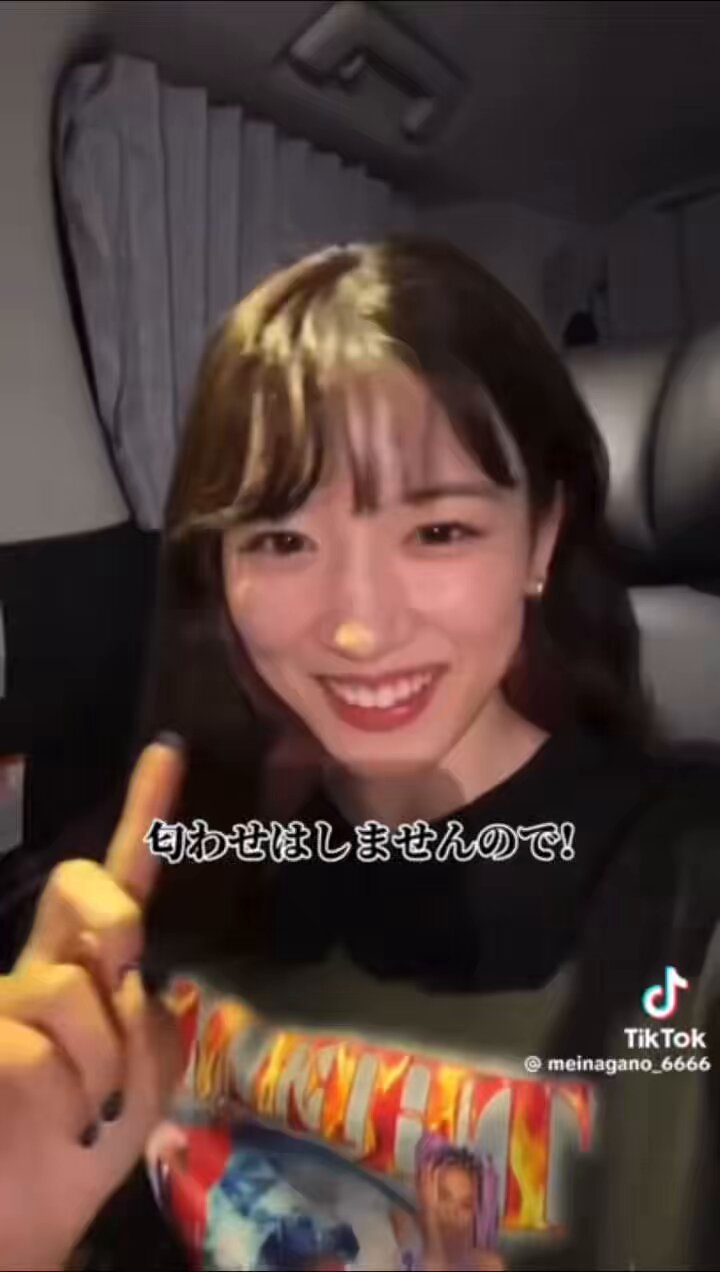



コメント