https://news.yahoo.co.jp/articles/c650e61af142ba23052b9da026b458bcc33e498f
「各拠点から集めたエクセルの形式がバラバラで、人手による集計にも膨大な時間がかかっていました。ミスも発生しやすく、データの精度にも課題がありました」
総合商社の伊藤忠商事(以下、伊藤忠)で、IT・デジタル戦略部デジタル戦略室、プロジェクトマネージャーの吉嵜瑞穂さんはこう話す。
伊藤忠は、この春までにグループ約600拠点に温室効果ガスの排出量をはじめとした環境データの集計・算定システムを導入。3月に本格稼働を開始した。生物多様性や廃棄物といった複数の環境データのほか、温室効果ガスの排出量データの収集を「脱エクセル化」し、業務の効率化・精度向上を狙う。
背景を取材すると、単なる業務効率化にとどまらない「企業価値向上」にかける強い意志が見えてきた。
引用元: ・伊藤忠、600拠点「脱エクセル地獄」で企業価値アップ狙う。総合商社の泥臭いリアル [662593167]
■現場で感じた「脱・エクセル地獄」の必要性
吉嵜さんは
「IT・デジタル戦略部でESGや非財務情報を用いたDX関連のビジネスを検討していく中で、グループ会社や伊藤忠全体のESG情報の収集精度や状況を調べていました。そこで(データの収集や管理を)全てエクセルでやっていることを知ったんです」
と、プロジェクトのきっかけを語る。
実際、温室効果ガスの排出量をはじめとした「非財務情報」の収集は、伊藤忠に限らずいまだに表計算ソフトを用いた“手作業”で行われることも多い。
伊藤忠のサステナビリティ推進部の人数は20人程度。このうち環境関連のデータを取り扱う人材は一部だ。グループの全拠点から送られてきたデータを、この人数で取りまとめるのは大きな負担だった。
「このままでは、本来注力すべきデータの分析や改善策の検討に時間を割けない。そうした問題意識から、ツール導入の話が進み始めました」(吉嵜さん)
伊藤忠としても、人的資本の強化やESGへの対応といった「定性面」を磨き、企業ブランド価値の向上を図ることは経営方針のキーワードにもなっていた。
同社IT・デジタル戦略部長の浦上善一郎さんは、非財務情報の開示を強化してきたことで、第三者機関からの評価やESG銘柄としての選定など、「外部からの評価も上がってきている」とその効果を語る。
温室効果ガスの排出量算定をはじめ、非財務情報の開示要求は年々強まっている。
米トランプ政権が反ESGを唱えていたとしても、世界的な大きな流れは変わっていない。日本でも、2027年3月期の有価証券報告書から時価総額3兆円以上の企業に対してサステナビリティ情報の開示が義務化される方針だ。
こういった環境下で企業価値をさらに上げていくには、単に数値を計測するだけではなく、数値を分析して改善にどうつなげていくか、道筋を示すことが求められていた。非財務情報の収集・管理が将来的に内部統制の対象となってくる可能性を見据えると、システムによるデータ精度の向上やプロセスの明確化は「ガバナンスの強靭化」にもつながる。
■システム導入「逆に身動き取れなくなるのでは」
伊藤忠が今回構築したシステムで収集するのは、廃棄物や生物多様性といった環境データと、燃料の直接消費や間接消費分にあたるスコープ1~2※と呼ばれる温室効果ガスの排出量データ。計算が複雑になるサプライチェーンに関係するスコープ3のデータは、カンパニー(部門)ごとの商習慣の違いなどもあり、今回のプロジェクトからは切り離した。スコープ3の集計や、人的資本などのほかの非財務情報については、今後の課題だ。
システム導入を見据えたプロジェクト案の策定が始まったのは、2022年春。プロジェクトを進めていく上ではさまざまな課題があった。
議論がスタートした当時は、国内外で規制や開示基準が乱立しており、準拠すべきルールが固まりきっていない状況だった。定式化したシステムを導入することで「逆に身動きが取れなくなるのでは」と、反対する声もあった。
「エクセルへの手入力」の方が、どんな規制、開示基準にも「柔軟」に対応できる面があったわけだ。
ただ、浦上さんは
「有価証券報告書に記載が求められるようになると時間も限られ、業務が難しくなってきます。できるだけ効率化するべきですし、過去との比較をして分析することに時間を割くところに意義があります」
と、将来を考えると現状のスタイルを変える合理性があったと指摘する。
システムの導入によって、ノウハウを個人ではなく組織に蓄積する仕組みを構築できることも大きかった。ジョブローテーションのある組織の中で長期的に改善を進めていく地盤ができれば、継続的な取り組みが期待できる。
伊藤忠では、サステナビリティ推進部とIT・デジタル戦略部がそれぞれ業務主管、システム主管として連携し、半年から1年ほどかけてさまざまなベンダーにツール導入のメリット、デメリットをヒアリングしながら、議論を積み重ねていったという。






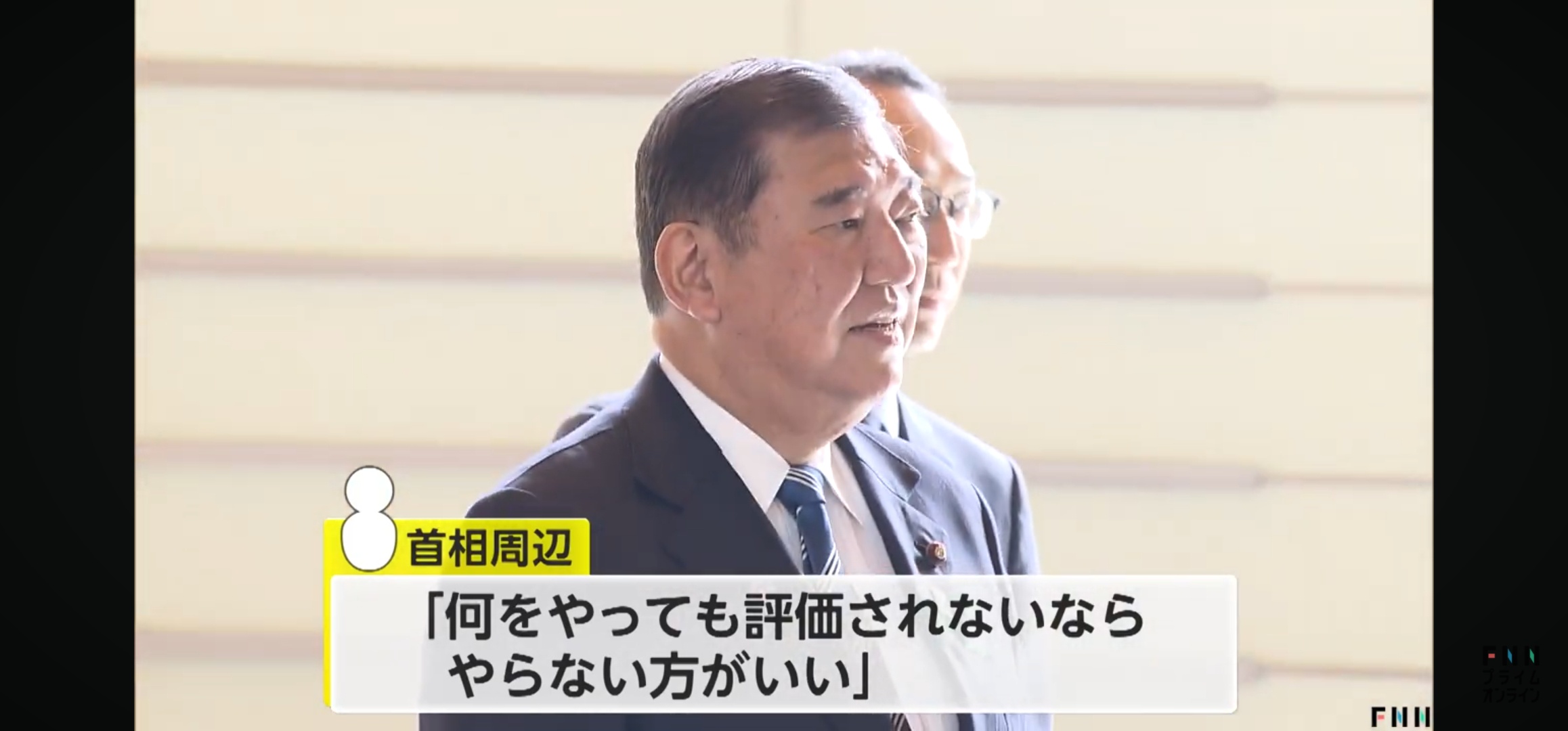


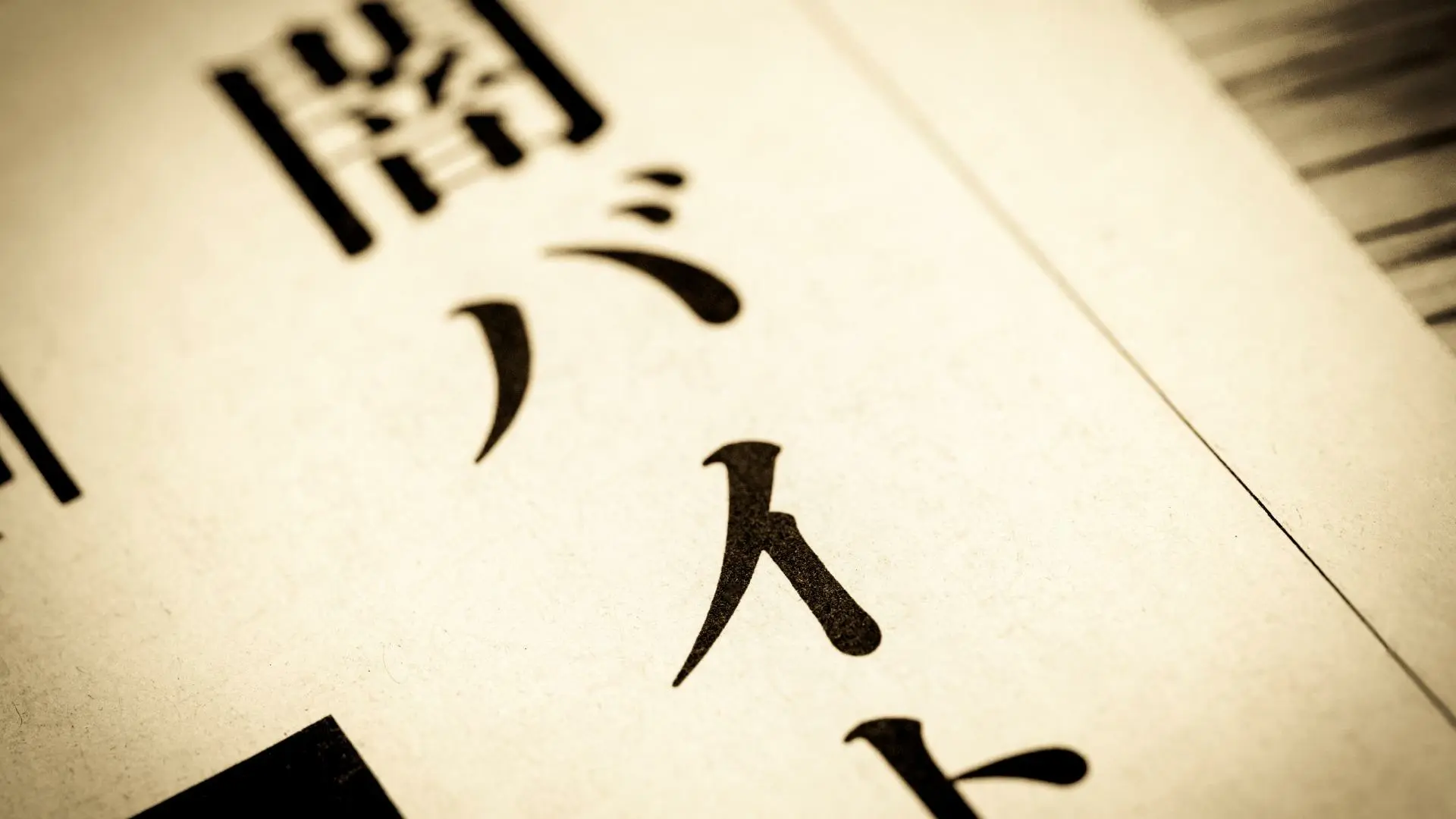

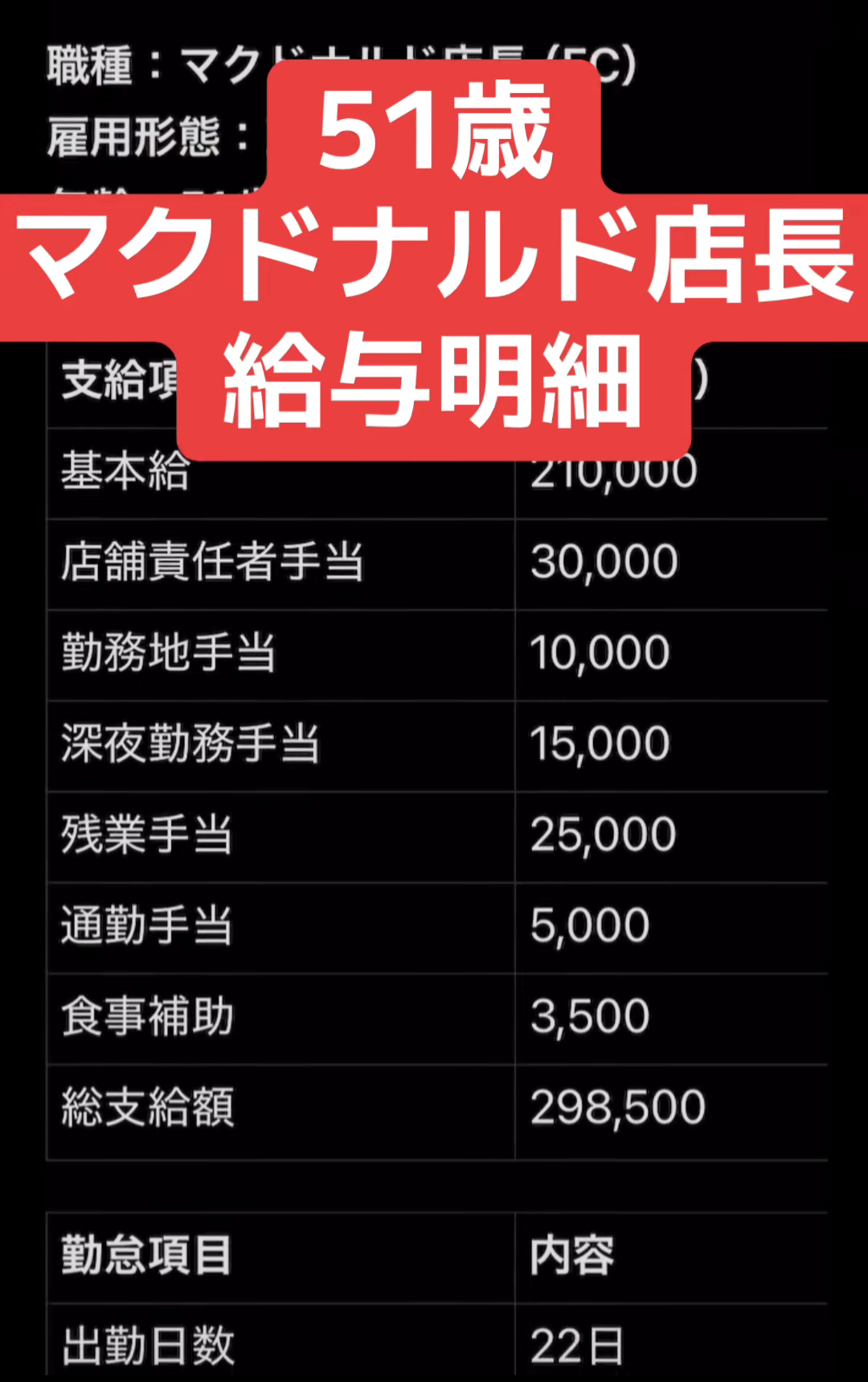


コメント