であれば「今までの倍売れる細見を作る!」「それが倍売れたら板元となることを認めてほしい!」と啖呵を切った蔦重は、その約束を問屋仲間たちに認めさせる。かくして、周囲の人々の協力もあり、これまでにない工夫を凝らした新しい吉原細見『籬の花』を完成させ、地本屋たちから好評を得て大はしゃぎの蔦重。そんな彼を横目に、鶴喜は「倍売れるかもしれませんが……」と意味深な表情でつぶやくのだった。
ここまで『べらぼう』を観てきて思うのは、とにかく「悪い人間」――もとい、「腹に一物がある人間」ばかりが登場するということだ。吉原を取り仕切る「忘八」たちはもちろん、おっとり刀で市内の地本問屋を取りまとめる「鶴喜」、もともと鱗形屋と共謀して蔦重を利用しようと企んでいた西村屋与八(西村まさ彦)も、なかなか狡猾な人物だ。それは江戸城内の人々も同様である。
改革の推進者であり、初回では蔦重に貴重な助言を与えた老中首座・田沼意次(渡辺謙)。一見すると立派な人物であるように思える田沼だが、賄賂を受け取ることには特に抵抗はなく、登場するたびに満面の笑顔で不穏な雰囲気を漂わせる一橋治済(生田斗真)をはじめ権謀術数渦巻く城内で、ときには書類の偽装もいとわないなど、目的のためならば手段を選ばぬ人物でもあるようだ。そんな田沼と蔦重を結び付けた平賀源内(安田顕)も、ただ愉快な好人物というわけではなさそうだ(書類の偽装は源内が行った)。しかし、彼ら全員が「悪人なのか?」と問われると、必ずしもそうではないように思えるのだった。
「面白い青本を作ろう!」と意気投合し、蔦重と大いに盛り上がった鱗形屋。明和の大火で多くの板木と紙を失い、経営は火の車だという彼の「面白い青本」に対する情熱には、嘘がなかったようにも思える(実際それは『金々先生栄花夢』として近々形になるだろう)。そして、西村屋の「永寿堂」、鶴喜の「仙鶴堂」は、当時の江戸を代表する板元だ(その後、そこに蔦重の「耕書堂」が加わることになる)。その主人を「悪人」のひと言で片づけて、果たして良いのだろうか。それは田沼意次や平賀源内についても同じだろう。「清廉潔白な人物か?」と問われると、どうやらそうではないように見えるけれど、だからと言って、彼らが成し遂げたことを無視するわけにもいかないだろう。ややや、何やら近頃SNSなどで見掛けるような話になってきた。
いや、それを言ったら、本作の主人公・蔦重だって、必ずしも清廉潔白ではないだろう。「吉原で働く女たちのために!」と、旧態依然とした業界に疑問を呈し、自ら率先して行動に出てきた彼だって、決して「純朴な善人」というわけではなく、それなりの「打算」があるわけで。それが「吉原のため」になるのであれば、長谷川平蔵(中村隼人)のような血筋自慢の世間知らずを、ニッコリ笑顔でカモにすることも忘れない。磯田湖龍斎(鉄拳)に描いてもらった絵が台無しになったとき、それを唐丸(渡邉斗翔)に模写させて、しれっとやり過ごしたのも、なかなかと言えばなかなかだ。そして、鱗形屋が偽板作りに関与していることに、誰よりも早く気づいたときも……。そう、どうやらこのドラマには、完全な「悪人」も完全な「善人」も存在しないのだ。否、むしろ「それらが入り混じっているのが人間なのではないか」という強い信念のもと、本作は生み出されているように思うのだ。そもそも「吉原」という場所にしても……。
続きはソースで
https://realsound.jp/movie/2025/02/post-1936757.html
引用元: ・【大河ドラマ】『べらぼう』はなぜ新しい大河なのか “完全な善人も悪人”も存在させない森下佳子の信念 [ネギうどん★]
金と銀みたいに10話前後なら面白かったと思う
つまらん大河
吉原とかどうでもいい











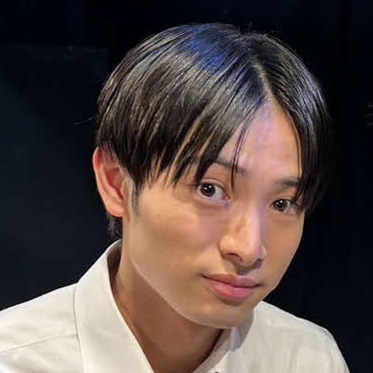


コメント