プロのスポーツ選手は現実の世界に生きるスーパーヒーローかもしれないが、不死身ではない。それを象徴したのが、9月12日に行われたNFL(全米プロフットボールリーグ)の試合で、マイアミ・ドルフィンズのスター選手、トゥア・タゴバイロアが倒れた場面だ。
バッファロー・ビルズに31対10とリードされた第3クオーター、クオーターバック(QB)のタゴバイロアはファーストダウンを狙って走った。
そしてビルズのディフェンダーに向かって頭を下げて突っ込み、そのまま倒れた。NFLでプレーを始めて3度目の脳震盪(のうしんとう)だった。
先ごろ発表されたハーバード大学の研究によれば、元NFL選手の3人に1人が「自分は繰り返し頭部を負傷したことに関連する脳の慢性疾患を抱えている」と考えているという。
ショッキングな数字だが、この種の脳の疾患を確定診断する方法は、死後の解剖以外にないのが現状だ。
だが将来、血液検査がそうした目にも見えなければCTスキャンにも映らない脳の損傷を診断する一助となるかもしれない。そうすれば、脳の傷が癒えないうちに選手が試合に復帰することも防げるかもしれない。
タゴバイロアがやったことは自らの体を犠牲にしてチームのために戦うという、QBに期待される行動だった。だが、そうした自己犠牲の考え方はもう古い。話が脳への打撃となれば、なおさらだ。
サッカー界でも、頭部のけがが疑われる選手に対して「脳震盪による選手交代」が通常の交代枠とは別に認められるようになった。子供たちのヘディングを制限する動きも広がっている。
脳震盪を含む外傷性脳損傷は、スポーツの世界でもそれ以外の場所でも珍しくない。アメリカでは、外傷性脳損傷が原因の救急搬送が年に480万件に上る。
適切な治療と支援がないと、脳震盪は記憶障害や人格変容、睡眠障害、心の問題、認知症などの神経変性疾患といった長期的な影響を残す可能性がある。頭部への衝撃が繰り返される場合は、なおさらだ。
問題は、プロの選手だけにとどまらない。ダートマス大学のアメフトチームで活躍していたパトリック・リシャがいい例だ。
「私たち家族は2014年、パトリックを自殺で失った」と語るのは、母でパトリック・リシャCTE啓発財団の代表を務めるカレン・ジーゲルだ。
「当時は自分たちが抱えている問題の正体が分からなかった。息子には鬱やADHD(注意欠陥・多動性障害)、依存の問題、不安、睡眠障害の明らかな症状があったが、スポーツをやっていたせいだとは思いもしなかった。CTE(慢性外傷性脳症)のことも、脳を調べたほうがいいと言われて初めて知った」
アメリカを代表する医療機関であるメイヨー・クリニックの定義によれば、CTEは「繰り返し受けた頭部外傷が原因となった可能性の高い脳障害で、
脳の神経細胞の死(変性)を引き起こす。確定診断の方法は死後の解剖のみ」という疾患だ。
脳が損傷を受けるのはプロかアマかを問わない。NFLの偉大なランニングバック(RB)だったトニー・ドーセットはかつて、記憶障害や感情の爆発といった問題を抱えていて、これらはCTEの症状かもしれないと語ったことがある。
11年の夏には、NHLでエンフォーサー(乱闘で活躍する選手)として知られていたデレク・ブーガードら3人が相次いで急死し、いずれもCTEだったことが判明した。
20年に死亡した米サッカー選手のスコット・バーミリオンも、死後にCTEと診断された。
「パトリックが脳震盪の診断を受けたことはなかった」と、ジーゲルは言う。「アメフトや脳震盪に関して、弱音を吐いたこともない。でも結局は生き続けられないほど、苦しみに耐えられないほどに脳を破壊する病気を背負い込んでしまった」
https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2024/12/530596_1.php
引用元: ・【アメフト・サッカー】死後に判明するケースが相次ぐ、脳震盪が記憶障害、睡眠障害、心の問題、認知症に繋がることも・・・子供たちのヘディングを制限する動きも広がっている
まともだったのに~♪
、ガチでやばい死に方してた模様…_633225.jpg)


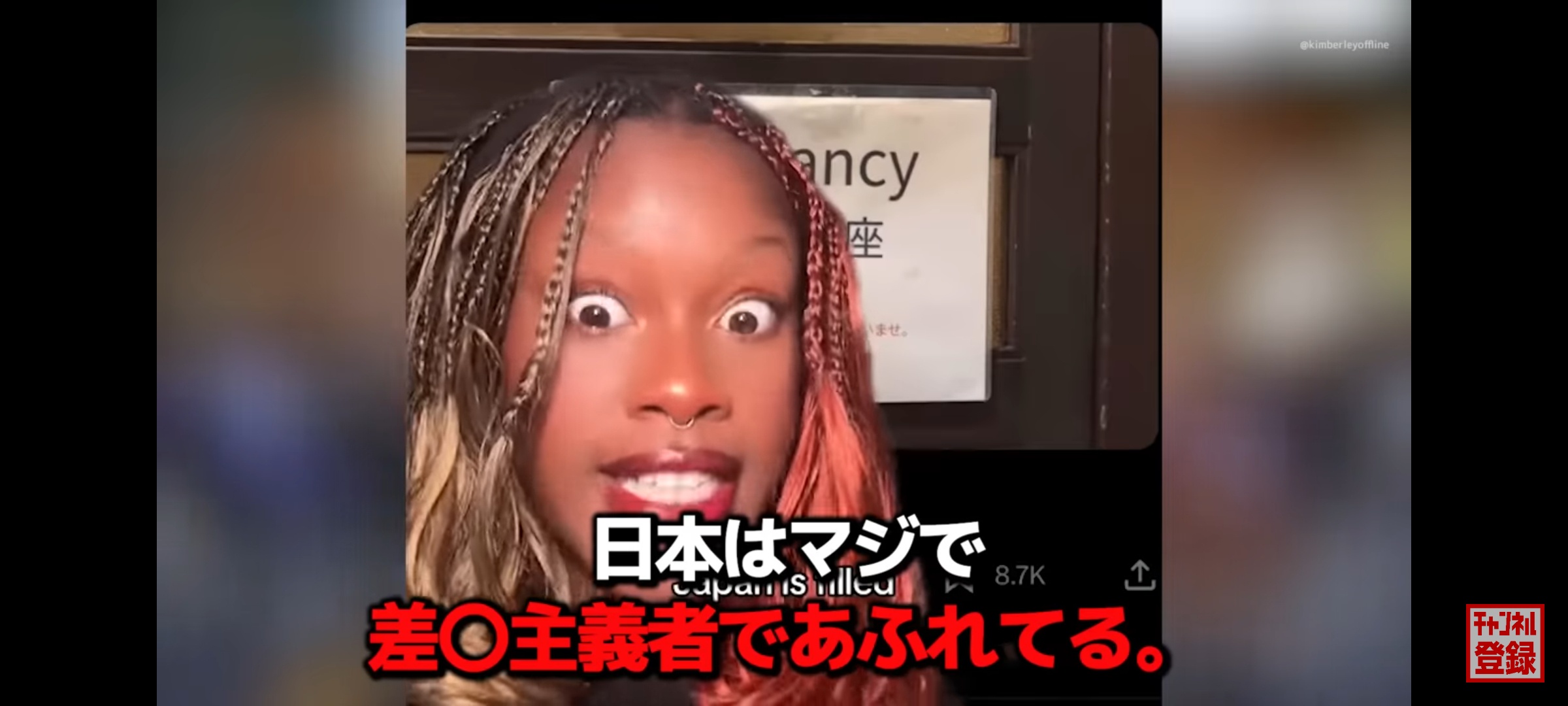











コメント